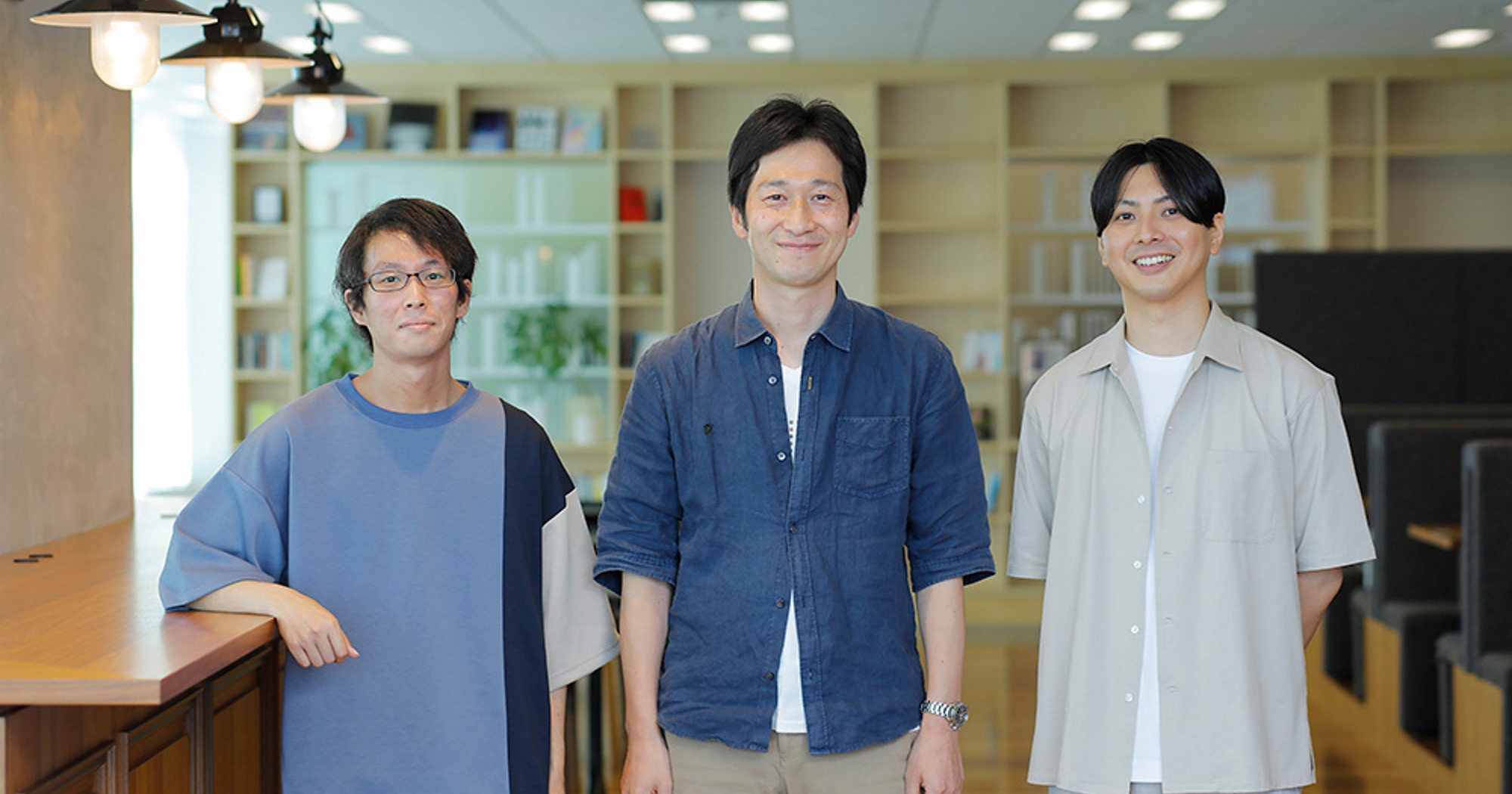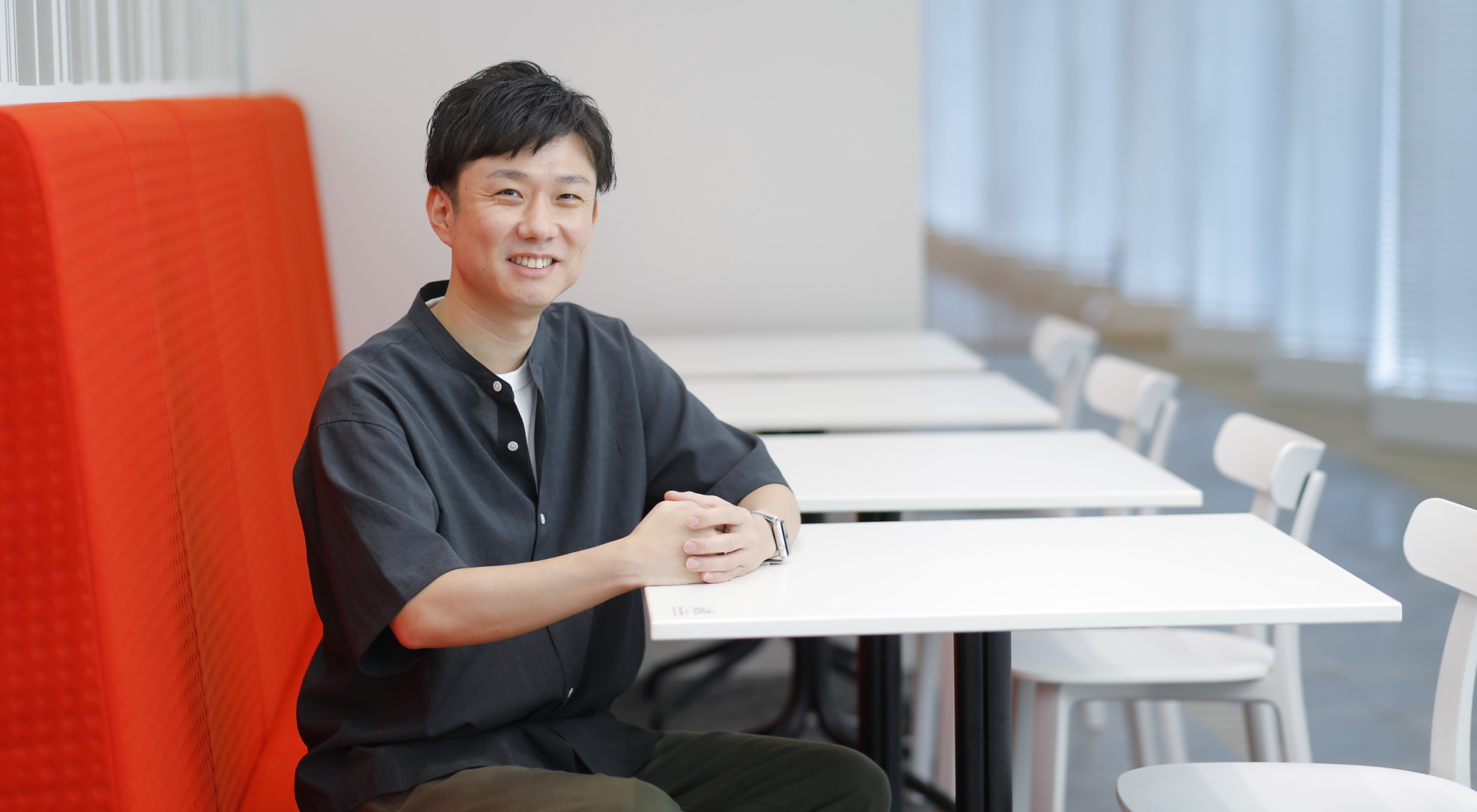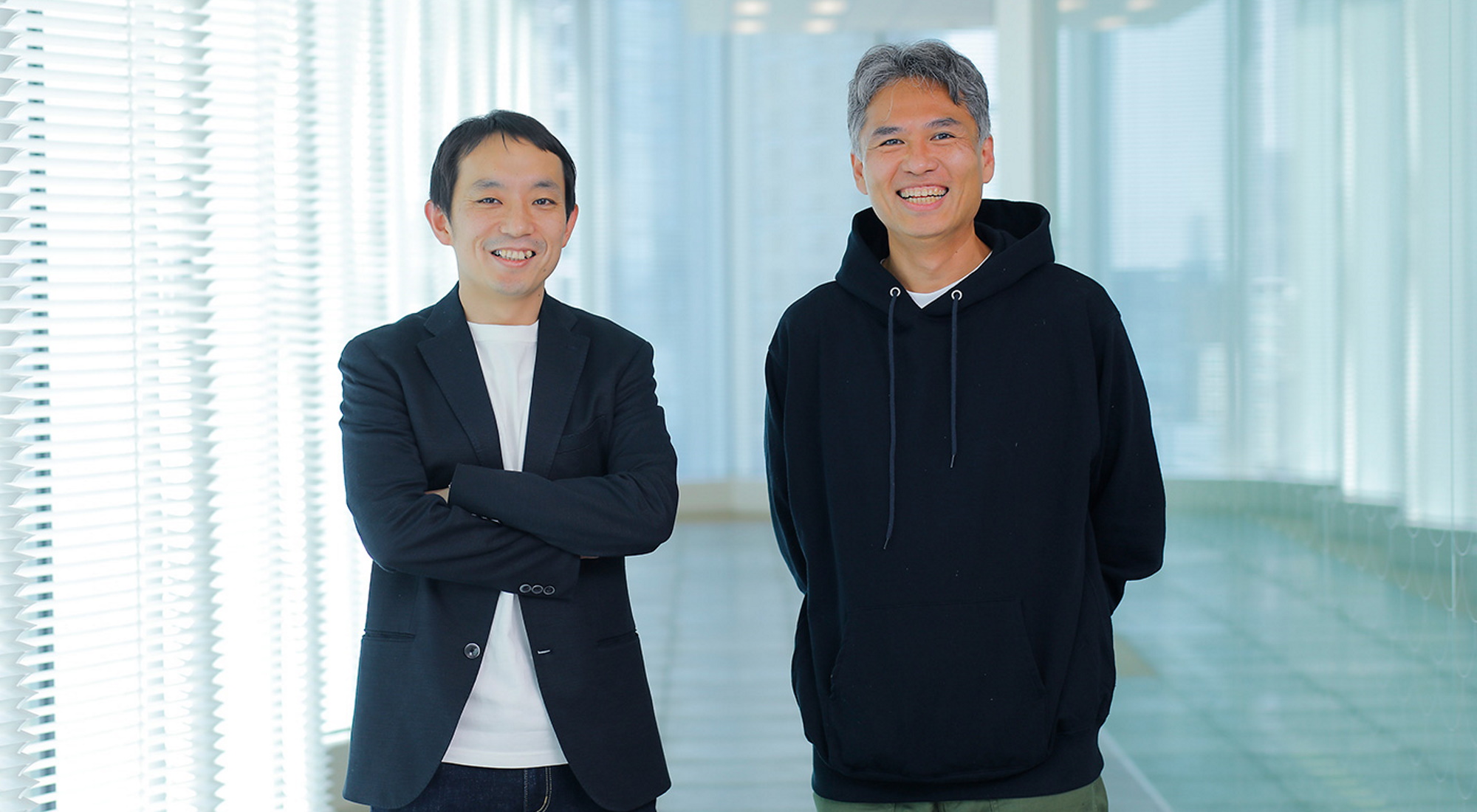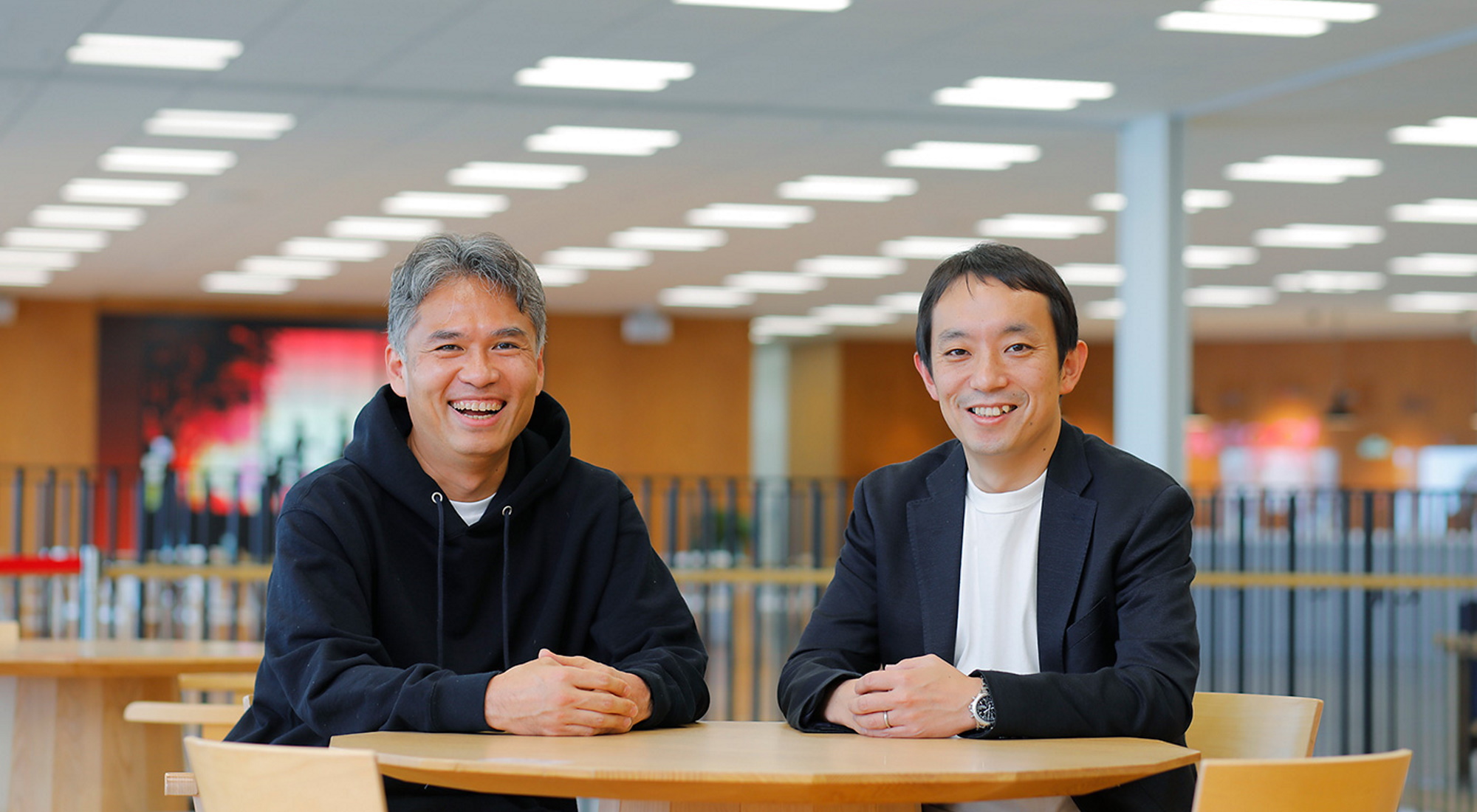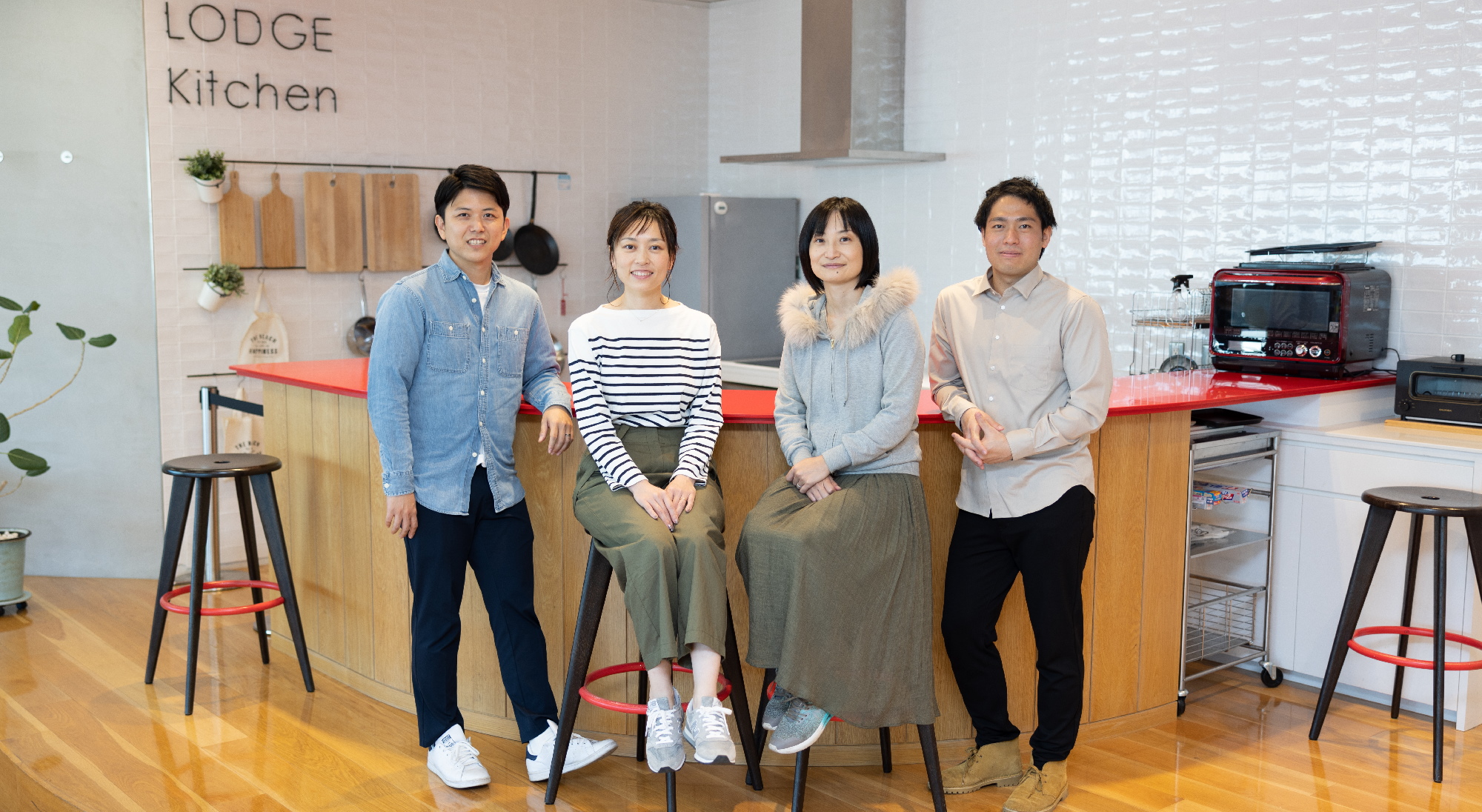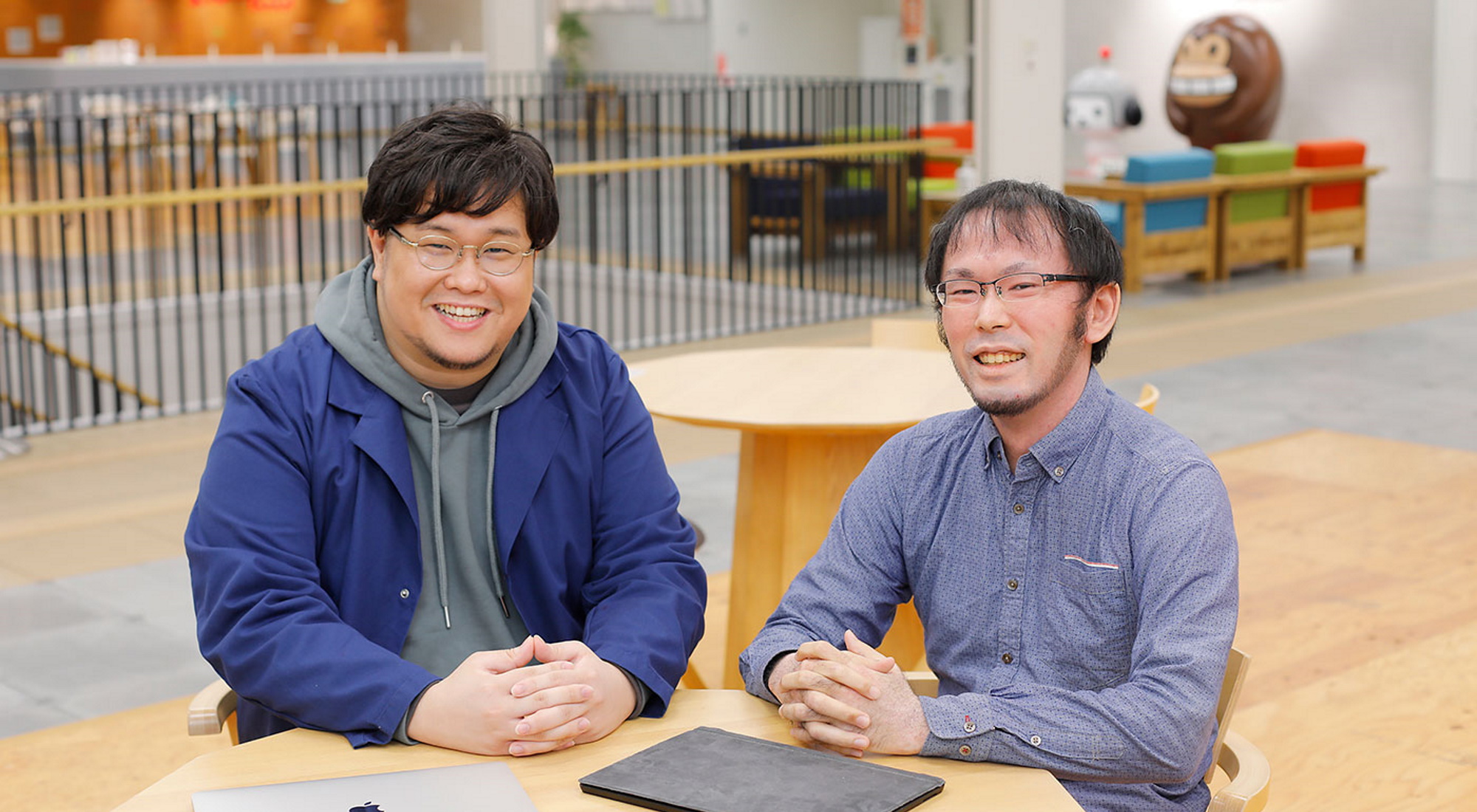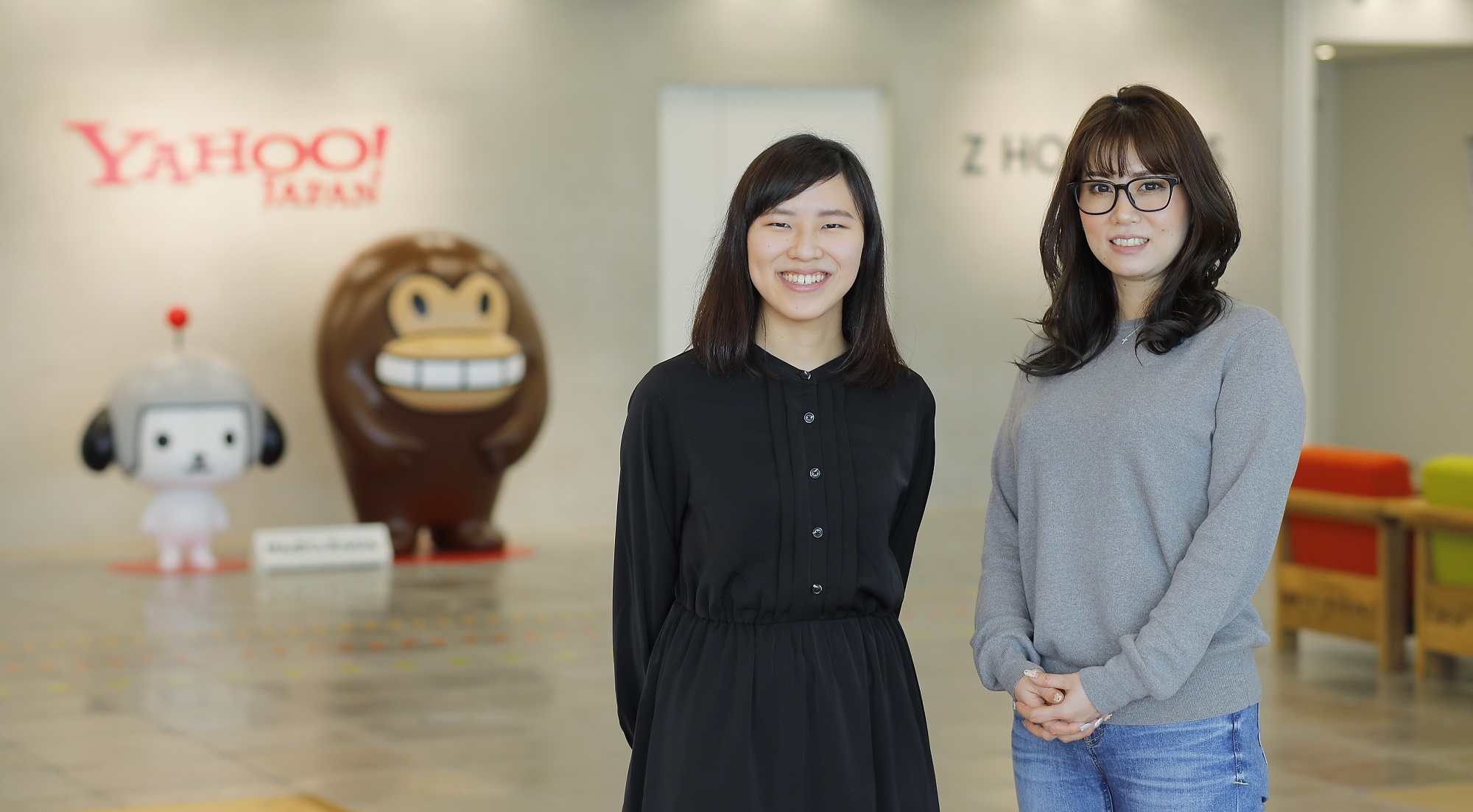プロフィール

- 澤田 正稔
ヤフオク!統括本部 プロダクション2本部 本部長兼VPoE - 2004年にヤフーに中途入社。エンジニアとしてYahoo!ショッピング、ヤフオク!などを担当し、2018年より現職。

- 三宅 晃暉
ヤフオク!統括本部 フリマ推進本部 フリマ開発2部 部長 - 2016年新卒入社。入社以来、商品情報を扱う開発エンジニアとして活躍。2018年より、PayPayフリマに立ち上げから携わる。

- 林 祐大
ヤフオク!統括本部 フリマ推進本部 フリマ開発2部 - 2016年新卒入社。営業、マーケティング、プロダクト企画を経て、2022年よりエンジニア主務。現在は、開発や設計を担当。
手軽で使いやすいフリマサービス「PayPayフリマ」誕生の舞台裏
──まずは、2019年に誕生した「PayPayフリマ」についてお聞かせください。
ヤフオク!のサービス開始は1999年。20年以上にわたるインターネットオークションサービスの草分けであるヤフオク!の資産を引き継ぎながら、PayPayフリマは誕生しました。私はヤフオク!とPayPayフリマの両方のサービスを担当するVPoEを務めています。
PayPayフリマは、ヤフオク!からフリマ向けのサービスを切りだすことに特化した事業です。例えば、ヤフオク!には「競り」と「即決」という機能がありますが、PayPayフリマは個人間での取引にフォーカスし簡単に取引ができるサービスとなっています。
ヤフオク!の多岐にわたる機能をシンプルにし、垣根を低くすることで、これまでオークションサービスを使ったことがないユーザーにも、気軽に使ってもらえるように始めたのがPayPayフリマなのです。
幸いにも、PayPayフリマはこの2年間で急成長しており、アプリダウンロード数もローンチ1カ月で100万を達成し、現在は累計で1000万ダウンロードを越えています。
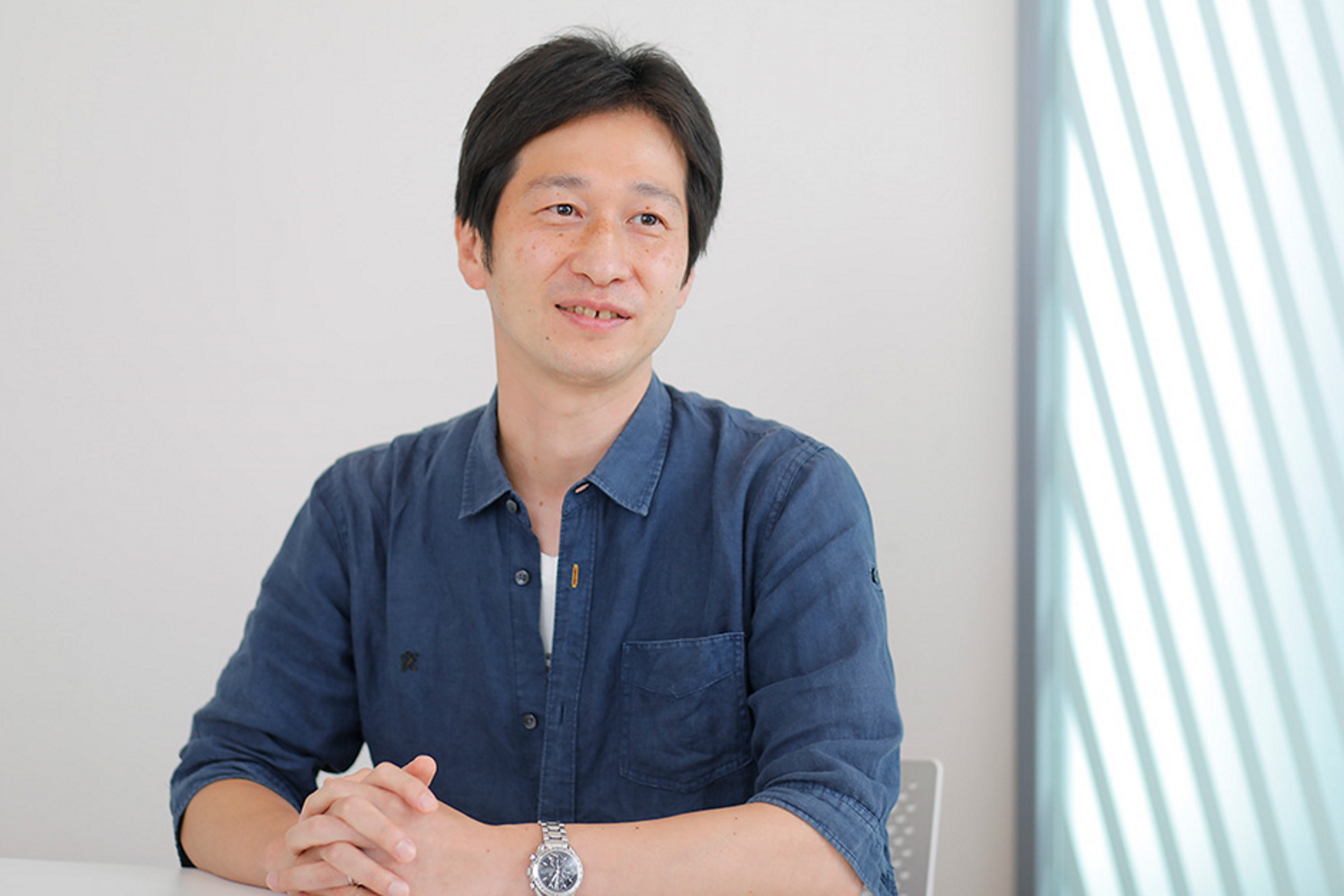

入社後3年間は、ヤフオク!の機能開発にエンジニアとして取り組んでいました。2018年頃からフリマサービスの検討が始まり、初期段階からサービス設計や機能開発に関わっています。
PayPayフリマでは、ヤフオク!のサービス基盤を共有して使っている部分と、PayPayフリマならではの新たな機能を実装した部分がありますが、
現在は、新たに実装した機能全体を管掌する開発部長を務めています。

私は入社後ヤフオク!のストア向けの営業を経験し、その後は企画やマーケティングの部署に異動して、集客施策や顧客育成などの業務を担当してきました。
PayPayフリマの担当になってからは、エンジニアやデザイナーと協力して機能開発や改善を進めるプロダクトの企画をしています。
2022年からはエンジニアが主務になりました。エンジニアのスキルはすべて入社後にヤフーで身につけたものばかりです。

二人ともPayPayフリマの立ち上げから関わっているので、尋常ではないフリマ愛にあふれています(笑)。入社2〜3年目のメンバーが新規事業の企画開発に関わり、
主導的な役割を果たしているのも、ヤフーの風土ならではです。特にPayPayフリマ開発部は、若いメンバーが大きな裁量を持ってサービスを作っています。

若手に任せる裁量。身近なサービスだからこその思い入れ
──ヤフオク!統括本部は、社内のエンゲージメントサーベイ(商品やサービスに対する熱意や愛着心を定量的に把握する調査)で高い評価を得ています。特に「上司との関係性」や「裁量の大きさ」ではトップクラスですね。
エンジニアが受け身で仕事をするのではなく、サービスの企画段階から関わり、企画やデザイナーが連携して仕事を進める点を一番大切にしています。
若いメンバーでも意思の強ささえあれば、どんどん抜擢して裁量権を与えています。そうしたことが評価にもつながっているのだと思います。

エンジニア一人ひとりに任される役割や裁量が大きい。「やりたい」と手を挙げた人を組織が後押ししてくれるので、やりやすいですね。

ヤフオク!やPayPayフリマはコンシューマー向けのサービスなので、メンバーも一人のユーザーとして楽しんでいます。
だからこそ、ユーザーの体験を自分たちの力で、より向上しようと前向きになれますね。友人や家族など、身近な人たちがPayPayフリマを楽しく手軽に使ってくれている。
だからこそ、もっとサービスをよくしたいという気持ちになります。

モダンな開発環境を目指し、使用言語にKotlinを提案
──PayPayフリマを支える技術について話を進めていきたいと思います。高負荷のトランザクションを処理する技術やサーバー分割の技術などは、ヤフオク!から技術資産として継承していると聞きました。その蓄積のうえに、PayPayフリマならではの新しい技術も導入しているそうですが、具体的にはどんなことでしょうか。
PayPayフリマの事業を立ち上げる際に、選定技術としてサーバーサイドKotlinを採用しています。
ヤフーのサービスはJavaを標準言語として使うことが多いのですが、KotlinはJavaとの親和性が高く、短い開発期間でも効率的にバグの少ないコードを書けること、開発メンバーにAndroidエンジニアが多かったことから品質を担保しつつ、最短で価値を提供できるのではと考えて提案しました。

それらの提案は、他の技術も広くサーベイしたうえでKotlinのメリット・デメリットを正しく検証しており、十分に納得できるものでした。導入しやすいタイミングだったこともありますが、提案内容が優れていたので導入を任せました。

ほかにもマイクロサービスアーキテクチャでコード自体をテンプレート化することで、複数コンポーネントを高速に同時開発することも提案しました。共通機能はヤフオク!の資産を活用することで開発コストを抑え、PayPayフリマ特有の部分についてはバックエンド・フロントエンドともに新規開発することが基本的な戦略でした。
すべての機能をスクラッチ開発することは非常にコストがかかることですが、もともとヤフオク!ではマイクロサービスアーキテクチャを採用しており、全社もさまざまなSaaSを提供しているため、必要な部分のみを開発すればよく、スピード感を出せたこともよかったと思っています。
設計のスタートが2019年の4月で、サービスリリース予定が10月。初期メンバーが20人だけで、開発期間も半年間だけでしたので、このスピード感はとても大切でした。
また、マイクロサービス化されているシステムは状況によって一部機能を遮断し切り離すこともできるため、可用性を担保するという点でもメリットがありました。


一方で、ドキュメントを残しておく余裕がなく、ソフトウェアアーキテクチャは人によって癖が出る部分も大きいという課題もありました。
属人性を排除しつつ、スピードも高める必要があったので、チーム内にペアプログラミングを導入することにしました。ペアプログラミングの組み合わせをシャッフルさせながら開発することで、コード品質の偏りを可能な限り軽減できたと思っています。
アプリからデータを取得する際はすべてBFF(Backend for Frontend)のAPIを利用しています。アプリに持つロジックを極力排除し、BFFに実装することでアプリをシンプルな状態に保ち、コード自体はサーバー側でコントロールできる状態にします。
また、サーバー間の通信にはGraphQLを採用しました。さまざまなユースケースに対して専用のAPIを作成する必要がないため、変化に強いシステムができたと考えています。
ヤフオク!との連携、Androidアプリの同時開発も
──ヤフオク!との機能連携はどのような取り組みを行ったのでしょうか。
ヤフオク!の検索技術を活用して、双方のデータから検索できる機能を開発したのですが、データのフォーマットがそれぞれ違うため、どうやって吸収するか。そこが一番苦労したところであり、仕様を同じように見せるマッピング技術も工夫しました。

マーケティング担当としては、クーポンの発行やキャンペーンなどの仕掛けについての要望を出していたと思います。Yahoo!検索からPayPayフリマにユーザーを送客するなど、グループのアセットを活用した集客施策も重要なポイントなのではという議論をしたことを覚えています。

リリース時にPayPayフリマのプロモーションをどのように行い、ユーザー認知を拡大していくか、検索チームやマーケティングチームと話し合いをしましたね。

実は、当初PayPayフリマはiOSアプリだけでスタートする予定でしたが、マーケティングの都合などから急遽、Androidアプリも近い時期にリリースすることになりました。これも結構大変でしたね。

リリースまで3カ月足らず。この限られた時間で何をやるかを検討しながら、一時はAndroidアプリ開発に人的リソースを寄せ、スタート時はいくつかの機能を削ることで、なんとかiOS、Androidアプリともにリリースすることができました。Android開発経験のあるメンバーがバックエンド開発を支えてくれて、サービス仕様の細かいことも把握できていたからこそ実現できたと思っています。

出品者とつながる機能を実装。PayPayサービス全体のシナジーを生かす
──サービス開始後はどんな機能追加が行われましたか。
私がエンジニアとして主担当で実装したのは、投稿機能です。具体的にはPayPayフリマ内で、ユーザーが欲しい物や出品している物について情報発信できたり、
ユーザー同士で交流できたりする機能です。例えば、農家の出品者が「うちのみかんがもうすぐ収穫できるので出品します」といった投稿をすると、それに“いいね”やコメントをつけることができるのです。
リアルな市場で売り手と買い手が仲よくなる雰囲気。そんなコミュニケーション機能をアプリのなかにも持ち込めないかと思っています。今後もフリマアプリとしてのスタンダード機能は完備しながら、新たなアイデアを盛り込んでいきたいです。

ほかにウェブブラウザで商品が閲覧できるようにしたり、PayPayアプリのなかに導線を作ってフリマの商品が見えるようにしたりなど、よりユーザーの間口を広くして、PayPayサービス全体のシナジー効果を高める取り組みも進めています。

出品数や取引件数が増えていくと、不正出品を検知する機能も強化する必要があります。その仕組みは、ヤフオク!と同じ機能で開発しています。
長年にわたってヤフオク!で積み重ねてきた知見や判断基準があることは強みの一つですね。この領域にはAI技術もどんどん活用していきたいと考えています。

「PayPayフリマの先にあるもの」を突き詰めたい
──最後に、今後の抱負とPayPayフリマ事業にジョインしてくれるエンジニアに期待することを聞かせてください。
今後もYahoo!ショッピングやPayPayモール、ZOZOTOWNなど、ショッピングサービスとの連携は強めていきたいですね。いずれはLINEなど、グループ内のアセットを活用したPayPayフリマならではの機能を作っていきたいと思います。

PayPayフリマは、ヤフーのなかでもモダンな技術を採用したサービスだと自負しています。レガシーなコードを手直していくことも、エンジニアとしては面白いのですが、技術的な負債とうまく付き合いながら、新しいシステムを開発・運用していくことが楽しいですね。
もう一つは、PayPayフリマの先にあるフリマサービスを見てみたいです。投稿機能も一つのアプローチですが、例えばC to Cの売買を通して生まれる新しいコミュニティーの価値みたいなもの。カメラの中古レンズの取引一つとっても、思い入れのある商品はこの人にぜひ売りたい、この人からぜひ買いたいということがあるのではないかと思います。
現状のフリマという売買行動だけでなく、売買そのものやその外側にある本質的な価値。それがどんなものなのか、その価値が果たしてユーザーに受け入れてもらえるものなのかどうかは、検証が必要ですが、そうした体験の見直しや向上をもっと突き詰めていきたいです。

自社サービスですから、入り口から出口まで全部、自分たちで考えて作ることができます。エンジニア、企画、デザイナーなど、職種に関係なく、一緒に開発できるチームワークも楽しいです。
リリース後の反響を分析して、悩んで、そしてまた新しい企画を出していく。そのサイクルがPayPayフリマでは常時ものすごいスピードで回っています。
その渦のなかに飛び込んでくれるエンジニアの方をお待ちしています。

「サービスをよりよくしたい」というマインドを持っている人にぜひ参加してほしいです。また、大量のトラフィックをシステムとして処理していく技術も、
純粋に面白い。直近ではSRE(Site Reliability Engineering)という組織を立ち上げましたが、大規模なシステムをどう構成していくのか、どう運用していくのかという面白さもあります。

フリマサービスには社会のさまざまなことを変えていく可能性があります。モノを廃棄するのでなく、リユースするエコシステムを作ることは、これからの社会に不可欠です。
単にシステムを改善するだけではなく、ヤフーグループ内のアセットや他社サービスとの連携を深めながら、その可能性を高めていける多様なバックグラウンドを持つエンジニアに、仲間に加わってほしいと思います。