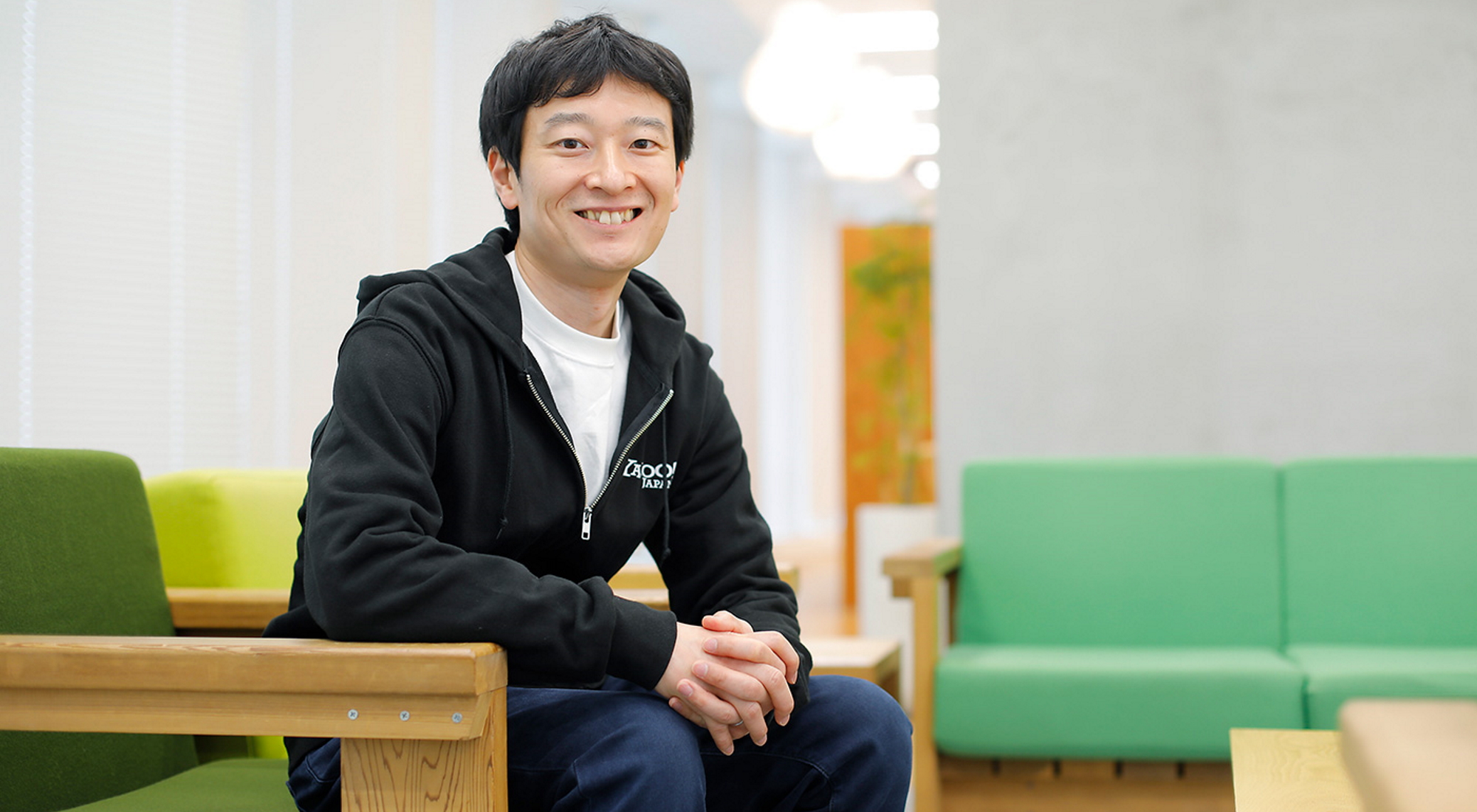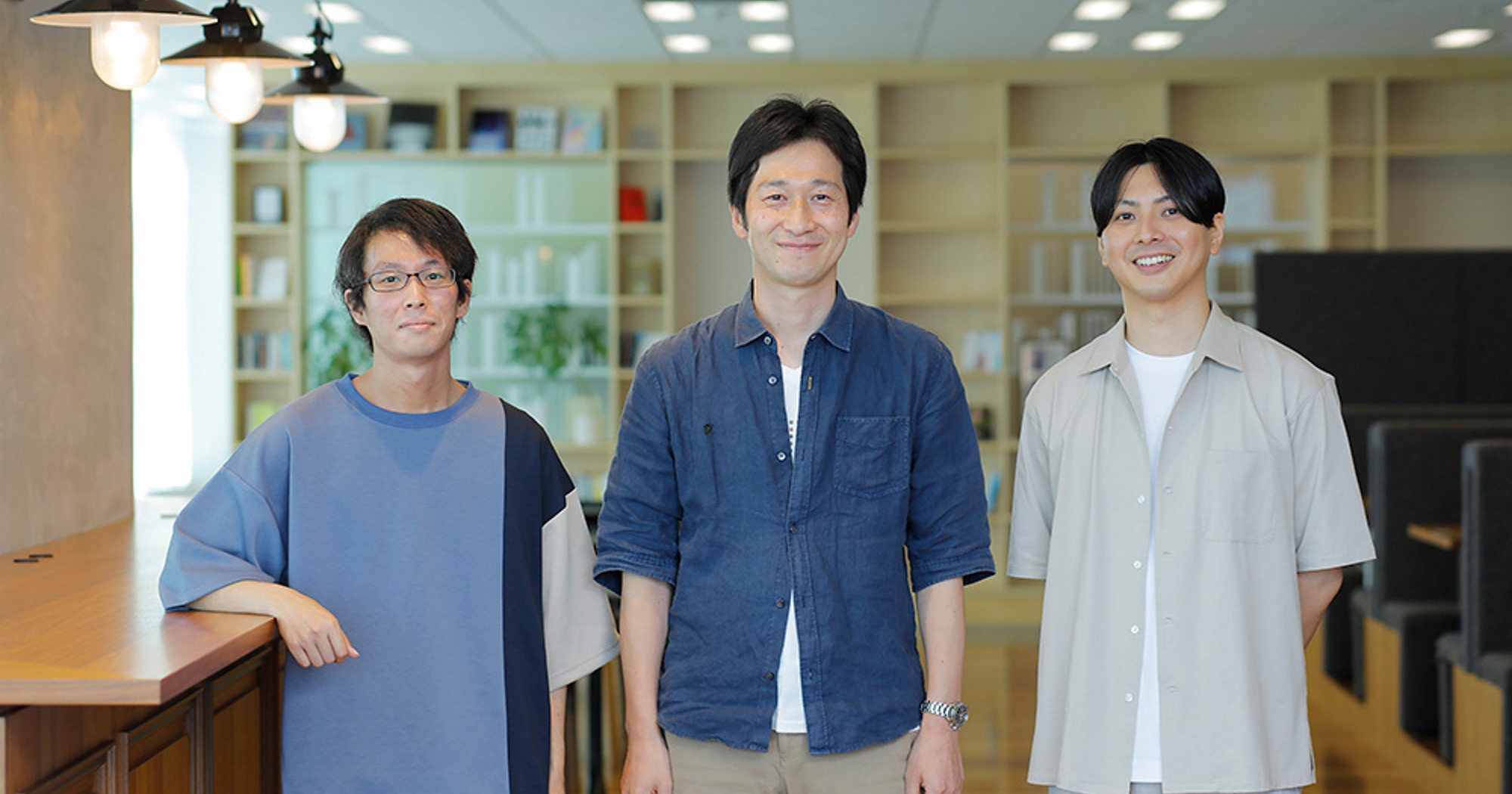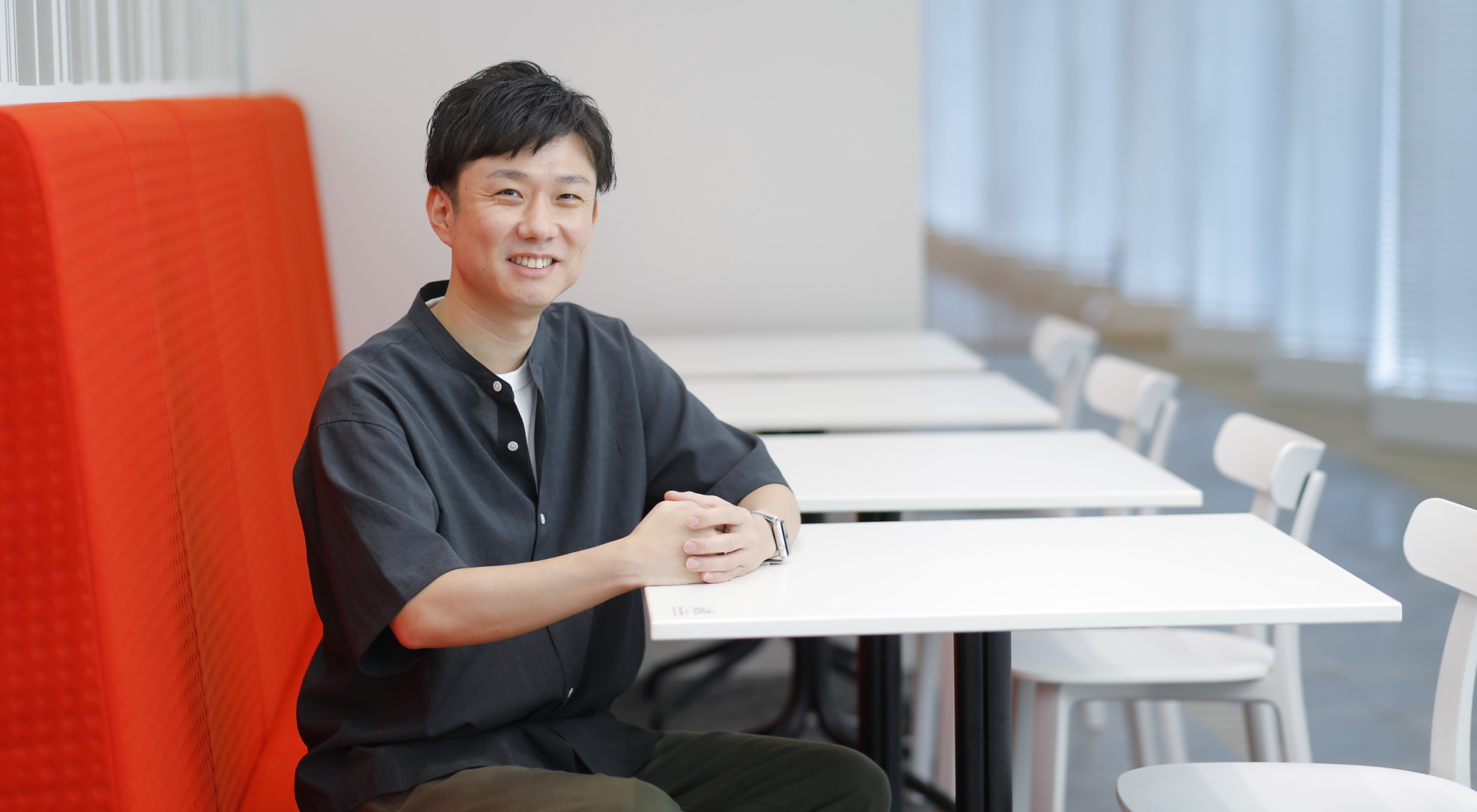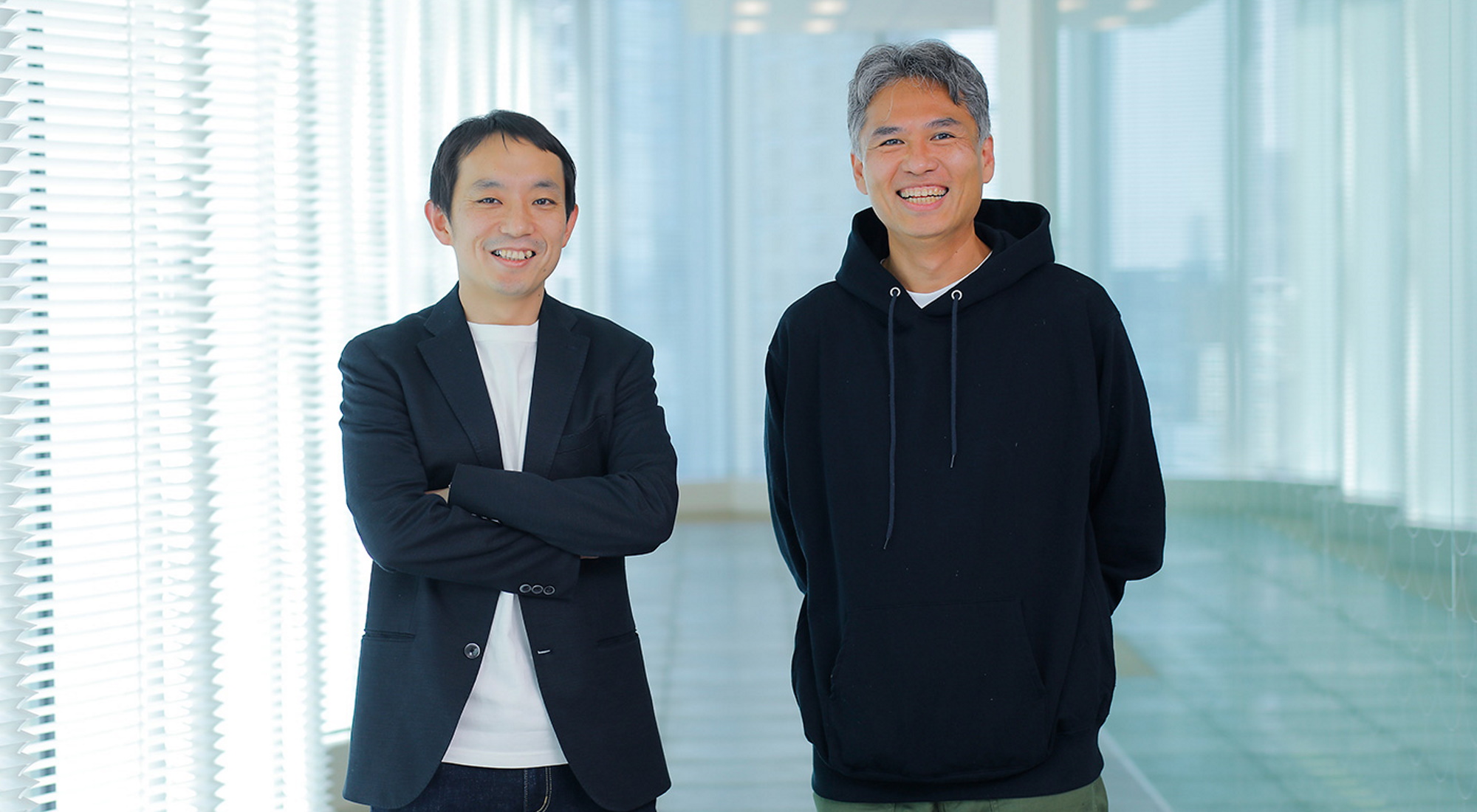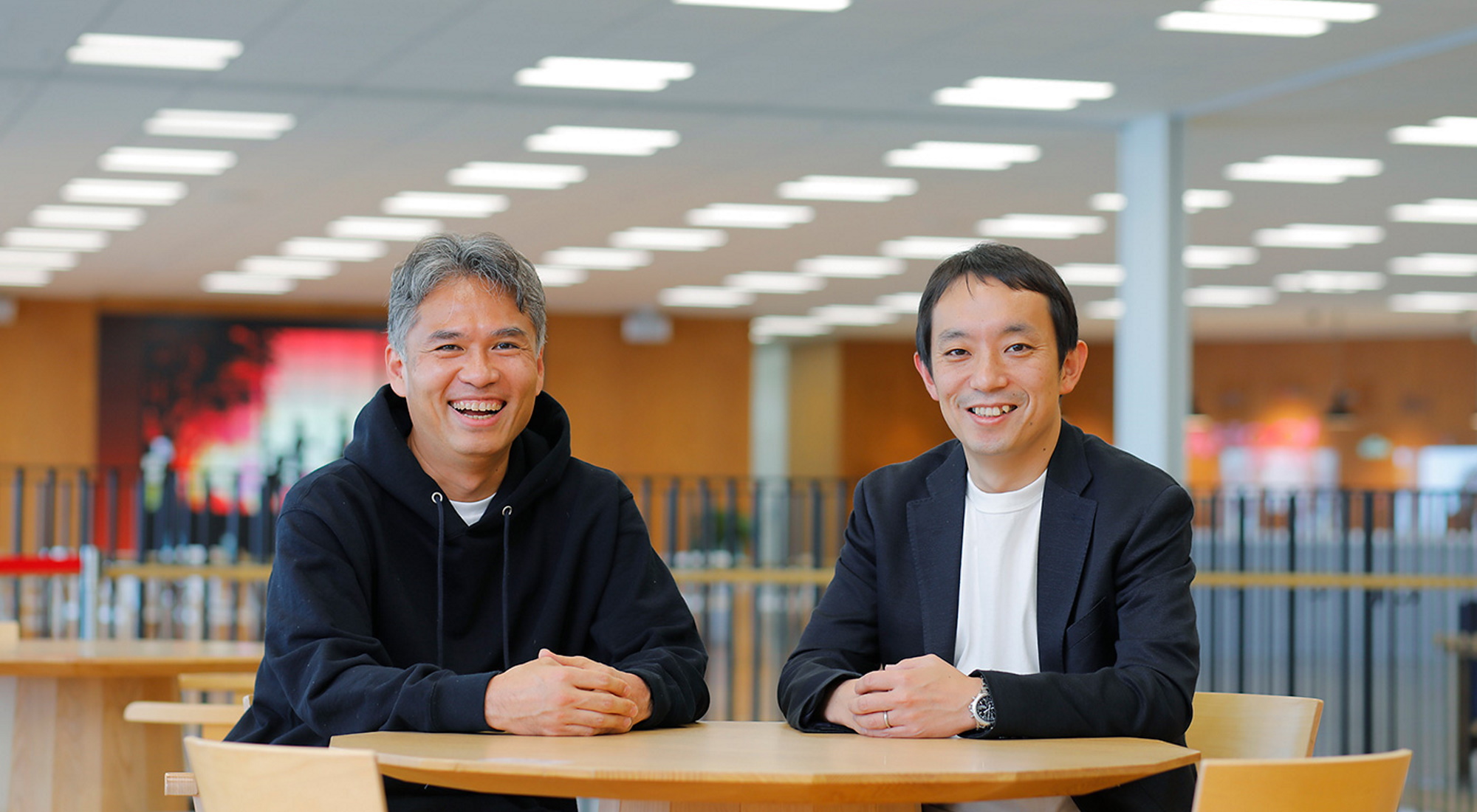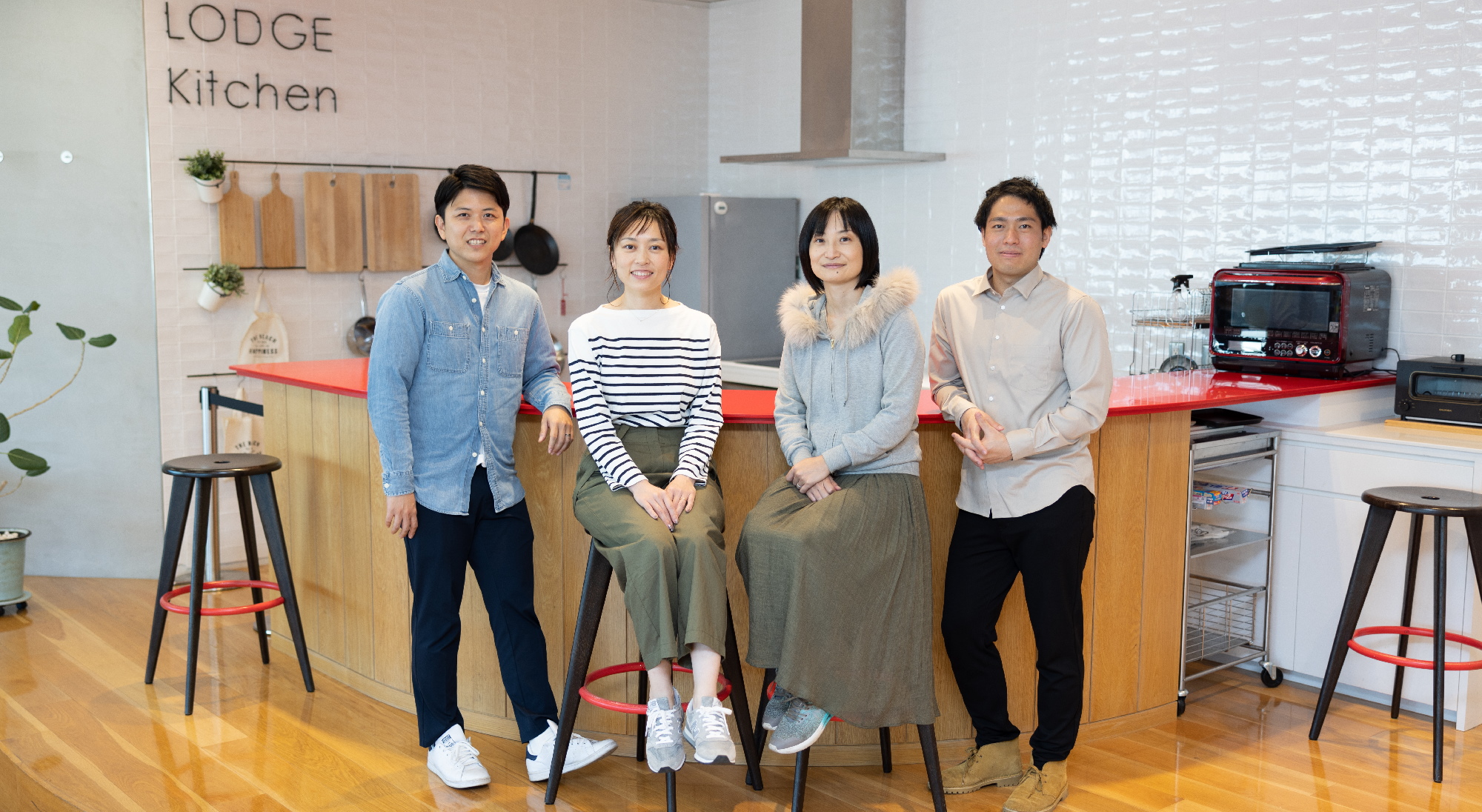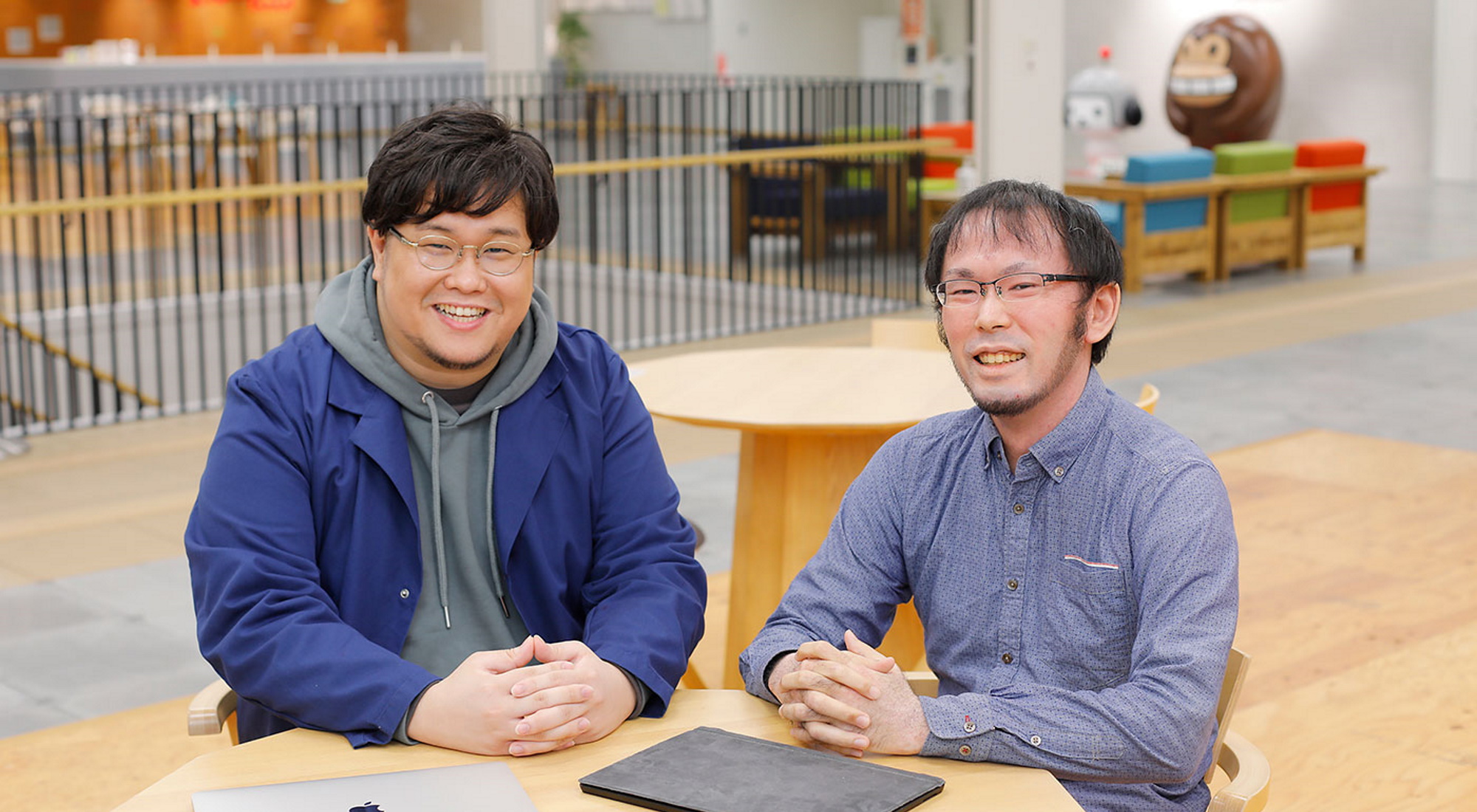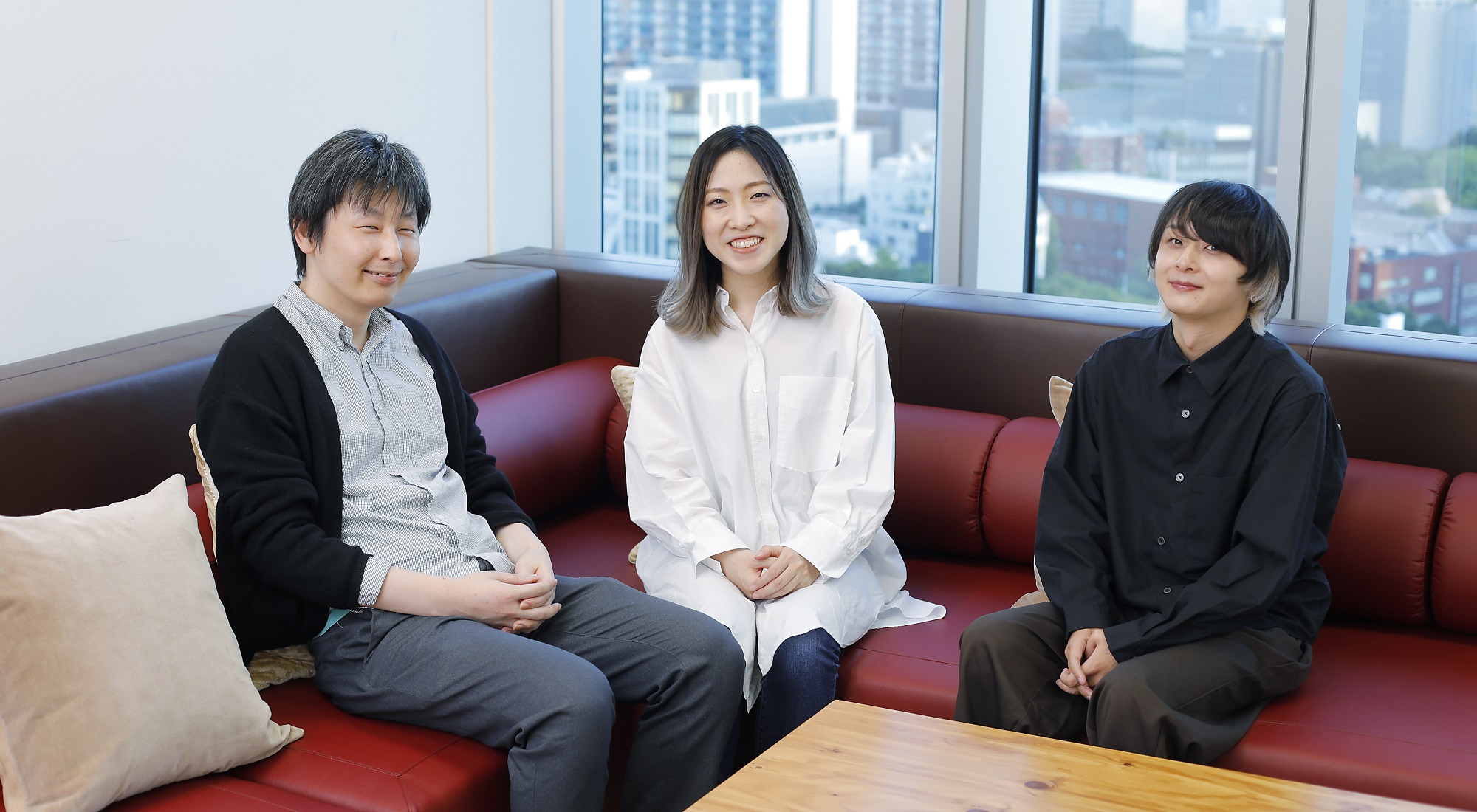情報技術のチカラで、日本をもっと便利に。──ヤフーが掲げるミッションです。その実現のために求めるのは、どのような人財なのか。 企業のミッション・ビジョン・ゴールは、実際の採用面接にどのように反映しているのか。人財採用戦略の根幹となる“ヤフーの採用哲学”をテーマに、 人事部の大森靖司と干場未来子が語ります。役職、職歴、職種に関係なく、これからヤフーで働いてみたいと考えている、すべての皆さんの参考にしていただけたら嬉しいです。
プロフィール
- 大森 靖司
PD統括本部 コーポレートPD本部長 - ポテンシャル採用からキャリア採用までヤフーの全採用における母集団形成をリーダーとして主導。その後クリエイター向けの人事施策の企画運用や部門人事、ギグパートナー制度立上げを経て、2022年4月より現職。人事労務や採用業務を管掌。
- 聞き手:干場 未来子
PD統括本部 コーポレートPD本部 - マーケティングソリューション事業で営業、エデュケーション、プロダクトマーケティング、マーケティングチームなどを経て、2016年に人事へ異動し、採用ブランディングを担当。
「仲間を集める」から「仲間をつくる」へ
本章のポイント
✓時間や場所の既成概念を取っ払って、採用の可能性を最大化

さらなるヤフーの事業成長を考えるうえで、人財採用は最優先のテーマです。ヤフーは何のために人財を採用し、育成するのか。 そこにはどのような考え方が貫かれているのか。今回はあらためて、そんな根源的な話を大森さんとできたらと思います。

「何のために採用活動をしているんだっけ?」については、以前からよく議論してきましたね。会社のミッションは「UPDATE JAPAN」「情報技術のチカラで、日本をもっと便利に。」 だとすれば、ヤフーの採用のミッション、ビジョン、ゴールは何だということで、現時点では次のように言語化しています。
採用のミッションは、「未来をつくる『仲間』をつくる」こと。
採用のビジョンは、「『仲間』をテコに、未来創造を加速する」こと。
最終的に目指すゴールは、ヤフーを日本で「働きたい会社No.1」にすること。
なかでも一番大切にしていることは「仲間をつくる」というミッションです。採用はよく「仲間集め」だといわれますよね。これまでのヤフーもそうでした。どう仲間を集めてくるか、ということで試行錯誤してきた。 例えば、どのような媒体に募集広告を出すのか、人材紹介会社をどのように活用するのか、どのダイレクトリクルーティングツールをどんなふうに使うのか、などです。いわば、仲間を集める採用手法を1つ1つ地道に磨き込んできたんですね。
他方で、実は、採用の手法論はここ5-10年単位では大きく変化していないと考えています。 その変化していないものに対して、ヤフーはもちろん各社も採用の優先度を上げて取り組んでいるわけで、成功事例はすぐに広がりますし、模倣される。なかなか差別化が難しくなっているんじゃないか──。
そこで考えたことが、もはや仲間を集めるための採用手法で勝負する時代ではない、ということですね。

「仲間を集めるための採用手法論だけで勝負する時代ではない」とは、どういうことでしょうか。

仲間を集めようとすると、どうしてもHowにばかり考えが及びがちです。もちろん、Howは大切ですよ。 採用手法のレベルをどんどん上げて、優秀な方々に数多く応募いただくこと、目の前の応募者と向き合い、ヤフーの魅力をしっかり伝えていくこと。それらは基礎力として大事です。ただ、それは各社もやっているので、差別化が難しいのではと個人的には思っています。

だとすれば、どう差別化を図るんですか?


仲間を「集める」こと以上に大切なのは、仲間を「つくる」ことですね。 ひょっとしたら僕たち自身も忘れがちかもしれませんが、私たちは採用担当者である前に人事担当者です。社員が働く環境、組織風土、それを担保するためのルールづくりや制度づくりを旗振りできる主体なんですよ。
これまでヤフーが仲間に加わってほしくても仲間にすることができなかった層が少なからずいらっしゃいます。理由は、時間や場所の制約であったり、ご家庭やご自身のプライベート含めた諸般の事情だったり、さまざまでしょう。そこに採用手法をピカピカに磨いて臨んでも、そもそも仲間にできないジレンマがあった。
でも、「仲間をつくる」ためにどうするかという発想で臨めば、全く違う景色が見えてきます。

例えば、どういう景色ですか?

いくつかの事例をもとにお話しましょう。
例えば、新規学卒一括採用の廃止を行いました。2016年のことです。これに伴い、ポテンシャル採用・キャリア採用の2軸に体系化し、通年採用に移行しました。 結果、例えば既卒の方やポスドク、海外留学経験者など、若手の方にご応募いただきやすい土壌ができたと考えています。
新型コロナをきっかけに生まれた「仲間をつくる」ための取り組みもいくつもあります。
代表的なものを時系列でお話しすると、まずは、ポテンシャル採用のインターンシップのフルオンライン化ですね。 ヤフーの働く共通のワークスペースはオフィスでも自宅でもなく「オンライン」ですが、それを学生にも名実ともに“就業体験”していただく形です。よく驚かれますが、PCも郵送で受け取れるので会社に取りに行く必要はありません(笑)。
ヤフーを副業先とする人財を受け入れる、ギグパートナー制度もつくりました。これまで時間や場所の制約から一緒に働くことが難しかった個人の方と、ヤフーという舞台でオープンイノベーションを図る枠組みを整えることができました。
最近では、新しい働き方をUPDATEし続け、場所にとらわれずに働くことができる「どこでもオフィス」という制度を拡充することによって、日本全国津々浦々の方々に応募いただきやすい環境をつくりました。実際に、2022年度6月にはキャリア採用の応募者の一都三県以外比率が応募総数の4割近くとなりました。

確かに、採用手法というよりは、制度やルールを交えた施策が多いですね。

採用手法を駆使した「仲間を集める」だけではない、人事だから扱える制度やルールなどをテコにした「仲間をつくる」こと。これがヤフーの採用のミッションです。ある種、新規事業開発のように、仲間のつくり方をどんどん発明する感覚に近いですね。企業の人事機能を広い視点から捉えたら、まだまだ新しい採用のカタチは発明できるのではないか、と考えています。 そういう新しい取り組みに果敢に挑戦する姿勢は社外の皆さんにも伝わると思っていて、それがさらに「仲間をつくる」ことに寄与するのではと考えています。


「仲間をつくる」というミッションは、ヤフー全体のミッションとリンクしていなければなりませんね。

そうですね。
あらためてヤフーのミッションは「UPDATE JAPAN」「情報技術のチカラで、日本をもっと便利に。」です。そのためには、ヤフーの持続的な成長が必要で、それには良いサービスを生み続ける仕組みが重要だと考えています。
良いサービスを生み続け、良い会社を実現するためには、社員一人ひとりが能力を最大限に発揮することが不可欠です。そのために、社員が成長できる仕組みとして人事制度が存在します。
この「社員一人ひとりの能力を最大限に発揮」という点が、実は「仲間をつくる」にも直結するんですよ。

お、これは初めて聞いた話かもしれない(笑)。

言うまでもなく社員の属性はさまざまです。年齢や性別というデモグラフィーの点はもちろんのこと、それぞれがパフォーマンスを最大化できる服装だって違う。 ましてや、机の高さ、デバイスの種類、キーボードの型だって違うじゃないですか(笑)。その延長線上に、働く時間や物理的な場所の違いもあるわけです。
例えば、場所を例にとれば、一番パフォーマンス発揮できる場所なんて本当にバラバラで驚きます。 昨日の私のチームを見渡しても、オフィスに出社しているメンバー、自宅で働いているメンバー、サテライトオフィスで働いているメンバー、はたまた実家に一時帰省中のメンバーまで、多様なんですよね。
ヤフーでは会社と社員はイコールパートナーであると考えています。労使関係でも、依存関係でもなく、お互いが共存関係です。 だからこそ、会社は、それぞれの社員がベストな働き方を選べるように選択肢を提供し、社員にはパフォーマンスにしっかりコミットして各制度を自由に選んでもらっています。
そうやって、会社として考え生み出した「選択肢」がまさに「仲間をつくる」武器になるんですよね。

なるほど、それぞれの社員にとってベストな働き方を追求することが、「仲間をつくる」にもつながっているんですね。

はい、社員一人ひとりが自分らしくヤフーらしく働くための選択肢を拡充しくことが、同時に「仲間をつくる」ための選択肢にもつながるんですよね。
こういったことを積み重ねて、「日本一先進的な働き方」や「日本一成長できる環境」を目指したいですし、 そうした働き方や環境を追求することが、多様な経験と才能を持った人に訴求できる点だと信じて、取り組んでいきたいですね。

ヤフーはそもそも日本のインターネット草創期から、仲間をつくってきましたもんね。

そうですね。
ヤフーはまだインターネットが何なのかほとんど認知されていなかった時期から事業をスタートさせ、仲間づくりを進めてきた会社。 「業界」や「業界経験者」という言葉がないころからまさに試行錯誤しながら、仲間をつくってきました。そういう意味では、「仲間をつくる」という思想は、以前からヤフーの採用の軸であり続けたのかもしれませんね。
企業の社会貢献と、人財採用はどう関係しているか
本章のポイント
✓社会課題解決における先進的な取り組みを、今後はより積極的に紹介してゆく

最近、ヤフーの人財募集にエントリーしてくれる学生から「ヤフーの仕事を通して、自分は社会のどういう部分に貢献できるのか」という質問をされることが増えてきました。

そういえば、キャリア採用入社者向けアンケートの一つ、「なぜヤフーに入社を決めたのですか?」でも、ヤフーのミッション・ビジョン・ステートメントに共感したと答える人が実は一番多いんですね。
どんなミッションを掲げているか、社会に対してどんな価値発揮や課題解決を図っているかに加えて、企業の活動が社会貢献やSDGsのようなテーマとどう関連するのか、 そのなかで自分自身はどんな貢献ができるのか。そのあたりに対する若い世代の注目度の高さは感じます。

ヤフーの社会貢献活動については、もっと広く知らせたいなと思っています。


HPにも「Yahoo! JAPANが挑戦する 社会課題解決の取り組み」のページがあって、具体的な大きなテーマとして、 情報技術社会の発展、災害・社会課題への支援、誰もが活躍できる社会の実現、持続可能な社会への挑戦など掲げていますが、しっかり伝えられているかというと、まだまだ。伸びしろだらけです。
例えば、先程話にあがったSDGsの話でいえば、2018年度からコーポレート部門の幹部向けに、サスティナビリティ研修を実施しています。 カーボンニュートラルを推進するという宣言も企業として行っていますよね。
こうした取り組みや実績が評価されて、親会社であるZホールディングスは、ESG(環境・社会・ガバナンス)の世界的な評価機関であるMSCIから昨年、最上位のAAAの評価をいただいています。

ヤフーはダイバーシティ&インクルージョン推進や障がい者雇用、LGBTQへの理解・啓蒙にも注力しています。

「多様性は可能性」といったキーワードも、社内の会話で頻出しますね。経験・価値観・ライフステージ・属性の違いにかかわらず、多様な社員一人ひとりを尊重し、 活躍できる土台をつくり、多様なサービスや事業のイノベーション創出に活かすことは、ヤフーにとっては日常的に取り組んでいるテーマです。
例えば、障がい者雇用では法定採用率を満たすだけでなく、障がいある社員がそれぞれの特性に応じて取り組みやすい仕事を創出してきました。 また、弊社所属のパラアスリートへの支援にも注力しており、うち一人の選手は東京2020で銅メダルを二つ獲得しました。
LGBTQといったセクシュアル・マイノリティへ向けた施策についても、さまざまな取り組みを行っています。 育児休暇や結婚の祝い金など、一般的な婚姻カップルに提供する福利厚生を同性パートナーや事実婚カップルにも適用することも、2017年度からやっていますね。
そうした活動もあり、2019年に任意団体「work with Pride」の「PRIDE指標」でゴールド認定をいただきました。

個々の施策は社外からも高く評価されているものの、ヤフーの人財採用の強みとなる施策や事例をまだまだ紹介しきれていないですよね。

採用の責任者としては、ヤフーが取り組んでいる先進的な働き方や取り組みを、サービスや事業と同じように構造的・立体的にして、積極的に紹介していきたいですね。
「あなたの代表作は何ですか」──三つの求める人財像
本章のポイント
✓ 見ているポイントは「再現性があるかどうか」

ヤフーに応募していただく皆さんの関心としては、やはり「面接でどんなことを聞かれるのだろう」「採用の基準は何だろう」 「どんな人材像を求めているのだろう」ということがあると思います。ポテンシャル採用・キャリア採用を問わず、これらは気になる人が多いのではないでしょうか。

まず求める人財像については、大きく三つです。
一つは「変化を楽しめる、または自ら変化をつくり出せる人」。インターネット業界はまだ歴史が浅く、過去には答えがないし、これからどう変化するかもわからない。 だからこそ、変化を恐れない、楽しむスタンスが大事です。もちろん、変化を自らつくり出せればさらに良いですよね。
二つ目は「学ぶ力のある人」です。変化をもたらすためには、日々の学習が欠かせません。「学び続けられる人」でありながら、ときとして古い学びを捨てる(「アンラーン(Unlearn)」)。 それらを通じて自己研鑽を続けられる人ですね。
三つ目は、「決めたことをやりきる意思および力がある人」です。「変化するって面白そう」でいうだけでは評論家と同じです。その変化を自分ごととして捉えて行動することが大切ですね。 いざ何かをやろうとすると、「これが実はこうでして…」「もしこうなったら、こんな懸念がありまして…」では何も進んでいかない(笑)。それを実現するためにどうするか。そこをしっかり考え抜いて実行するスタンスも大切です。


「変化を楽しめる人、変化をつくり出せる人」なのかどうかを見極めるために、面接ではどんなことを聞いていますか。

これまでの経験や過去に取り組んできたことを聞きながら、それが単なる偶発的なものでなく、再現性があるのかどうかを見ています。 学生であれば学業やアルバイトやサークル活動などで一番頑張ったこと、社会人であれば非常に困難なプロジェクトをやり抜いたこと。 私はこれを「仕事のなかでの代表作」という言い方をよくするんですが、それを面接では必ずお話しいただくようにしています。
「なるほど、この人はこういう場面でこういうふうに考え、実行し、失敗し、工夫し、成功してきたのか」──話を詳しく聞くうちに、面接官もそのストーリーを疑似体験できるようになります。 応募者を取り巻いている環境や要素を踏まえたうえで、「この人だったらその成功経験がヤフーでも再現できるのでは」。そんな視点で、面接の場でインタビューさせていただくことが多いですね。

学び続けることができるかどうかも、その経験を語っていただくことで、私たちは判断していますね。

過去に何か重要な経験をされてきた方に、「もう一度、時間を巻き戻すことができたら、何か変えることはありますか」「もっといいアウトプットにするためには、どうすれば良かったですか」といった質問をすることもありますね。
それに対して、「過去の経験を棚卸しして振り返ってみると、こうしたほうが良かった」と、自分の学びを自分の言葉で言語化できている人の話は、やはり説得力があります。


三つ目の「やりきる意志や力」はどこで判断していますか。ヤフーでは、おそらくほとんどの人がこれまで経験したことのない課題に直面するでしょう。それを前に「できない」理由を考えるのではなく、「できる」と信じて行動を起こせるような人とぜひ出会いたいですね。

「一番困難だったけどもやり抜いた経験」って、やっぱり相当苦しいし辛い局面がついて回るものだと思うんですよね。その、客観的には逃げたい・泣きたいようなシーンにおいて、どう自分なりに意義を見つけて取り組んだのか。やり抜くためにどう周囲に働きかけたのか。そのあたりを伺っています。

ヤフーの社員は、周囲を上手く巻き込みながら仕事をする人が多いように感じます。巻き込むためには、自分の信念をしっかり持つことや、周囲とのコミュニケーションスキルも必要となります。

変化を楽しんでいる人、学び続ける人、そしてやりきる意志や力がある人がいたとして。その人がやりたいことがあって、根拠も合理的であるならば、自然と予算と人財が集まるものです。
そうやって、これまで誰もやっていないことに挑戦して、世の中を便利にすることに心血を注いできた。それはヤフーのミッション「UPDATE JAPAN」にも通ずるものだと思います。

企業としてのミッション・ビジョンと求める人財像の紐づきが伺えるお話ですね。
毎日の採用担当朝会で、リクルーターの「選ぶ力」を高める
本章のポイント
✓ 組織単位ではなく全社的な視点を持つことで応募者の可能性を模索している

ここまでヤフーが求める人財像を語ってきましたが、企業の採用は応募者に求めるものだけでなく、応募者の側から企業に求めるものとの接点でもあります。その意味では、ヤフーの採用担当側にも「選び抜く力」が問われている。そのことを肝に銘じる日々です。

例えば、採用チームでは毎日採用担当者同士で朝会を行っていますよね。前日の面接の結果などを担当者全員で共有し、リクルーター全員で目線合わせをするための会議ですが、これを毎日やっていることを話したら、他社の方に驚かれたことがあります。

参加者も多いですし、毎日30分繰り返していますからね。採用に注力する時期は職種ごとに二手に分かれて実施することもあります。他の企業様から見ると「前日の面接結果だけで、どれだけ話してるの?」と思われるのかもしれません(笑)。
例えば、仮にAさんという応募者がいたとします。で、何らかの採否判断がなされたとします。その場合、理由などが言語化されているので、そこを採用担当一同で見て議論をするわけです。
なぜ合格or不合格になったのか。部門と人事、それぞれの判断はどうだったのか。Aさんが最初に希望していたBという部署ではフィットしていないと判断されたとしても、情報交換するうちに「Aさんの経験はCという部署で活かせるかもしれない」と、もう一つの選択を示すような話題が出ることもよくあります。
実際にそうした経緯を経て、別部署での採用が実現することもあって。募集要項を特定の部署やサービスだけでなく全社的に見ることで、採用の可能性を見落とさない、ということを心掛けています。
ごくごくありふれた話かもしれませんが、社外の採用パートナーとお話をすると、ヤフーの企業規模でありながら、個々のサービスや組織単位だけでなく全社目線で採用を検討するスタイルはかなり珍しいようです。 こんなに広範な組織や募集全体を、横串を通しながら、一人ひとりの可能性を探るというのは、実はヤフーの採用の特長かもしれません。なお、リクルーターが全社の組織や募集をキャッチアップするのは非常に大変です(笑)。


採用活動全体の相談や報告を経営陣やCTOとする機会も多いですよね。人財採用の重要性が、役員や役職者たちと常に共有されていることも、当たり前のことかもしれませんが、ヤフーでは特長かもしれません。

例えば、当社の採用活動の主たるターゲットの一つにエンジニアがありますが、求めるエンジニア像に当てはまる人がどのくらいいるのかという市場動向も、CTOやVPoEに共有しています。
今年4月には新しいCEOやCTOも着任しました。彼らが発するメッセージの一つひとつが、採用にも直結していることは十分に理解してもらっていると感じています。

そうですね。ヤフーのミッション・ビジョン・ゴールと具体的な採用戦略や人財像との関係性、これが応募者の皆さんにもきちんと伝わって、さらにヤフーへの興味・関心を持っていただけると嬉しいですね。