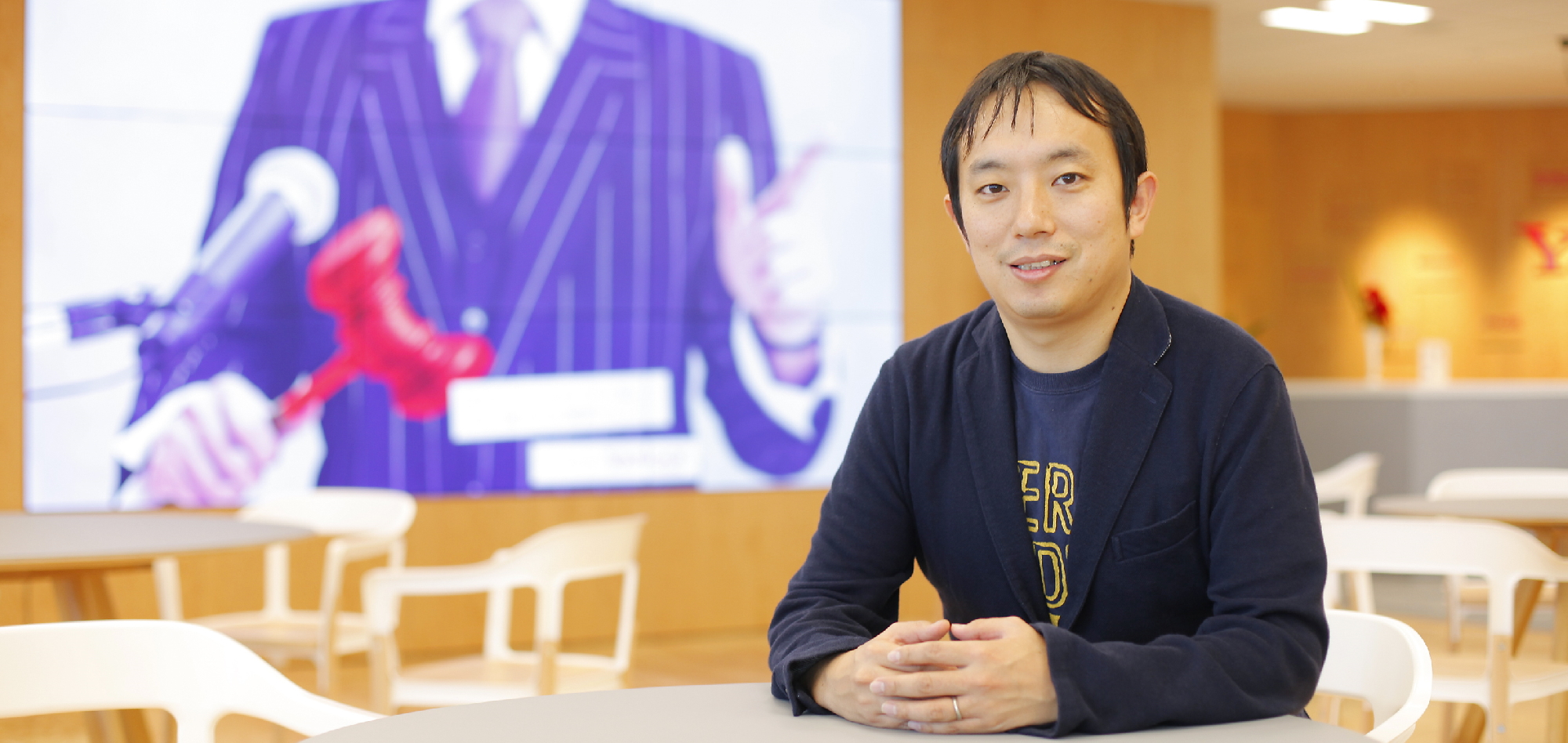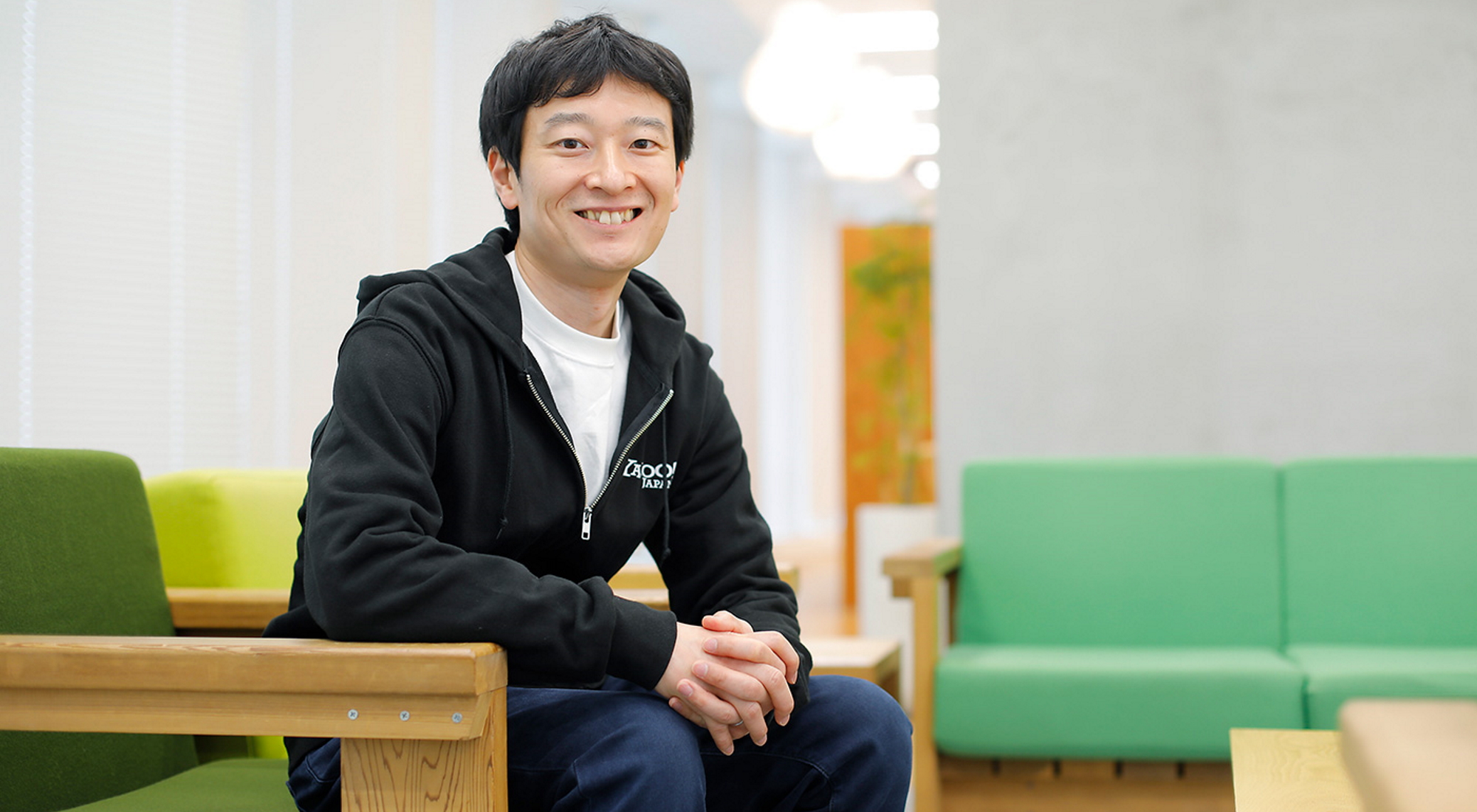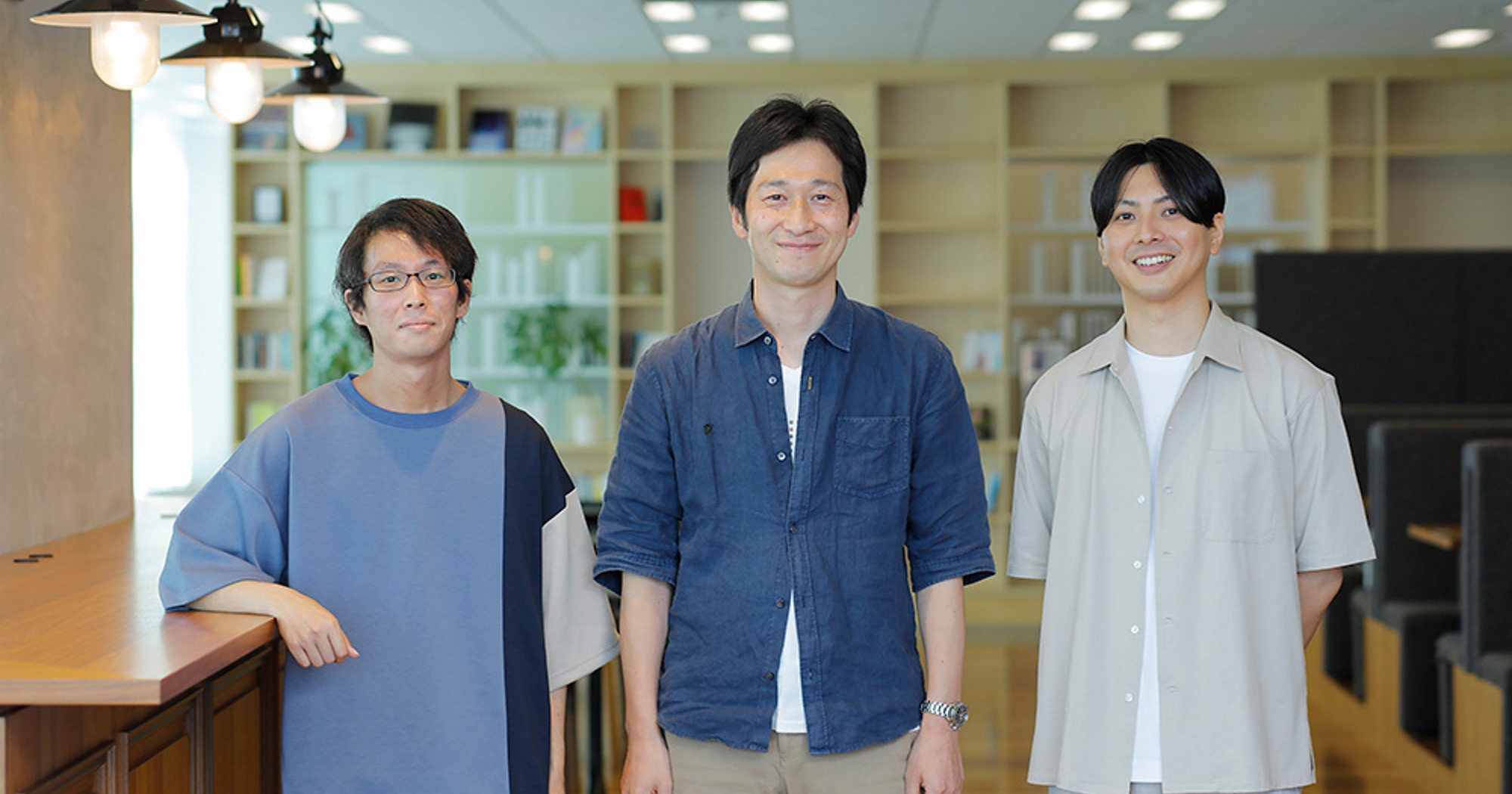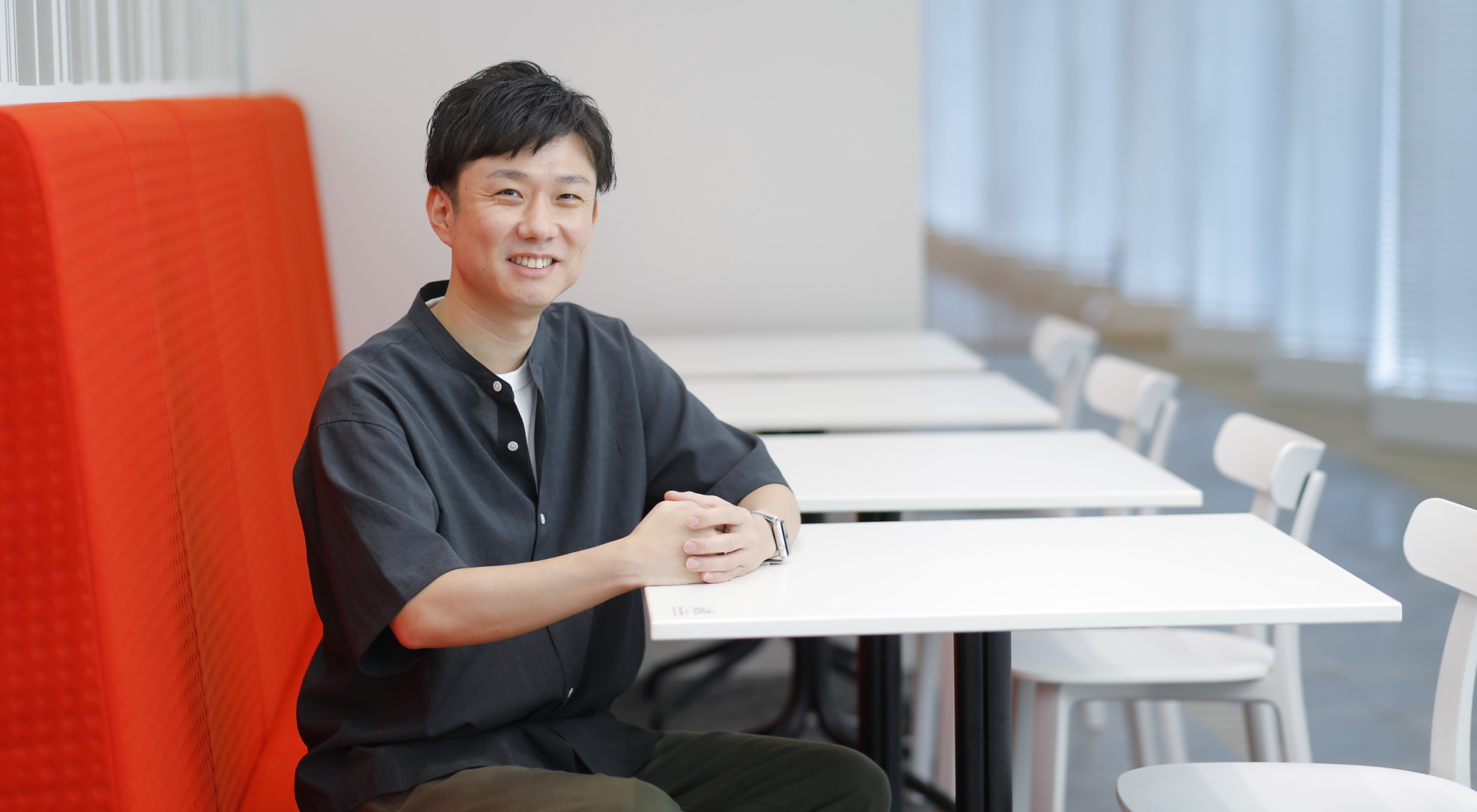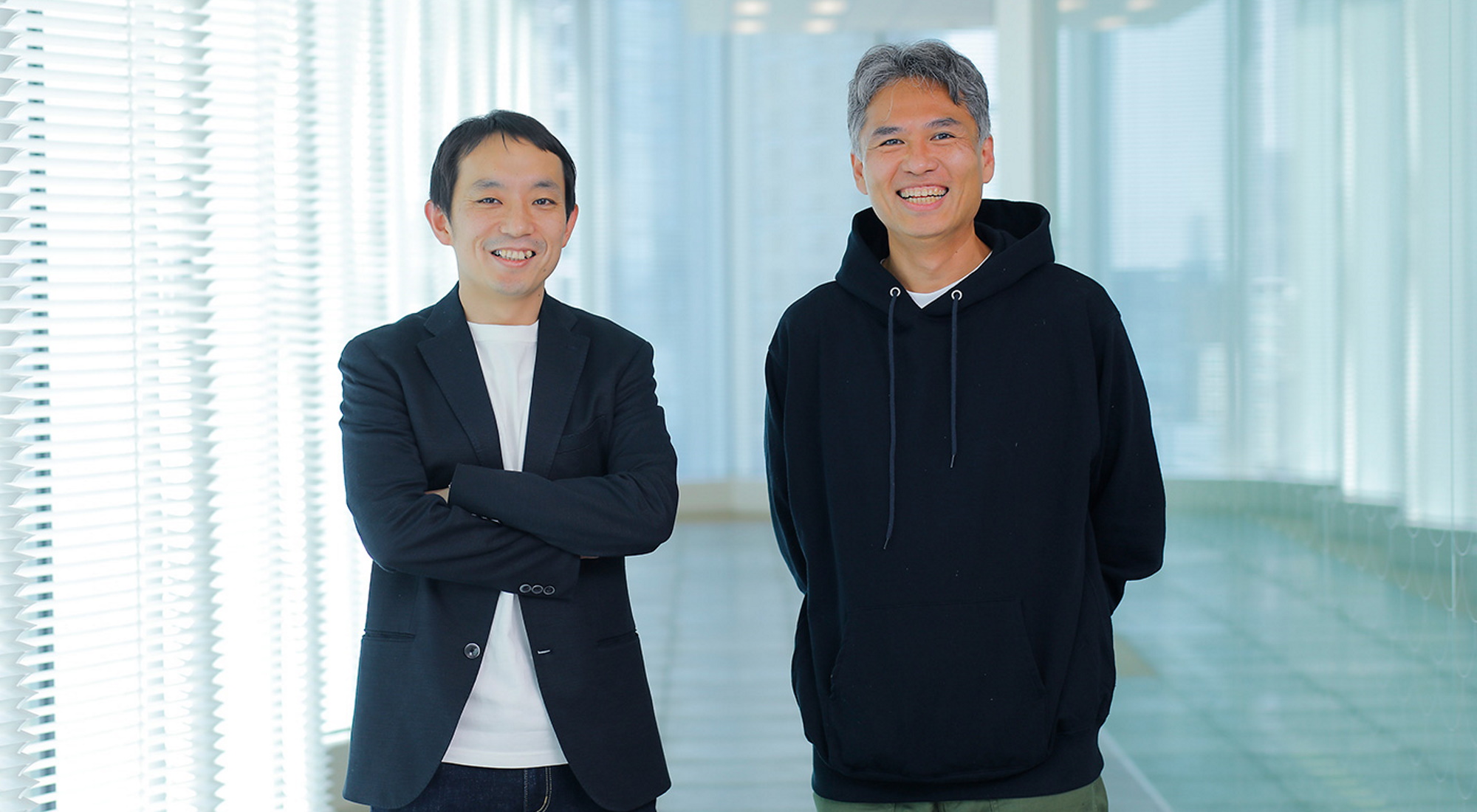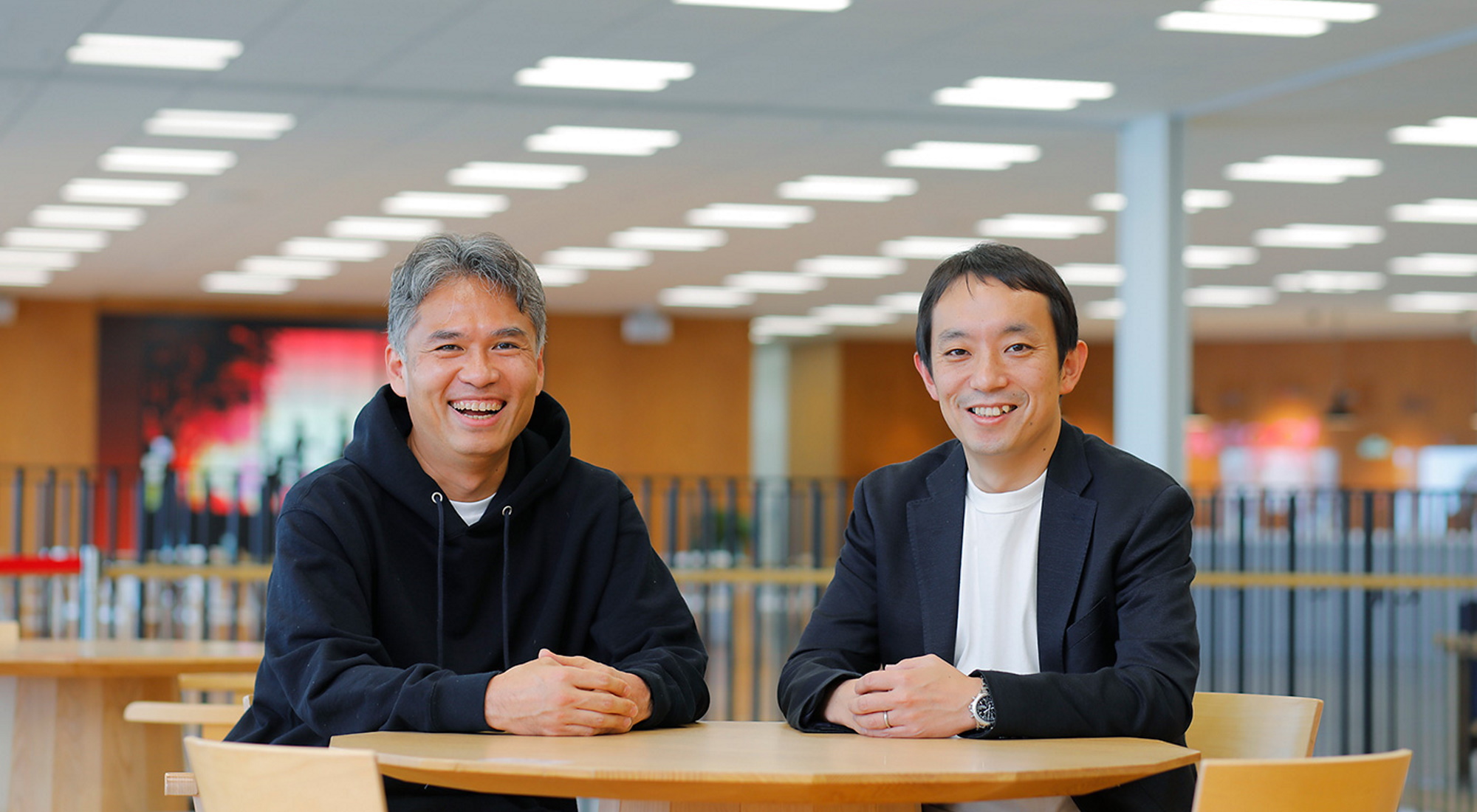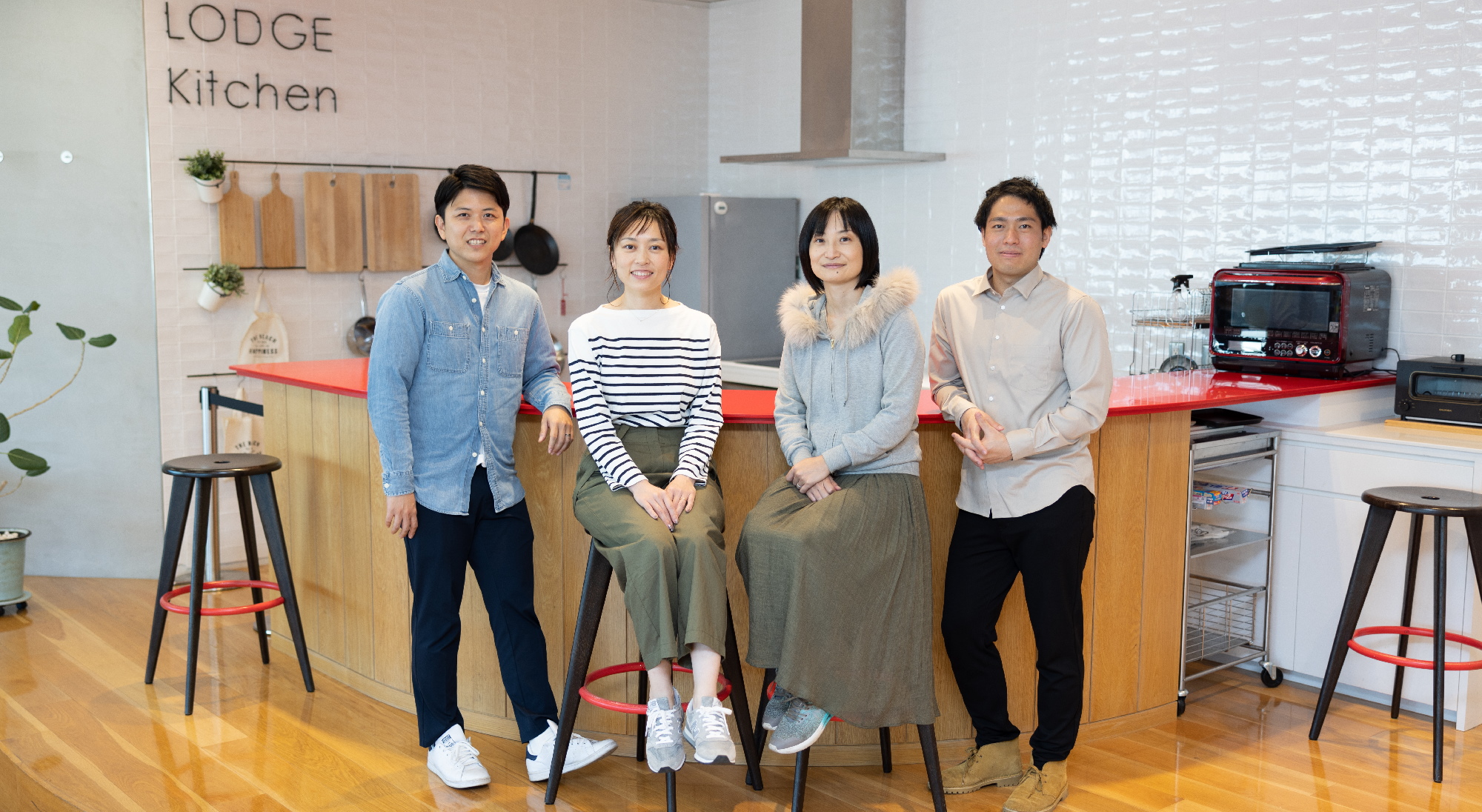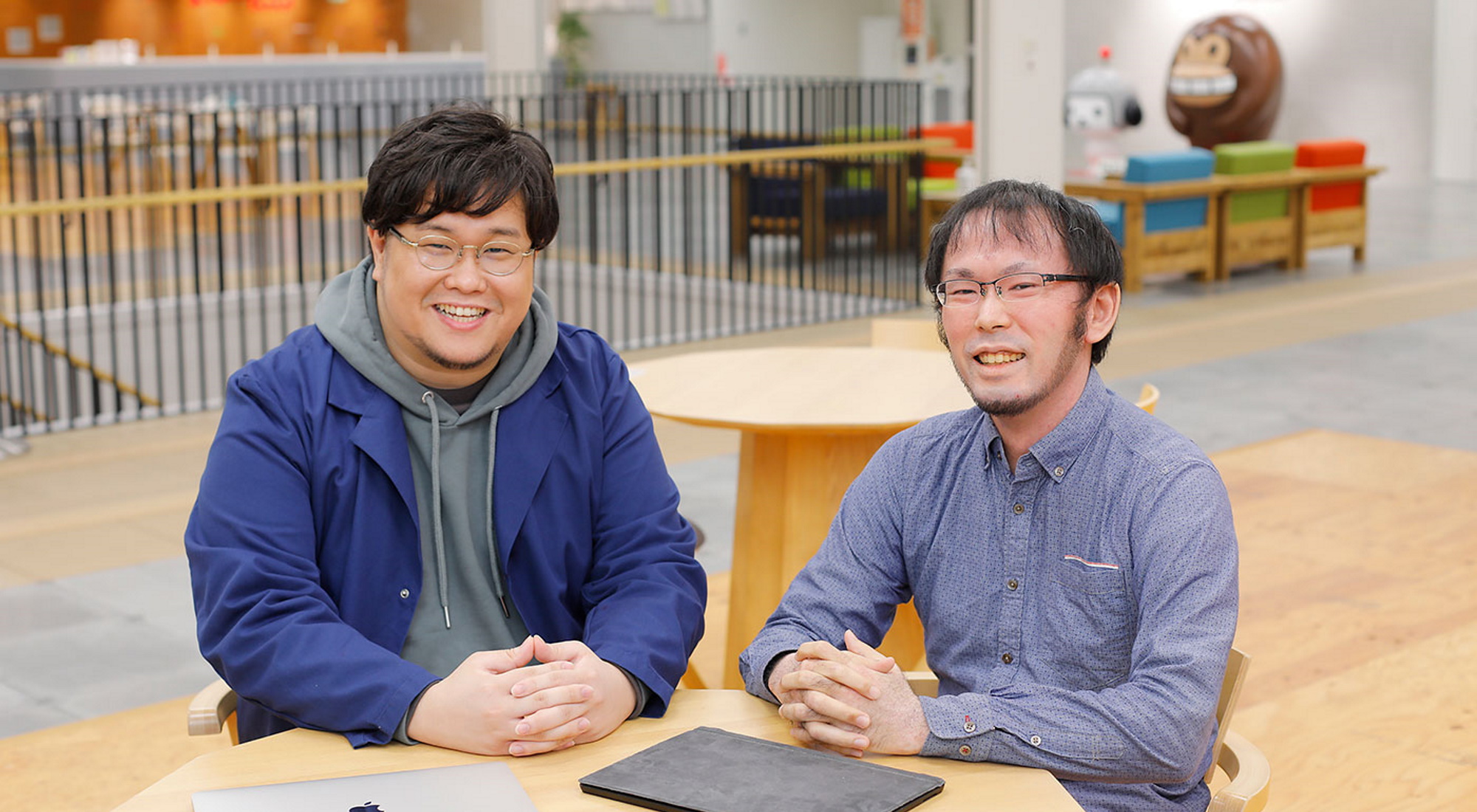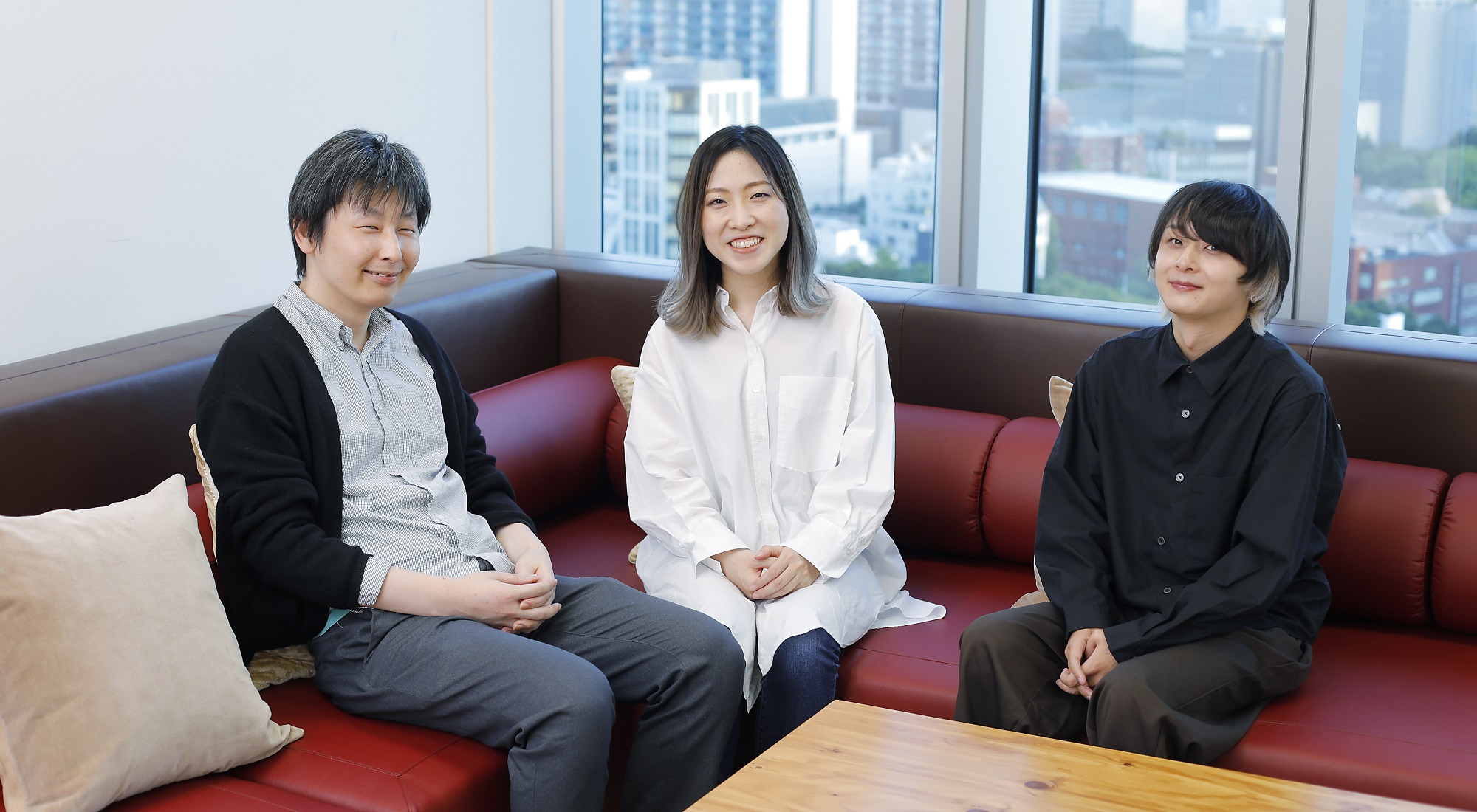最高技術責任者兼執行役員として、ヤフーの技術経営を牽引する藤門千明。彼のキャリアをたどっていくと、インターネット企業の中でのエンジニアの成長に欠かせない要件のいくつかを発見できるかもしれない。
入社後すぐのプロジェクト「Yahoo!ウォレット」を経て、彼が配属されたのは、他人のドアを土足で蹴破ることも辞さない“特殊部隊”。主体的介入の日々で彼が学んだこととは?
藤門の言葉に会議は凍りついた
決済システム「Yahoo!ウォレット」の開発とその物販ビジネスへの展開が一段落すると、藤門は、そろそろ新しい仕事にチャレンジしたくなった。
2008年、自ら申し出て配属されたのが、エンジニア3人だけの“特殊部隊”だった。
「部門を越えて、社内のシステムのお困りごと全般を引き受ける専任部隊。火を噴いている、さまざまなサービスやプロダクトの開発部門からリクエストを受けると、すぐさま動いて解決する“ お助けチーム”です」
最初は特に名称がついていなかったが、彼らの課題解決ぶりが知られるにつれ、チームは自然と「SWAT」と呼ばれるようになった。
その動きが、警察などに設置されている特殊部隊を想起させるからである。ちなみにSWATは現在では正式名称になり、CTO直下の組織として存続している。
SWATが最初に“出動”したのは、マーケティング事業部門が所管する、ユーザー向けキャンペーン展開のためのプラットフォームの作り直しという事案だった。
マーケティングの事業担当者、開発担当のディレクター、そして社員エンジニアがそれぞれ1名、さらに業務委託のエンジニア3名で構成されるプロジェクト。

「すぐ気づいたのは、組織の問題。マーケティング、ディレクター、エンジニアの間で意思疎通がよくできていなかった。マーケティング部門はいわば社内顧客。そこから上がってきたニーズはきちっとした要件定義もせず、そのままエンジニアに流れるだけ。顧客がなぜこうしたプラットフォームを必要とするのか、実際に作ったものの使い勝手はどうなのか、具体的な改善点は何なのか。そのあたりの理解がほとんどできていなかったのです」
そこで藤門らは、マーケティング担当者に直接会って話を聞くことにした。担当者はシステムのことは詳しく知らない。
「いい感じで作ってください」と要求はアバウト。間に立つディレクターも、「いい感じ」の内容をつかみきれず、事業側の言葉をそのままエンジニアに伝えていたという実態が浮かび上がった。
「ディレクターは顧客の漠然とした要求から真の課題を発見し、それをシステム要件として定義することが欠かせないのですが、これができていなかった。案の定、会議の場でそのディレクターとはケンカになりました」
そのときの藤門は、焦りや葛藤から思わずこう啖呵を切ってしまったという。
「伝書鳩のような仕事しちゃだめですよ」
年上のディレクターに入社3年目の藤門が投げつけた言葉に、会議の空気は一瞬、凍り付いた。
役割「分担」ではなく、役割「分解」が必要
しかし、これは顧客の要望をシステムとして具現化する仕事をしたことのあるプログラマーなら、誰もが一度は心の内に浮かぶ言葉ではなかろうか。
「…と客が言ってるんだよねえ。俺もよくわかんないんだけど、なんとか来週までによろしく」と、営業やシステムエンジニア(SE)に言われ、わけもわからずコードを書かされるプログラマー。
業界よくある話の一つではあるのだが、藤門はそれを黙認していたのでは、良いコードは書けないし、より良いプロダクトは作れないと感じた。
もちろん、SWATチームがその場しのぎ的に、ちゃちゃっとプログラムを書いて提示はできる。
「しかし、システム開発の正しいフローを定着させないと、SWATチームが去った後に、プロジェクトが機能しなくなる。そのために、エンジニアとディレクター、事業側が互いに歩み寄る必要がある、とメンバーには訴えました」
システムの規模が大きくなり、複雑になればなるほど業務の分担は細かくなるが、そうなればなるほど、相互のコミュニケーションを密にする必要がある。
暗黙の職務分担範囲を越えて、他の人の職務に主体的に介入したり、そのときの状況に合わせて役割分担の境界を調整する必要も出てくるだろう。
お困りごと即解決で鍛えた、アサーティブな仕事のやり方
そもそもSWATは、他人の家のドアをぶち破り、土足で踏み込む特殊部隊だ。だから自己主張が強くなくてはいけない。とはいえ、その主張を、相手の権利を侵害することなく、誠実に、率直に、対等に表明しなければ、真意は伝わらない。そうした態度のことを英語では「アサーティブ(Assertive)」と表現する。
アサーティブな仕事のやり方というのは、プロジェクトに介入するとき、まずは「どこか、いまお痒いところはないですか」と下手に構えることだ、と藤門は言う。
SWATは戦闘的プログラマー集団ではあるが、介入する組織が持つ技術や文化を頭ごなしに否定することはない。
「とても細かい例だと、プログラミングでインデントにスペースを使うか、タブを使うかは、そのチームのお作法。これらの積み重ねがチームの文化を作りますから、問題がなければ、躊躇なくチームの流儀に従います」
ただ、指示があるまで待機することはしない。技術的問題であれ、組織的問題であれ、速やかに課題を発見したら、遠慮なくその改善を提案し、実行する。
最初は迷惑そうにしていたプロジェクトサイドも、最終的には課題が解決してホッとする。
「入るときは土足ですが、最後は恩を売って帰ってくる。だから、いやでもすぐに顔を覚えてもらいました(笑)。SWATでさまざまな分野の課題に触れたことは、エンジニアとして視野を広めることに役立ちました。
エンジニアが事業領域を横断してモノを見られるチャンスはそう多くない。課題を解決しながら、自分の専門領域を広げることができます。
私自身、大学院時代はコンピューター・グラフィックスの専門家気取りだったんですが、学生時代の専門なんて、あくまでも仮のスキルにすぎない。自分の可能性を広げたい若い人にとってこそ、SWAT的な立ち位置は向いていると思います」
そう藤門はSWAT体験を振り返るのだった。
藤門 千明
筑波大学大学院を卒業後、2005年に入社。エンジニアとしてYahoo! JAPAN IDやYahoo!ショッピング、ヤフオク!の決済システム構築などに関わる。決済金融部門のテクニカルディレクターやYahoo! JAPANを支えるプラットフォームの責任者を経て、CTOに就任。