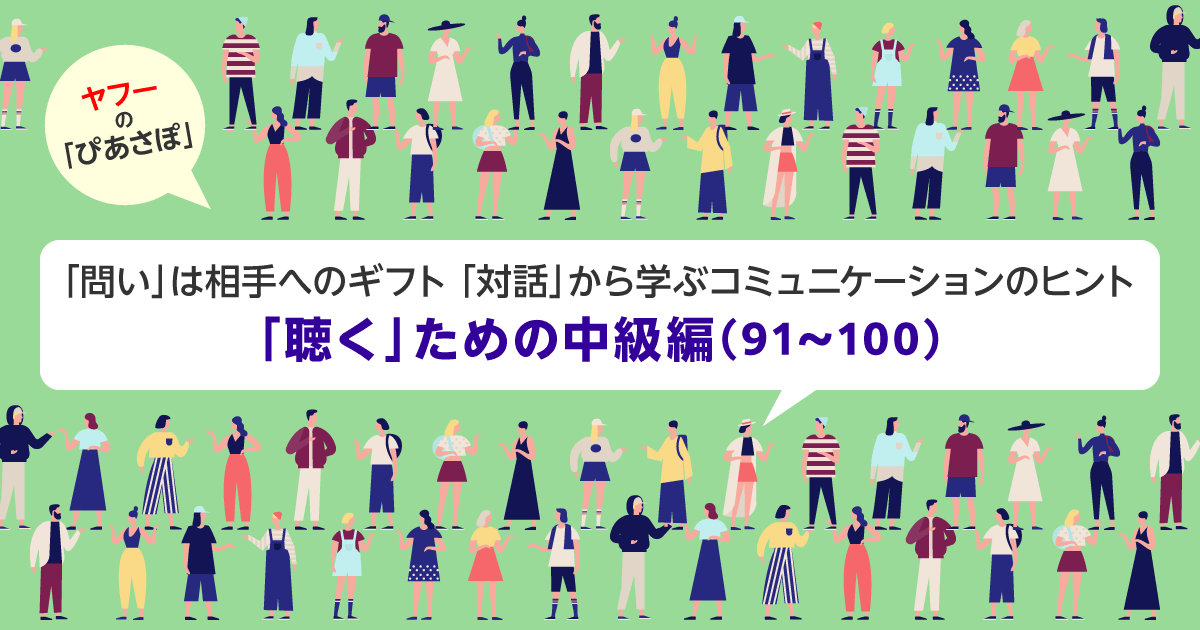この連載(※)ではこれまで「聴く」ためのヒントをお伝えしてきました。
※1よい対話にするために心がけたいことや「聴く」ためのヒントを、「YJぴあさぽ」のメンバーがお伝えしています。
YJぴあさぽ:産業カウンセラーや国家資格キャリアコンサルタントの有資格社員によるボランティアプロジェクト。
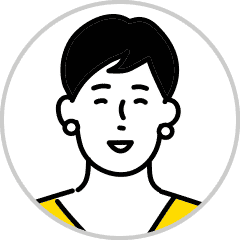
- まさみん
-
ZアカデミアでZホールディングス全体の組織活性、人材育成、コミュニケーション円滑化の取り組みなどを担当。
保有資格:国家資格キャリアコンサルタント、トラストコーチングスクール 認定コーチング スキルアドバイザー
これまで、「聴く」または「聴いてもらう」90個のヒントをお伝えしてきました。いよいよ最後の10個は上級編です!
ここまで読んでくださった方は、「聴く」の大切さを感じていて、もしかしたらコミュニケーションがスムーズになっているかもしれませんね。
そんなみなさんに今回は、「問い」の大切さを贈りたいと思います。
- 「聴く」上級編 目次:
- 91.「問い」は最高のギフト
- 92.Yes or No それとも…?「問い」には2種類ある
- 93.意外な「問い」のギフトがうれしいことも
- 94.誰とでも仲良く、誰とでも理解しあえる?
- 95.子どもに質問してもらうと、思いがけない問いも
- 96.「良い質問」をしよう! と頑張りすぎない
- 97.受け止めて反応する、「感想」をつぶやいてみる
- 98.やることではなく、「やめること」を決める問いも効果的
- 99.聴いた後は、自分のケアも忘れずに
- 100.最後に 読んでくださったあなたへのギフト
- YJぴあさぽメンバーおすすめ:「対話」「コミュニケーション」のヒントになる本
91.「問い」は最高のギフト
集中して、相手のことを思いやりながら聴けたら、実はそれだけで相手への素晴らしいギフトになっていると思います。
聴いていると、ふと、この人にこの「問い」をしてみたいと感じることもありますよね。
あえて、なにか1つ「問い」を投げるとしたら?
その問いには、とても大きな意味があると思います。
参照)50.「聴く」ときに大切なのは、相手を思う気持ち
ギフトは、相手のことを考えて贈りますよね。
その方のことを想像して、お花であれば、「あの人は、いつも水色の持ち物が多いから、好きな色なのかな?」と考えて淡い水色のブーケをアレンジしてもらう。
食べ物であれば、「スイーツの話を良くしているけど、最近、ちょっと食べすぎていて…とも言っていたから、甘さ控えめのヘルシーなスイーツがいいかな?」など。
「問い」も同じです。
相手のことをよく考えて、「問い」というギフトを贈ってみましょう。
92.Yes or No それとも…?「問い」には2種類ある
キャリアコンサルタントの学びの中では「閉ざされた質問」「開かれた質問」の2つがあります。
「閉ざされた質問」は、YesまたはNoで答えられる質問。
「開かれた質問」は、OPEN QUESTIONともいい、YesやNoでは答えられない質問です。
たとえば、
A:「業務を行う上で、悩みがありますか?」
には「はい」か「いいえ」で答えますよね。これは、「閉ざされた質問」です。
少し、相手の方に話してもらおうと考えたときは、この質問をこんな風に言い換えます。
B:「業務を行う上で、どんな(または、何か)悩みがありますか?」
だったら、Aの質問よりも「どんな悩み」なのか話してくれるように思います。
こちらは、「開かれた質問」です。
Aの質問の仕方には、「Yes」「No」なので、話し手が簡単に答えられるという良い点もあります。
Bの質問は、より話し手を知ることができますが、「なんで?」「なにが?」「どうして?」と立て続けに聴くと、話し手が疲れてしまうこともあるかもしれません。
この2つの特性を理解して、「問い」を使い分けることができるといいですね。
93.意外な「問い」のギフトがうれしいことも
先にも書きましたが、「問い」はギフトなので、その人が自分では「思いつかないもの」を贈ってもいいと思います。
人には、生きてきた道の中で、思考の癖が出てきます。
「仕事はしなくてはいけない」
「朝ごはんは食べなくてはいけない」
「上司よりも先に帰ってはいけない」
など、案外たくさんの思い込みがあるもの。
でも、「must(〇〇でなければいけない)」だけで考えない方が、思考はより自由になります。そんなときには、
「本当にそうですか?」
という「問い」を贈ってみてはいかがでしょうか?
たとえば「朝ご飯って、本当に食べないとだめですか?」という問い。
はじめは、「え? 当たり前じゃない、朝ごはんは食べないといけないよね!」と思う人もいるようです。
でも、実は1日くらい朝ご飯を食べなくても大丈夫ですよね。無理して食べたり、作ったりするよりもほかに方法もありそう、などという気づきもあるかもしれません。
人は、本当に多くの「しなければいけない」に縛られています。私もそうです。
だからこそあえて、「~できたらいいなぁ、くらいの気持ちでもいいのでは?」という問いを贈ってみてもいいかもしれません。
意外なギフト(問い)にはじめは驚かれるかもしれませんが、自分では気づかなかったことを考えるきっかけを喜んでくれるかもしれません。
94.誰とでも仲良く、誰とでも理解しあえる?
「問い」から少し離れるかもしれませんが、誰とでも仲よく、誰とでも理解しあいたいという思いが強い人も多いと思います。
でも、ここで1つだけお伝えさせてください。
それは、人とのコミュニケーションはどんなに、こちらが頑張っても、相手の気持ちが0だと満足度100%にはならないということです。
私とAさんがいて、手をつなぐ場面を想像してみてください。ここでは、手をつなげることが満足度100%だとします。
私が手を出しても、Aさんが手を出さなければ、成立しません。ですが、Aさんに手を出してもらおうと無理に頑張ってしまうことはありませんか?
あなたが手を出しても手を出してくれない人もいるし、手を出してくれる人もいる。
手がつなげた時は、通じ合ったと感じてあなたも相手もハッピーです。
これは、上長と部下、親子、友人…すべての人間関係においていえることだと思います。
いくら自分が最大限手をのばしても、努力しても、伝わらないことはあります。努力することは大切だけど、思うようにいかなくても、それは、あなたが原因でないこともあります。
自分のできる限りの努力はするけれど、そこから先は、相手がある時は、思うようにいかないこともあるので、「自分は最大限手を伸ばした!」と思えばいいと思います。
ある人とうまくいかない、と悩んでいる方には、
「あなたは、十分努力したんですよね。でも、うまくいかないこともあるのでは?」という問いを贈るのもいいと思います。
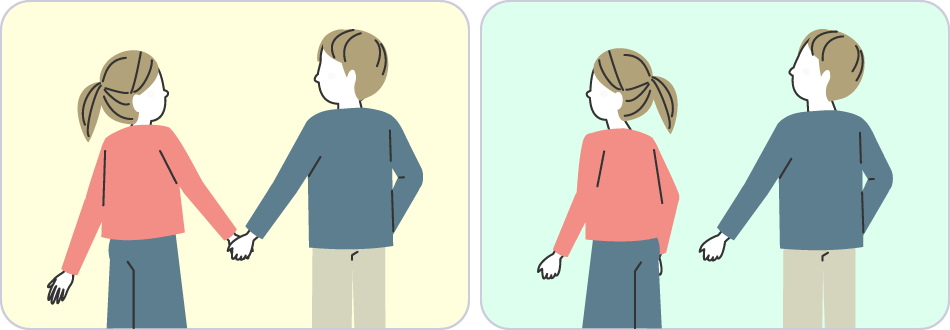
95.子どもに質問してもらうと、思いがけない問いも
また、「子どもに質問してもらう」のも、思わぬ発見があるのでおすすめです。
わたしたち大人は、子どもにたくさん質問をしていると思います。
「今日、学校はどうだった?」
「習い事は、楽しい?」
「友だちとはうまくいっている?」
など…。ついいろいろ質問してしまうのではないでしょうか?
ときには趣向を変えて、子どもが大人(親)にどんな質問をしてもいい時間を設けてもおもしろいと思います。
私は、家族で食事をしている時間や、ドライブをしているときなどに、順番に質問をしていく「5つの質問タイム」を取ることもあります。
子どもからは、たとえば、
「今、一番行きたいところはどこ?」
「5000円あったら何を買う? 何がしたい?」
など、子どもならではのユニークな発想の質問が飛んできます。
こんな風に、職場でも新しい仲間が加わった時には、その方を良く知るために、質問タイムを設けてみてもいいかもしれません。
参照)52.自分についてのクイズで「自分」を知る
96.「良い質問」をしよう! と頑張りすぎない
なかには、「良い質問」ができそうにない…、「良い質問」をしようとしすぎて、「聴く」に集中できない!などに気づいた方もいらっしゃるかもしれません。
そんな時はいつでも、「聴く」に立ち戻り、まず「全集中で聴いて」、あなたの「聴く」に磨きをかけてみましょう。
「次にどんな質問しようかな…」と考えているときの顔は、案外相手にもわかってしまうもの。まずは、「聴く」だけでも十分相手へのギフトになります。
97.受け止めて反応する、「感想」をつぶやいてみる
また、一生懸命、全集中で聴いてきたあなたの心に今思い浮かんだことを「問い」の代わりに「ギフト」として贈ることもできます。
たとえば、まだ小さいお子さんの育児と仕事の両立をされている方からお話を聴くことも多くあります。
「子どもはしょっちゅう熱を出すので、保育園と仕事を休むことになります。上長も、周りの方も、気にしなくていいと言ってくれるのですが…。これでいいのかな…もっと、子どものそばにいてあげたい、でも、仕事もちゃんとやりたい!」
こんな風に、悩んでしまう方がとても多いように思います。
私自身も、同じような気持ちを感じていたことがありました。そのため、ついつい「一時のことだから、大丈夫!」「周りは案外気にしていませんよ」と言いたくなってしまいます。そして、相手のためになる良い「問い」も思い浮かばない。
そんな時、あなたは、どんな言葉をかけるでしょうか?
私は、
「○○さんは、今、全身全霊で子育ても仕事もしているのだと思いました」
その方の思いを受け止めて、反応する。感じたことをていねいに伝えるようにしています。
「問い」がなくても、これだけでも相手の気持ちは少し楽になるように思います。
98.やることではなく、「やめること」を決める問いも効果的
YJぴあさぽで話を聴いていて感じるのは、とても一生懸命な人が多いということです。
仕事も、子育ても介護も、自分の学びも、趣味も! とフル稼働で毎日頑張っているのに、それでもまだ、「あれができていない…」と話す方もいます。
そんなときは、どうすれば「できないことができるようになるか」という「問い」ではなく、「今、どれか1つやめてみるとしたらどれですか?」と問うこともあります。
「今は」という言葉をつけて、優先順位を明確にするための「問い」も効果的です。
99.聴いた後は、自分のケアも忘れずに
全集中で聴いて、余力があれば「問い」というギフトも考えて…。聴き終えた後のあなたは、実はくたくたかもしれません。その後、自分をしっかりケアする時間もとても大切です。
YJぴあさぽでは、2名で30分お話を聴きますが、終了後はぴあさぽ同士で対話の振り返りをしたり、今の気持ちを伝えあったりしています。
あなたが、誰かの話を全集中で聴いた後は、たとえばこんな風にクールダウンしてみてはいかがでしょうか。
・一人になって自分をハグする
・鏡に向かって伸びをして、最後ににっこりしてみる
・「私、ちゃんと聴けた!」と自分で自分をほめる

100.最後に 読んでくださったあなたへのギフト
ここまで読んでくださって、ありがとうございます。
あなたにどんな「問いのギフト」を贈ることができるか、考えてみました。
あなたは、誰の話を聴きたいですか?
あなたは、誰に話を聴いてほしいですか?
思い浮かんだのは、この2つの「問い」でした。
この答えは、あなたが、気になる人、わかりあいたい、わかってほしい人だと思います。
この問いを受けて浮かんだ人が、気になる人、わかりあいたい、わかってほしい人なのだと思います。その人の話を聴いてみてください。そしてあなたの話を聴いてもらってください。
何が起こるでしょうか。
楽しみですね!
参考書籍)「良い質問」をする技術 電子書籍版
「対話」「コミュニケーション」のヒントになる本
「相手との向き合い方」に関心がある方におススメ
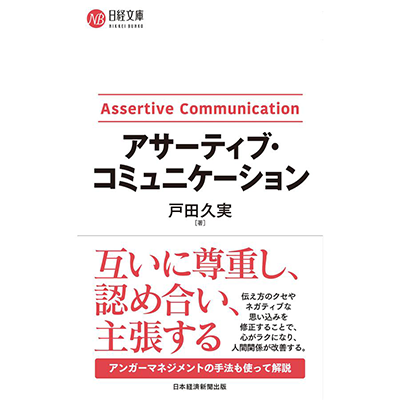
アサーティブ・コミュニケーション
著者:戸田久実

私は、これまで多くの方との面談を通じて、相手と対話するうえで思い込みや先入観を持たずに向き合うことが大切だと実感してきました。
ただ、そう頭ではわかっていても、その相手についての情報を知る機会が他にもあることで、思い込みや先入観をなくして対話することは容易ではないと感じています。
だからこそ、「アサーティブコミュニケーション」のニーズが高まっているのだと思います。
アサーティブコミュニケーションとは、お互いの立場や主張を大切にした自己主張・自己表現の一種で、心理的安全性実現のための伝え方・向き合い方の面で注目されています。
この本では、「相手に伝える」スキルだけでなく、どうすれば相手に対して思い込みや先入観を持たず、対等な向き合い方ができているのか? というマインド面にもフォーカスしています。
リモートワーク環境など含め、さまざまなリアルな事例をもとに、自分の対話におけるクセと向き合えました。
また、仕事だけでなく、家族や友人などプライベートの対話においても学べる点が多いと感じました。「相手との向き合い方」に関心がある方におススメです!(LINE:まみや)
【関連リンク】
- 「対話」から学ぶコミュニケ―ションのヒント 「聴く」ための準備編
- 「対話」から学ぶコミュニケ―ションのヒント 「聴く」ための初級編(11~20)
- 「対話」から学ぶコミュニケ―ションのヒント 「聴く」ための初級編(21~30)
- 「対話」から学ぶコミュニケ―ションのヒント 「聴く」ための初級編(31~40)
- 「対話」から学ぶコミュニケ―ションのヒント 「聴く」ための中級編(41~50)
- 「対話」から学ぶコミュニケ―ションのヒント 自分を知り、「セレンディピティ」を高めるために意識したいこと 「聴く」ための中級編(51~60)
- 気持ちを「言葉にする」ために心がけたいことは? 「対話」から学ぶコミュニケーションのヒント 「聴く」ための中級編(61~70)
- 「偶然」を「チャンス」に変えるための5つのポイントは?「対話」から学ぶコミュニケーションのヒント 「聴く」ための中級編(71~80)
- 「聴いてもらう」「聴いてもらい上手」になるには? 「対話」から学ぶコミュニケーションのヒント 「聴く」ための中級編(81~90)
- グッドキャリア企業アワード2022」の受賞企業を決定しました(厚生労働省) - YJぴあさぽは、厚生労働省のグッドキャリア企業アワード「イノベーション賞」を受賞しました。2023年度は、事務局含めて16名で活動中。