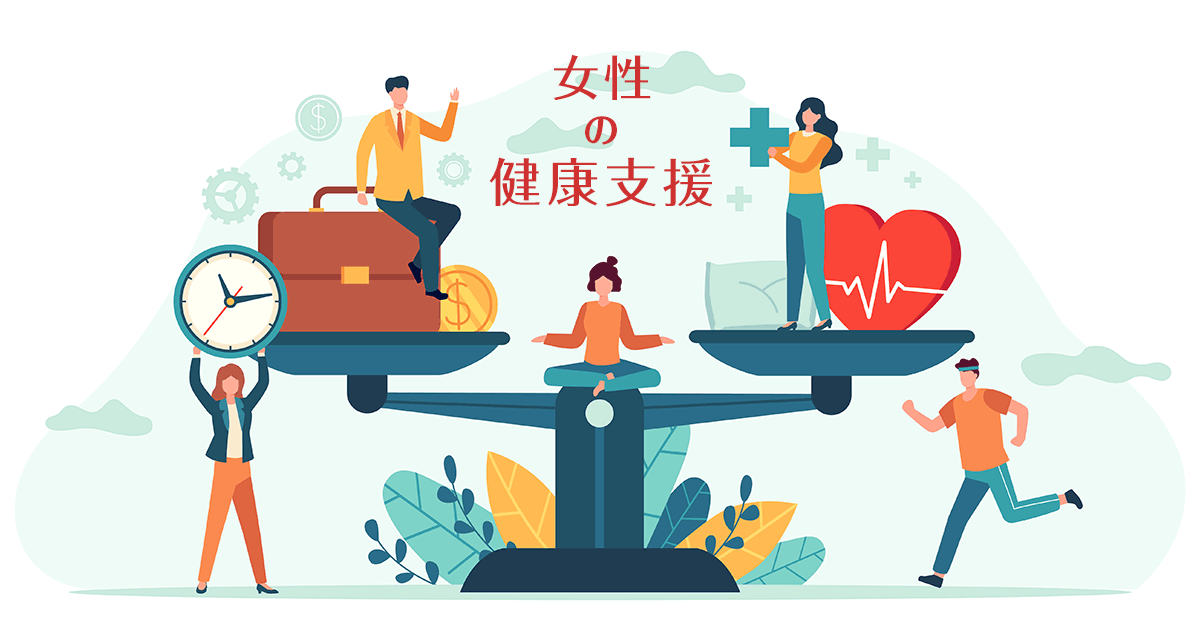今回は、有志社員で構成された「女性の健康支援プロジェクト」をご紹介します。これは「女性の健康について社員とその上司・同僚の理解が深まり、活き活きと健康に働ける文化醸成」を目的に2014年に発足したプロジェクト。
健康に関する「サポーター」として社員の相談を受けるなど、女性の健康についての啓発活動を行っています。発足8年目になるこのプロジェクトのこれまでの取り組み、私たちが心身ともに健やかに働き続けるために大切なことなどを聞きました。

グッドコンディション推進室で従業員の健康増進企画を担当。女性の健康支援プロジェクトのプロジェクトマネージャーでもある。
心と体の健康維持のために心がけていること
「気づくこと」です。日々仕事や家事、育児などで忙しいと、気づかないままで不調にどんどん向かってしまうこともあると思いますが、そこからまた回復するのは大変です。 「何が今、自分の体や心で起こっているのだろう?」と感じながら過ごし、無理をしすぎずに調整して調子を戻していくのが、働く上で大事だと思います。
水摩 直子(みずま なおこ)
北九州センターに所属していた2014年にこのプロジェクトを知り、東京に異動後、女性の健康支援プロジェクトのコアメンバーとして活動をスタート。
心と体の健康維持のために心がけていること
「心身ともに健やかであること」が一番だと思っています。常に「年相応であればよし」といつも思っていて、その上で自分の心と体から発せられる声に耳を傾け、何か違和感があるところに対しては、食べ物に気をつけたり運動したり、リフレッシュしたり。早めにケアをすることが大切ですね。

- 秋橋 仁美(あきはし ひとみ)
-
北九州センターで女性の健康プロジェクトのメンバーとして活動後、現在はダイバーシティ推進事務局として、「女性の健康支援プロジェクト」を担当。
心と体の健康維持のために心がけていること
体の声をおざなりにしないこと。忙しいとつい「このくらい大丈夫かな」と、ついつい無理してしまいますが、そうすると後でやはり体にしっかり影響が出てしまいます。「ここはもうちょっと頑張っても大丈夫」「今はいったんちょっと立ち止まった方がいい」などの判断をするためには、健康についての情報をしっかりインプットしておくことも大事だと思います。
女性の健康プロジェクトとは
女性の健康プロジェクトとは
・2014年に20名が「女性の健康検定」を受検したことがきっかけ
・受検した有志メンバー(18名)で活動をスタート
・女性の健康相談窓口として社員の健康関連の相談にのる
・女性の健康についてサポーター内で勉強会を実施
・社員向けに女性の健康をテーマにした勉強会やセミナーを実施
鈴木:
女性の健康支援プロジェクトは2014年、管理職含めた20名が「女性の健康検定(※1)」を受検したところからスタートしています。私は当時、健康推進室に所属していて、検定受検のための勉強会を試験前に実施するなど女性の健康検定受検をサポートする立場でした。
※1 女性の健康検定:
2012年より実施。女性の健康とワークスタイルについて、基本的な知識を習得していることを認定する検定。女性の健康についての実情やデータ、年代ごとに知っておきたい体の変化についての正確な知識、健康でより良い働き方を選ぶことを目的とした年代ごとの提案などを学べる。
このときに受検した社員は全員合格しましたが、このプロジェクトが今後どうなっていくかは、まだこのときは決まってはいませんでした。ですが、「せっかく合格したので、これをきっかけに社員のために何か活動していきたい」という声が自然と上がり、有志メンバーで女性の健康支援プロジェクトとして活動することになりました。
ヤフーには「パパママプロジェクト(※2)」という有志プロジェクトがすでにありました。そこで実施していた、子育て中の社員がいろんなテーマでランチ会を開催しておしゃべりする形がうまくいっていたので、同じように、まずは検定を受けた有志メンバーでランチ会を開催するところから始めました。また、産業医の先生にセミナーをお願いしたり、社内PR用の動画を作ったりして活動を紹介するなど、手探りで活動の幅を少しずつ広げていきました。
※2 パパママプロジェクト:
女性の健康支援プロジェクトと同じ、有志メンバーによるプロジェクト。2012年から活動をスタート。ランチ時間に子どもを持つ社員が集まり育児関連の相談や情報交換ができる「パパママカフェ」などを開催している。

性別に限らず、働く人に知っておいてほしいことを伝える
鈴木:
先ほどお話した有志メンバーのランチ会で、たとえば「生理がつらい」という、友だちともあまり話さないようなつらさや、生理休暇を取ったときに困った経験などを共有し合えた経験が、この活動の原点になったような気がします。「自分たちの感じていることを正直に話せる場」だったことで、同じ女性ではありますがそれぞれの違う視点や価値観を共有し合い、理解できました。
さらに、セミナー実施後のアンケートで参加した社員からの声も次第に集まるようになったので、そこでわかった課題もメンバー間で共有することによって、この活動を進める意義がより明確になっていきました。
私は最初、北九州センターからこの活動を見ていましたが、「女性の健康」にターゲットを絞って推進活動を行っていることにまず驚きました。また、有志活動とは思えないほどみんな熱い思いを持って活動しているからこそ、ここまで根付いて継続できるのだろうと感じています。
当時、鈴木に「なぜ女性の健康に限って活動しているのか」たずねたことがあります。そのとき鈴木が言っていたのは、「女性は生理休暇を取得する人が少ない。体の変化による不調も多いのに、自分が大変だということにもなかなか気づかずに、体調に関するバックアップがない状態で働き続けなければならない。その大変な部分を女性の健康支援プロジェクトで支援したいからこの活動を続けている」ということでした。
当時の私はまだ、「男性も女性も同じ」だと思っていましたが、この鈴木の言葉を聞いて、ヤフーで女性が健康に働き続けることができる土台を作ろうとしているパワーを感じました。女性が健康で働き続けられる環境をより良いものにすると、企業価値も高まると考えている、とも当時の鈴木は語っていたので、ぜひ一緒に活動していきたいと伝えました。
また、ヤフーは若い人が多い会社だからこそ、この活動が必要だと思いました。若いうちは健康で体調について不安があまりないので、思い切りまい進できます。でも、30代ぐらいにホルモンバランスや体の変化によって立ち止まってしまう瞬間もあることを、私は自分の経験からわかっていました。だからこそ、できるだけ早く健康に関する情報や知識を得てもらいたい、この活動を通して伝えていきたいと思いました。
活動を進めていく間には、「女性の状態をまず男性に理解してもらえないといけないのではないか」という議論もしました。女性特有のつらさや大変さばかり伝えるのではなく、女性の体を知らない人に知ってもらうことも大切なので、知ってもらう機会を作ろう、などと話を重ねて、次第に活動の方向性が定まってきたような気がします。
2017年に社内で実施したダイバーシティウィークでは、「男性学を私たちも学んだほうがいいのではないか」と講師をお呼びしてセミナーを実施しました。これが初めて、このプロジェクトで男性に関することを学ぶ目的で実施した企画だったと記憶しています。
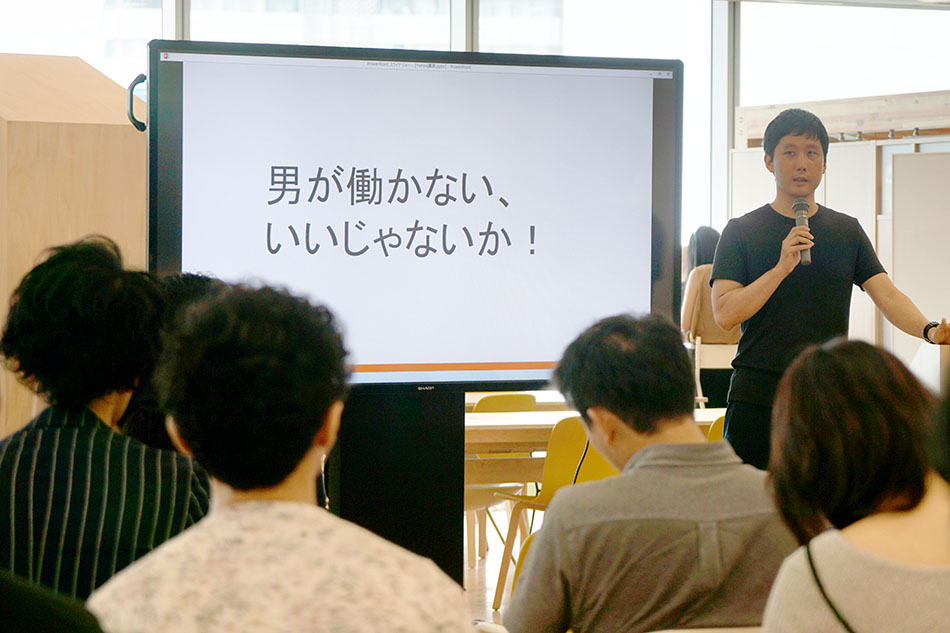
「女性の健康」とは言っていますが、ヤフーで働いている人たち全員が健康で働き続けるために知っておいてほしいことを伝える、というのが現在の方針です。
たとえば「がんセミナー」などもお昼休みの時間を使って実施しています。「女性の健康支援プロジェクト」ではありますが、男性も参加しやすいセミナーや雑談会などを実施していくことで、就業時間内で健康関連の知識を知る機会に触れてもらいやすい環境づくりも目指しています。
また、「更年期」をテーマに勉強会を実施したときには、参加した男性社員から「自分はあのとき更年期だったのではないかと思う」という声がありました。
「当時、心身がつらくてたまらない時期があったけれど、それは振り返ってみると、あのときは更年期だったのではないかと思う。そういう知識を早めに知る機会があれば、あとに続く男性社員の方々が何か不調を感じたときに、体のホルモンの変化に伴う症状かもしれないと早めに手を打てるのではないか」と言ってもらえたことがうれしかったですね。

「自分の体の変化に敏感でいること」は誰にとっても大切なこと
水摩:
体の変化を感じても、その変化から目をそらしてしまう人は、実は男女問わず多いような気がします。働き続けるためにも、毎日を楽しく過ごすためにも、体や心の変化を感じたときはその声や変化に意識をむけてほしいと思います。変化を感じたら必ず病院に行くなり、人に相談するなりして、対応にちゃんと結びつけてほしいですね。
近年は「人生100年時代」といわれ、高齢になっても働き続けるようになっていくと思います。
すべてのみなさんに活躍の場があり、すべての人が元気に活躍し続けられる社会があり、安心して暮らすことのできる社会が今以上に整ってくると思うので、やはり健康寿命はとても大切だと感じます。
長く働き続ける未来は、まだみんな経験しておらず、どうなるのかわからない世界です。100年先の未来、100年時代を見据えて健康管理に取り組むことで、若い人も多いヤフーだからこそ、何か新しいサービスが生まれるのではないかとワクワクしています。
秋橋:
以前参加したセミナーで聞いたのですが、もちろん個人差はあるものの、男性は「頑張らなくちゃいけない」「弱音を吐いちゃいけない」という傾向が強いのだそうです。そのため、健康面に関しても、不調を感じていてもつい頑張り過ぎてしまうところがあるのかもしれません。
誰もが安心して「今日はちょっと具合が悪いから休もうと思います」と言い合える環境にしていくことも、とても大切だと思います。
鈴木:
新型コロナウイルスのワクチン接種がはじまったときに、ヤフーは「副反応休暇(※3)」を導入しました。
当時、「ワクチンの副反応による不調で休む」という共通の経験をしたことで、「体調が悪くてどうにもならない」ことへの理解が、ヤフー内に限らず、誰にとっても深まったのではないでしょうか。「具合が悪いときは休んだらいいよ」と、人にも自分にも優しくなれたり、不調に対する想像力を働かせられたりするようになったように思います。
不調を感じたときは、適切に休んだほうが早く回復する、そうやって自分をケアすることが大切だと、自然に思えるようになってほしいと思っています。また、私たちが実施するセミナー後のアンケートで必ずある「もっと早く知りたかった」という声を減らしていきたいですね。
仕事で活躍するためにも、ベースとなる心と体の健康はとても大事なこと。心身の健康やウェルビーイングなども含めて、職場で自然に話せるような環境づくりにこれからも取り組んでいきます。
※3 副反応休暇:
就業時間内における社員の新型コロナワクチンの接種を認め、接種後に痛みや体調不良が発生し就業が困難な場合は、特別有給休暇の取得が可能
働くためのベースとなる心と体の健康はとても大事
・体や心の変化を感じたときは、意識をむけ、しっかり対応する
・「体調が悪いので休みます」と言い合える環境にしていくのも大切なこと
・健康関連の知識に触れてもらいやすい環境づくりを目指す
女性の健康支援プロジェクト 活動の歴史
| 2014年 | 女性の健康支援プロジェクト発足、管理職含めた従業員20名が「女性の健康検定」を受検 |
|---|---|
| 2015年 | 検定受検者の中から有志メンバーで活動開始 社内PR活動やランチタイム勉強会開催 女性の健康とワーク・ライフ・バランス アワード 奨励賞受賞 |
| 2016年 | ヤフーのダイバーシティスポンサーシップ制度(※4)開始 ダイバーシティ推進のプロジェクトの一つとして、活動を広げる 北九州センター・八戸センターでも活動開始 |
| 2017年 | ランチタイム勉強会や、社外講師によるセミナー開催を継続 「生理(月経)に関する社内アンケート」実施 |
| 2018年 | 「働く女性の健康チェックシート」によるセルフチェックを兼ねた啓発開始 女性の健康とワーク・ライフ・バランス アワード 推進賞受賞 |
| 2019年 | 北九州オフィス勤務の管理職23名が女性の健康検定を受検 |
| 2020年 | 女性の健康とワーク・ライフ・バランス アワード 推進賞受賞 コロナ禍でリモートワーク中心の働き方に ランチライム勉強会、セミナーはオンラインランチ開催に移行 ※鈴木:ヤフーがリモートワークに移行したことで、各メンバーが無理なく有志活動に参加できるようになりました。たとえば、コロナ禍前はセミナールームの準備やセッティングのための人手が必要でした。オンラインになってそれらが不要になったことで「こういうセミナーをやろうと思っているけど、どう思う?」という相談など、工数的な負担は軽いけれど、有志メンバーが持っている経験や知見の価値を生かしやすくなったと思います。 |
| 2021年 | ヤフーのダイバーシティ&インクルージョン推進体制がUPDATE 女性の健康検定オンライン受検を開始 |
| 2022年 | ヤフーの常務執行役員以上全員が女性の健康検定を受検 |
※4 ダイバーシティスポンサーシップ制度:
ヤフーのダイバーシティを推進し、働きやすい社内風土を醸成するため、有志を中心とした社内プロジェクトを執行役員がサポートしている