ヤフーでは、2022年4月からの新施策として、新入社員を含む全社員が各サービスに対して品質改善およびイノベーションにつなげる提案を行う「サービスななめ会議」を実施しています。
今回は、この「サービスななめ会議」の原点になっている「ななめ会議」について、ファシリテーションとフィードバックのコツを聞きました。
- 目次:
- ななめ会議とは?
- ななめ会議の進め方
- なぜ? ななめ会議なのか?
- フィードバックをうけるマインドセット 目的を意識することが大事
- 価値のあるフィードバックの仕方
- ファシリテーターに求められるのものは?
- ななめ会議の導入で変化したヤフー
ななめ会議とは?
「ななめ会議」とは、上司と部下の相互理解を促進する組織開発の手法の1つである「アシミレーション(assimilation)」が元になっています。それをヤフーでは「ななめ会議」と名付けて組織開発に活用しています。
「ななめ会議」は会議手法のひとつでもあり、管理職とチーム内の相互理解を深めたり、管理職自身の行動変容や成長を促したりする仕組みです。
また、「ななめ会議」はどちらかというと管理職にフォーカスしたものです。チームメンバーにフォーカスしたものでは「1on1」という上司が部下の話を聞く施策があります。この2つの施策で、より相互理解を促進すると考えています。

2005年ヤフー中途入社。2012年の経営刷新に伴い事業部門から人事に異動し、HRビジネスパートナーを経て、現在は人財開発領域にて主に管理職育成を担当。
ななめ会議の進め方
- 上司とファシリテーターと参加者がテーブルを囲む
- 上司が会議の趣旨を説明「私のためにフィードバックをお願いします」と伝えて席を外す
- ファシリテーターが参加者に、対象者について「知っていること」、「続けてほしいこと」、「やめてほしいこと」、「やってほしいこと」の4つの質問を行う
- 参加者はそれぞれの質問に意見を出していく
- 意見が出そろったら、上司にフィードバックする内容を決める
- ファシリテーターが上司にフィードバック内容を伝える
- 上司がフィードバックされた内容に向き合い考えや行動を改善していく

なぜ? ななめ会議なのか?
たとえば、参加者にとって上司やプロジェクトリーダーのような、評価者にあたる人物が会議をリードするとコミュニケーションの線は上から下、下から上という縦ラインになります。「ななめ会議」は上司に対するフィードバックを行う会議なので、その場に上司がいてはいけません。そのため、上司の代わりとなる隣のチームのリーダー、つまり「ななめの関係」にあたる人がその会議のファシリテーションを担当することから「ななめ会議」という名前になったと言われています。
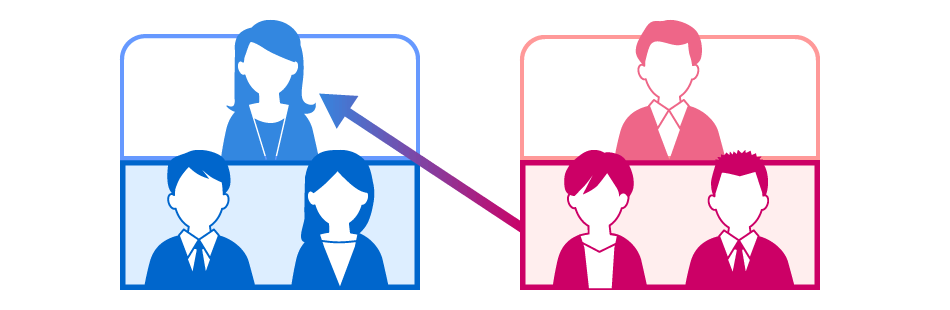
ファシリテーターは誰が適切か?
隣のチームの管理職は、その組織全体でやっていること、フィードバックの対象となる上司のパーソナリティーもある程度知っていることが多いと思います。そのため、そのような人がファシリテーションを行うことで参加者の発言のハードルが下がるというメリットがあると考えています。
ヤフーの場合、必ずしも隣のリーダーがやるのではなく、部門付の人事担当者がファシリテーションを担当することも多いです。部門の人事担当者は、その組織が何をやっているか知っていますし、メンバーがどういう人たちなのかもある程度知っています。その上でファシリテーションができるので、先ほど言った隣のリーダーのような役割を兼ねられているのではないかと思います。

2008年ヤフー中途入社。2013年より人事として組織開発、人財開発に従事。現在はテクノロジーおよびコーポレート組織のHRビジネスパートナーを担当。
意見が出にくい、2つのチーム状態

ななめ会議を効果的なものにするには、会議を進行するファシリテーションが重要です。まず大事なポイントは、「ななめ会議」を行うチーム自体がどういうフェーズのチームなのかによって、ファシリテーションの仕方が異なるということです。
たとえば、発言がでてこないチームは2つ軸があります。
ひとつは上司との信頼関係がまだそこまで築けておらず、意見を言いにくい状態のチーム。
もうひとつは、上司に対する意見は言えても、チーム内で「どこまで言っていいのか?」「誰が言うのか?」などとお互いをけん制し合ってしまうチーム。
このように、チームのメンバー同士が無理をせずに発言できる状態なのか、または、意見は出てきても大事なことには目をそむけている状態なのかなど、チームの状態によってファシリテーターがどう本音を引き出していくかが変わります。例えば、けん制し合っているチームの場合だと、チームの中で発言してくれそうな人を指名して回答しやすいことを誘導していくと発言が出やすくなります。

フィードバックをうけるマインドセット 目的を意識することが大事
「ななめ会議」は上司が自分のために、参加者の時間をつかってやってもらうもの。「ななめ会議」をどういう目的で行うのかを、上司も参加しているメンバーも理解していることが大事です。上司がフィードバックされた内容に納得しない時は、その手前の合意ができていない場合です。

上司自身が「ななめ会議」をやってほしいと考えているのであれば問題ないのですが、なかにはその上司の「上司」からの「ななめ会議」やってほしいという要望で行う場合もあります。
この場合は、なぜ、ななめ会議をやる必要があるかをきちんと伝え、上司本人が納得してから「ななめ会議」を行うことが大切です。
「ななめ会議」の目的は仲良くなることではない?
ななめ会議の本来の目的は、相互理解を図り目的を達成するためにチームのパフォーマンスを最大化すること。そのため、チームの目的意識、相互理解が足りないと、悪口の場になってしまいかねません。
普段から上司に対してある程度言いたいことを言えているチームであっても、今そこにある仕事上の課題を解決するために、言いにくいこともきちんと伝え合えないとしたら、いい関係のチームとはいえないと思います。
チームとしてのコミュニケーションは活発でも、本当に問題だと思っていることを言えない、話はしているが大事な話題から目をそむけているというケースも少なくないようです。

ただ、仲が良くて何でも話せるチームを目指さないといけない、というわけではありません。ななめ会議では特に、各メンバーの発言内容が、チームパフォーマンスを高める目的に向かっている必要があります。
そのチームの目的を達成するために個々の能力をより発揮していくことが大事なので、その目的意識さえ共有できていれば、必ずしも仲良くなる必要はありません。発言の内容を考える際に「上司という役割」という意識をチームが持つと、有意義な発言になっていくと思います。
価値のあるフィードバックの仕方
ななめ会議で出てきた意見をそのままフィードバックするというわけではありません。出てきた意見を正しくフィードバックできるかたちにみんなで話し合い、「何をどのように伝えるか」整えることも大事です。
また、「ななめ会議」で文句を言ってもよいのですが、そのとき大事なことは、その文句が上司にとって改善できる材料になっていることです。改善につなげることが難しい内容は、NGです。
たとえば、口下手な上司に、その苦手な部分のみを指摘しても、いきなりプレゼンがうまくなるわけではないですよね。「話すのが下手」ということだけ伝えても、本人が傷つくだけになってしまいます。この場合はたとえば、「もう少しだけ情報を足して話すことを意識してもらえるとより意図が伝わります」、というような、「提案型」のフィードバックを心がけましょう。
普段の業務では、メンバーからこのようなフィードバックはなかなか出てこないですし、自ら気づくことも難しいと思います。「ななめ会議」を行うことで、上司からもメンバーに対して「どうしてそのように行動していたのか」説明するきっかけを作ることができ、チームの相互理解が進むと思います。
「ななめ会議」の最後には、意見の中からどれを上司に伝えるか、どのような言葉で伝えるか話し合います。まず、どの意見を伝えるか議論する上で重要なのは、「何を伝えないか」を考えることです。一部の参加者しか言っていないことが全体の意見として伝わると誤解を生みますし、ひとつのアクションに対する評価や解釈はひとそれぞれのため、「何をつたえないか」を議論することはとても重要です。
次に、「どのような文言で伝えるか」を議論しましょう。フィードバックを受けた人が、次の具体的なアクションを思いつきそうか? などを確認しながら、参加者で意見をまとめていくことが、よいフィードバックをするためには必要です。
ファシリテーターに求められるのものは?
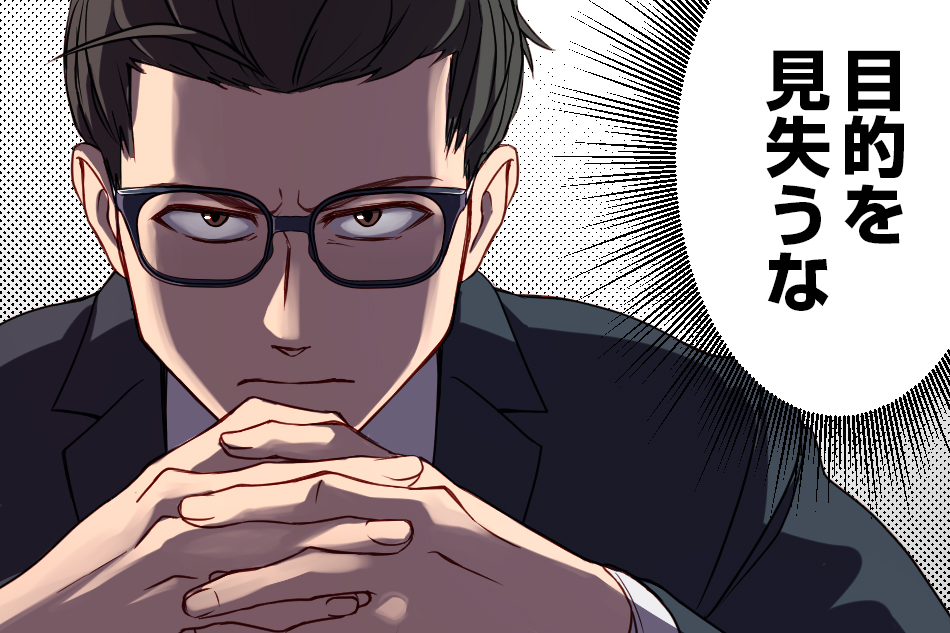
- チームビルディングという目的を理解する
- 行動変容につながるようにフィードバックを工夫する
- フィードバックでは「何を伝えないか?」も大切
上司やファシリテーターが、ななめ会議の目的を参加者にきちんと伝えることが大事です。
良くないやり方は、タスクの実行だけに注力した進め方です。
「時間が来たら次の質問へ」「15分たちましたので、次お願いします」というようにタスクを消化することが目的になってしまわないように気をつけましょう。
ななめ会議の導入で変化したヤフー
ななめ会議を導入した2012年以前のヤフーは 、メンバーから上司へのフィードバックの文化はあまりなかったと記憶しています。
2012年に社長に就任した宮坂学さん(現東京都副都知事)が、「いいことも悪いこともフィードバックし合えるような文化を作る」という指針を示しました。部下のために行うコミュニケーションである「1on1」が始まったのもちょうどそのタイミングです。
一人ひとりの中長期的な育成方針を話し合う人財開発会議ができた他、人の成長課題を本人にフィードバックする施策がいくつもスタートしました。その施策のひとつとして「ななめ会議」が導入されました。
導入されて10年ほど経つ施策なので、上司も部下からフィードバックされることに慣れています。むしろ、ななめ会議を待たずにどんどん言ってほしい、というように相互理解を図るようになっていると思います。
今年から全社員が、各サービスに対して品質改善およびイノベーションにつなげる提案を行う「サービスななめ会議」※1を実施しています。「ななめ会議」によってつくられた「フィードバック」の仕組みがなかったら、もしかしたら「サービスななめ会議」は生まれていなかったかもしれません。
オンラインが主のコミュニケーションになった今も、「ななめ会議」は部下が上司に言いにくいことを、第三者であるファシリテーターを通じて伝え相互理解を促進するツールになっていると思います。今回お伝えしたポントを確認しながら、いろいろな方に活用いただけたら幸いです。
※1 サービスななめ会議:
新入社員を含む全社員が、各サービスに対して品質改善およびイノベーションにつなげる提案を行う
