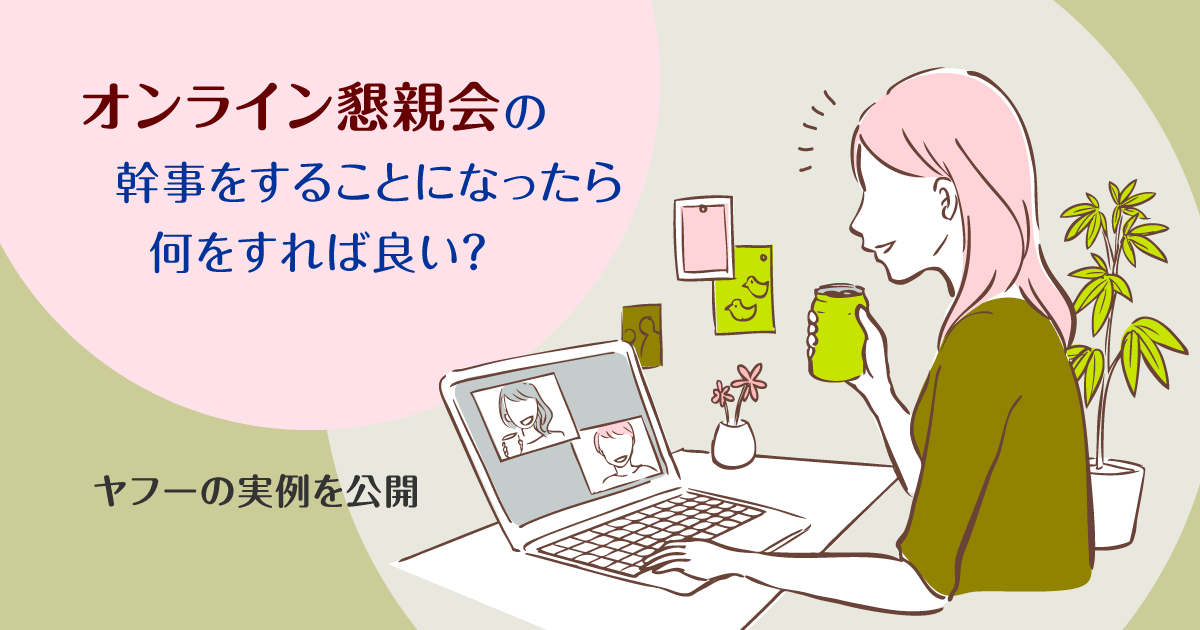ヤフーでは、コロナ禍が始まった2020年から、リモートワーク制度「どこでもオフィス」の利用回数制限が解除され、オンライン前提の働き方にアップデートしています。
リモートワーク中心の働き方により、社員間におけるコミュニケーションのメイン空間がオフィスからオンラインに切り替わった企業は少なくないでしょう。その一方で、リモートワークの課題とされているのが、社員同士のコミュニケーション不足ではないでしょうか。
ヤフーでは、2022年4月からコミュニケーション活性化を目的に、オンライン・オフライン問わず、社員間で行われる懇親会の飲食費用を補助する制度をトライアルでスタートし、毎月半数以上の社員が利用しています(※1)。歓送迎会や、チームメンバーでの気軽なランチミーティングのほか、業務で関わらないメンバー同士での懇親会にも利用されています。
今回は、この制度の利用者からはどんな声があるのか、また、オンラインで懇親会の、幹事や司会者は、どのような準備が必要なのかなどについて、制度を企画した人事担当者に聞きました。
※1:新型コロナウイルスの拡大状況を踏まえ、オンライン限定とする期間を設定するなど、臨機応変に対応しています。
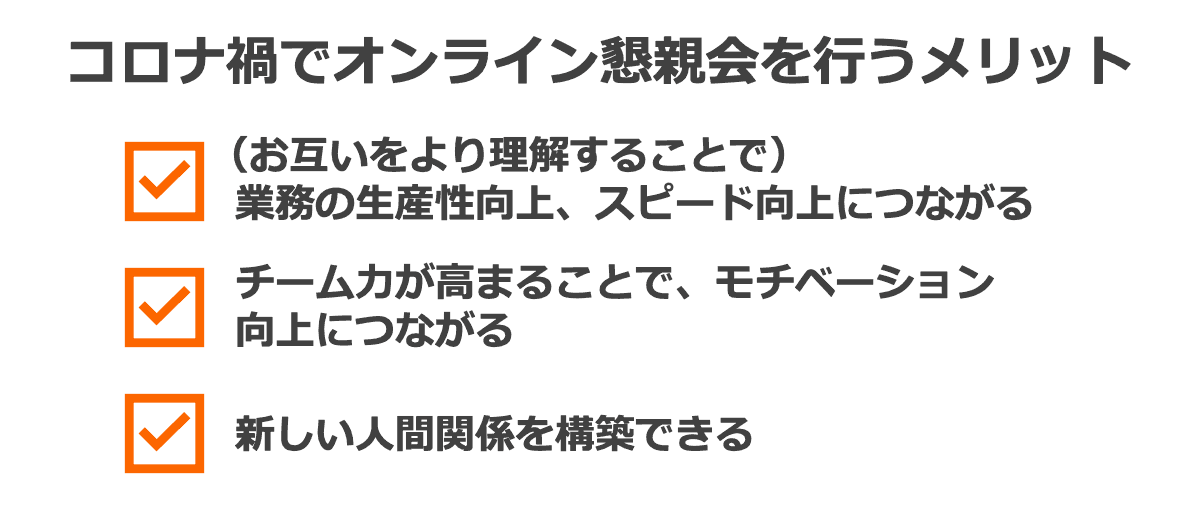
1. 懇親会とは
「懇親」には、「打ち解けて親交を深める」という意味があります。懇親会に参加した人々がお互いをよく知ることで、コミュニケーションをより円滑にでき、チーム力が高まり、業務の生産性やスピードが向上することも。
特にコロナ禍以降、リモートワークが前提になった企業では、自分が所属するチーム以外の人とは接点を持つ機会を作りづらい状況もあるかもしれません。そのような状況下でも、懇親会を通じて、新しい人間関係を構築するきっかけにできるというメリットもあります。
ヤフーでは、懇親会費補助の制度を使って、気軽なランチミーティングやランチ懇親会などを開催しています。その他にも決起会や打ち上げ、歓送迎会や新年会などのイベントでもこの制度が利用されています。
当日のプログラムとしては、
・コンテンツの説明
・開会の言葉
・乾杯のあいさつ
・食事や歓談
・閉会の言葉
という流れが一般的です。このほか、クイズやゲーム、歓送迎会のコンテンツなどが加わることもあります。基本的に、手軽に実施できて、盛り上がるコンテンツが採用される傾向にあるようです。今回は、ヤフーでよく実施されているコンテンツもご紹介します。
懇親会の目的を達成できることが理想なので、たとえば、歓送迎会では、歓迎される方や送別される方が主役。たとえば、その方たちをよく知ることができるクイズを行うと、その後の会話のきっかけ作りにもつながります。
今後、年度末に向けて、送別会のシーズンもやってきます。それ以外にも、会社はもちろん、学校、地域など、さまざまなコミュニティーでオンライン懇親会のニーズは増えると思います。今回ご紹介するヤフー社員のノウハウが参考になったらうれしいです。
目的・内容
- ランチ会:特に凝ったコンテンツは行わず、お昼の一時間程度で一緒にランチを食べる会
- 歓迎会:新しい仲間を歓迎する会
- 送別会:仲間の異動、退職などを送別する会
- 決起会:新規プロジェクトなどを立ち上げた際に、成功に向けてメンバー同士が気持ちを高めあうための会
- 慰労会・打ち上げ:プロジェクトなどの取り組みを振り返り、成果や苦労をねぎらうための会
- 新年会:年の始まりを祝い、お互いにあいさつを行う会
- 忘年会:年末に、一年を振り返り、その年の苦労を忘れるために開かれる会
2. ヤフーで行われている懇親会
- 定例ランチミーティング
→関係性が深まったため、業務において、以前と比べて発言しやすい関係性になった。
→コミュニケーションを通して、働き方、価値観あるいは、プライベートで大切にしていることなど、相手への理解が深まった。結果、仕事が円滑に進むといった、仕事面へのポジティブな変化があった。 - チームメンバーで会う機会として活用
→1カ月ごとの区切り、振り返りの機会としての効果があった。また、チームに一体感が出てモチベーション向上につながっていると感じる。
→プライベートの顔を知ることで関係性が深まり、「ちょっとした相談」や「ちょっとした質問」がしやすくなった。業務の生産性やスピードの向上につながっていると感じる(逆に懇親会に参加しないと、逆の傾向にあるように思う) - リモートでのランチ懇親会
→コロナ禍での中途入社ということもあったが、顔をあわせて仕事をする機会などがない中で、関係性の構築の助けになった。
→同じチームだが、接点があまりなく、対面でもあったことがない人と仲良くなり、業務においても相談しやすくなった。
- 在宅勤務になって少し疎遠になっていた元同僚との懇親会
→また身近に感じられるようになった。 - 短期プロジェクトのお疲れさま会
→普段業務で関わらない職種の方とも交流でき、人となりを知ることができた。 - パパママ社員のつながりで実施
→日頃の子育ての悩み、受験情報の共有、励ましなどを受けて、プライベートにも良い影響があった。
3. オンライン懇親会の幹事をすることになったら何をすれば良いのでしょうか?
オンライン懇親会の幹事になったら、まずは何をすればいいのでしょうか? 事前に準備すべきこと、当日に司会者と一緒にすり合わせて工夫したいポイントなどを参考にしながら組み立ててみてください。
- 懇親の場のため、なるべくビデオオンで参加してほしいと伝える
- オンライン会議システム(ZoomやMicrosoft Teams、Google Meetなど)の共通の壁紙を配布して設定しておいてもらう(花見シーズンなら桜、忘年会なら居酒屋、開放感を味わいたいならビーチなど)
- 当日の会の目的を決める(入社者や異動者の歓送迎会、慰労会など)
- ファシリテーター(司会者)を決めておく
- (食事がある場合)冒頭でご飯をあたためる時間を5分くらい取る(「あたため時間」のスライドも用意)
- 乾杯の様子を写真撮影(キャプチャー)する
- 注文したメニューを報告しあってアイスブレーク
- 離席するときは名前を編集して分かるようにする (例:矢風太郎@飲み物補充中)
- (場合によっては)家族の参加も歓迎する
- 特に人数が多い場合は個別の部屋(ブレイクアウトルームなど)で会話する
- 終了時間を決めておき、引き続き参加する人も随時抜けてよい旨を伝えておく
- 最後の締めのあいさつをルーレットで決定する
- 共通テンプレートの自己紹介
事前に記載してもらう(写真などもOK)と、個別の部屋(ブレイクアウトルームなど)での会話のきっかけ作りになる - 謎解きゲーム
個別の部屋(ブレイクアウトルームなど)で答えを出し合い、最後に全員で答え合わせをする - クイズ大会
一般的なクイズや、新メンバーが組織などに加わったタイミングでは、そのメンバーに関するクイズを実施する - 「ジャスト・ワン」
参加者みんなが力を合わせて遊ぶ協力型の連想系のワードゲーム - お描きクイズ大会や絵しりとり
オンラインホワイトボード・Miroなどを活用 - イントロクイズ
早押し曲あてクイズ - ビンゴ大会
各自でマスに好きなことを書いて、シャッフルトーク。合致したものに丸付けなどの工夫も
懇親会の最後に記念写真を撮影して参加者にシェアしても良いかもしれません。
また、オンライン懇親会に参加したときは、終了後には幹事に感謝の気持ちを伝えたいですね。
4. ヤフーの懇親会費補助企画のきっかけ

- 松井 あずさ
- 2021年ヤフー入社。PD統括本部PD本部人事企画部組織開発チームに所属。懇親会費や合宿費施策の企画、運営を担当している。
松井:
私は普段、人事企画部で働き方に関する施策や制度設計を行っています。新しい働き方になってからは、会社としてのコミュニケーションの促進を重視しています。
定期的にコミュニケーション状況の調査も行っていますが、コロナ禍以降は約93%の社員がリモートワークで働いていて、約半数の社員がコミュニケーションにおいて何かしら課題を感じているという結果が出ました。そういったアンケート結果を分析して課題を解決するために、懇親会費補助の施策を企画しました。
その後のアンケート結果では、制度ができてから半年が経過した時点で過半数の社員が懇親会費を一回以上利用していることがわかりました。「懇親会費の制度がコミュニケーションを円滑にする施策として有効か」という質問に対して、大半がポジティブな回答でした。
継続的に、かつ、全社横断で使われていて、新しい出会いが生まれていることも特徴ですね。引き続き、パフォーマンスが発揮できる場所や環境を選べる働き方を推進しながら、コミュニケーションの課題を解決する施策を考えていきたいと思います。
5. ヤフーのコミュニケーション促進の制度・取り組みについて
ヤフーでは前述の通り、コミュニケーション不足の課題に対する解決策の一つとして、社員間で行われる懇親会の飲食費用を補助する「懇親会費補助」を毎月支給していて、半数以上の社員が利用しています。
ほかにも「合宿費補助」の制度があり、こちらは組織での重要アジェンダの議論や、業務を通じた関係構築など、長時間のオフライン議論、普段とは異なる外部施設などでのミーティングが効果的だと判断される場面をサポートする費用です。
さらに、働く場所の選択肢の一つであるオフィスをニューノーマル時代の働き方に最適化する「実験オフィス」や、上司と部下が週に1回面談をする「1on1ミーティング」、リモートワーク環境でも社食の味を楽しめる「オンライン懇親会セット」などさまざまな取り組みを行っています。