5年前、東日本大震災は東京のヤフー本社にも影響を及ぼしました。
震災直後は交通事情も不安定だったため、出社が困難な社員は無理に出社せず、自宅から社内のネットワークにつないで業務を行いました。震災直後は、社員がほとんどいないフロアもありました。
2014年にできた「どこでもオフィス」制度で、現在は全社員が自宅以外の場所でも仕事ができるようになっています。ですが、震災当時は社外から社内環境につないで業務を行うことができるのはYahoo!ニュースの編集メンバーやエンジニアなどの一部の社員だけで、基本的に社員は会社に行かないと仕事ができませんでした。
そんな中「震災直後の今、全社員が自宅からでも業務をできるようにしなければ!」という強い思いで、全社員が自宅から社内にアクセスできる環境を1日で整えたのがインフラチームのみなさんです。今回は、当時のメンバーだった西村さん、嶋さん、小西さんにお話を聞きました。
- 5年前の3月11日、震災発生直後にどんな対応をしましたか?
西村:
まず普段から行っている「死活監視」(※1)で、地震の影響で落ちたところがないかを確認しました。
(※1)死活監視:
コンピューターやシステムが動作しているかどうかを継続的に監視すること。
嶋:
インフラチームは、社内のネットワークに異常がないかどうか常に死活監視をしています。震災直後は、仙台営業所が停電の影響でつながらなくなっていました。
- その後すぐに、社員たちの自宅から会社のネットワークにつなげるようにしようと思ったのですか?
嶋:
震災が発生したのが金曜日で、翌週の月曜日は通常通り出社しました。ですが、上長が交通機関の混乱の影響で出社できなかったんです。
上長と「会社に行けない人も多い。こういう時は、外から会社につなげる手段が必要なんじゃないでしょうか」とやりとりしたことを覚えています。
当時の本部長に提案したところ「(会社につなぐことを)やりたいならやればいい。やれるの?」と聞かれたので「やれます」と答えました。

(嶋さん)
以前働いていた会社で同じような対応をしたことがあったので、メンバーに「絶対できるからやってほしい」と伝えたんです。
でも、ヤフーの場合社員数の方がかなり多かったですし、設計もせずにいきなり実装したので大変だったと思います。小西さんは、深夜に大手町のデータセンターに行って、サーバーを冷やすための空調がゴーゴー吹く中対応していましたよね。
小西:
そうですね……寒かったです。

(小西さん)
- 全社員が社内ネットワークにつなげるようにすることへの不安はありませんでしたか?
嶋:
不安はもちろんありました。
全社員が社内のネットワークにつなぐ方法として、西村さんが考えたネットワーク機器を使った方法と、小西さんが考えたWindowsサーバーを使った方法の2つを考えていました。
その2つを同時並行で試して、どちらが現実的なのかを検討しましたが、どちらも確実に実装が可能なのかという不安がまずありました。それまで、何千人もの社員が一度に社外から社内につないだことはなかったので、キャパシティの問題も心配でしたね。
検討の結果、Windowsのユーザーパスワードで認証する方法を選択したのですが、セキュリティ的には弱いため開放してしまって本当に大丈夫なのだろうか? という不安もありました。
でも、上長にそれらのリスクもすべて説明した上で確認したところ「非常時だからやっていい」と。
社員のみなさんが外からつなげるように準備できたのが、3月15日の朝3時ごろだったと思います。15日の午前中には社内イントラページの担当者にお願いして、自宅から社内につなげられるようになったことを全社員に伝えてもらうことができました。
小西:
この時の仕組みは、3月14日に作り方を調べて1日で作ったものだったので、何も問題なく使ってもらえるのだろうか? という不安があったのですが、社内につながりにくいという声はほとんどなかったので、ほっとしました。
- 実際に使った社員からの反応はいかがでしたか?
嶋:
みなさんから「家でも仕事ができて助かった」と言ってもらえた時はとてもうれしかったですね。
西村:
この時、自宅のパソコンから社内に接続するために必要なのはWindowsのパスワードの入力だけでした。ソフトをインストールする必要もなかったので、みなさんにスムーズに使ってもらえたのではないかと思います。
- 震災後、状況が落ち着いてから対応したことはありますか?
嶋:
また何か災害が起きて社員が出社できなくなった時には、すぐに外からつながる環境を復活できるようにしました。
西村:
もし、東京で外からつながる環境の復活ができない状況になっても大丈夫なよう、名古屋オフィスからもオペレートできるようにしておきました。また、震災が起きるまでは大手町を通じてインターネットにつながっていたのを、地方拠点からもつながる構成に変えました。
3.11で「東京が落ちる可能性はある」と実感した
- この時の体験は、みなさんのお仕事にどんな影響を与えましたか?
嶋:
何か開発する時には必ず、BCP(※2)を考えるのが基本になりました。
これまでももちろん考えてはいたのですが、どこかで「まさか東京(のシステム)が落ちることはないだろう」と思っていたんです。でも「東京が落ちる」可能性は本当にあるんだと考えるようになりました。
(※2)BCP:
Business Continuity Planの略。災害や事故で被害を受けた場合でも、主要なサービスの継続利用、早期復旧を可能にするための計画の策定
小西:
そうですね、私も必ずDR(ディザスタリカバリ)(※3)を考えます。「東京のシステムが死んだ時にどうするか」と。
(※3)DR(ディザスタリカバリ):
自然災害などで被害を受け、主要なITシステム拠点での業務の続行が不可能になった際に、緊急の代替拠点として使用する施設や設備のこと。また、自然災害などで被害を受けたシステムを復旧・修復すること。
西村:
震災直後に設計した内容の構築を、5年たった今でも続けています。
最終的に目指しているのは「完全冗長化」。たとえ東京の大手町が死んでも、ヤフーの社内サービスが問題なく提供できることです。
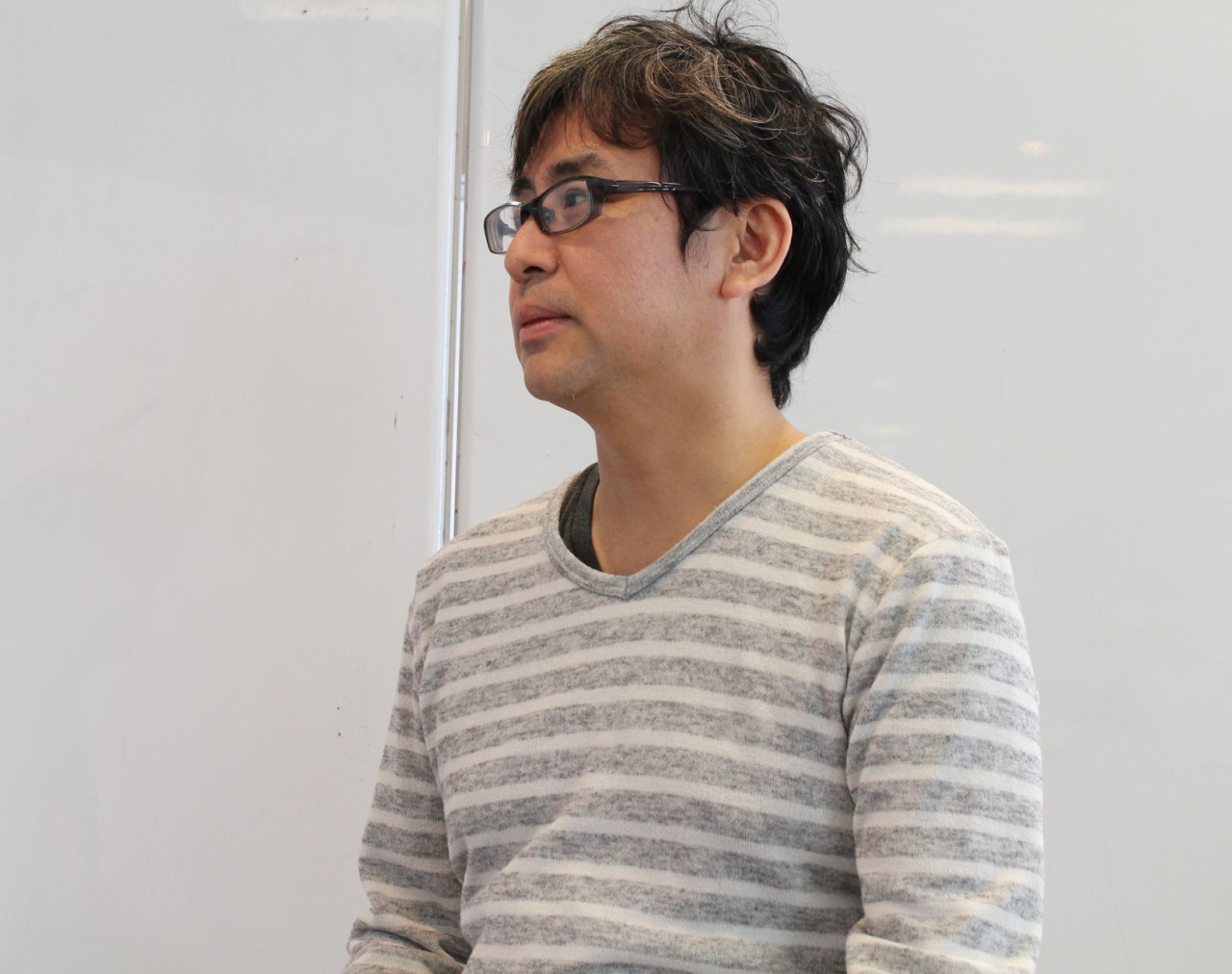
(西村さん)
- インフラエンジニアとしてのやりがいは何ですか?
西村:
社内のインフラはライフラインであり、動いて当たり前です。
ヤフーのサービスがちゃんと動くためのベース、下支えの所に関わることができているというところでしょうか。
小西:
私たちが作ったものを使って、みなさんが当たり前に業務ができたり、業務しやすい環境になっている、と感じられるととてもうれしいです。
「ヤフーの社員が満足してくれるために動きたい」という思いが強いです。

- そして、2014年に「どこでもオフィス」(※4)が始まりました。どのような思いでしたか?
(※4)どこでもオフィス:
月2回、貸与されているノートパソコンやiPhoneなどを使って、連絡がつくなら出社せず好きな場所で仕事ができる制度。 通称「どオフ」。
西村:
この制度ができたことで、本当に「どこでも」仕事ができるようになりました。セキュリティ上の不安も減らした上で、とても簡単に接続できる仕組みを作ることができたのではないかと思っています。
今後、もしまた災害が起きて、全社員が出社できなくなっても全員が「どこでもオフィス」を使って仕事ができるような環境にしておきたいですね。
小西:
場所を選ばずに仕事できるようになったことで、社員の働き方や考え方が変わったのではと思っています。
例えば、これまでは出社しないとメンバーからの申請を承認できませんでしたが、「どこでもオフィス」ができたことで「承認ボタンは後で押せるから、会社にいる時はメンバーと話したり他にやるべきことに集中しよう」と思えたり。
社員みんなが、それぞれにとって効率のいい働き方を選べるようになったのではないでしょうか。
嶋:
「どこでもオフィス」を始める前には、パソコンをもし電車に置き忘れたら……とか、後ろから見られたらどうなる? など、考えられる限りのネガティブなことは、ひととおり考えつくしてはいたのですが……それでも心配が完全にはなくなることはありませんでしたね。
でも「どこでもオフィスができるようになって助かっている」と言ってもらえるだけで、今でも本当にうれしいです。
「非常事態だからこそやってみよう」震災をきっかけにドアが開いた
- 最後に、これから挑戦したいことを教えてください!
小西:
「どこでもオフィス」は、まだセキュリティ的には不安な部分があります。どこででも仕事はできる便利さはそのままに、もっとデータを安全に担保できる環境を作れると思っています。
今は、VDI(デスクトップ仮想化)(※5)という、リモート環境でもデスクトップ環境を使える仕組みを担当しています。例えばこの仕組みを使って、貸与されたパソコン以外の端末からもまったく同じようにセキュリティが担保された環境につなぐことができると、もっと「どこでもオフィス」は便利に、自由になるのではないかと思っています。
「どこでもオフィス」の質を高めて、もっと安全に便利に使ってもらいたいです。
(※5)VDI(デスクトップ仮想化):
デスクトップ環境を仮想化してサーバー上に集約したもの。クライアント機からネットワークを通じてサーバー上の仮想マシンに接続し、デスクトップ画面を呼び出して操作できる。
西村:
私も、今以上に社員みんなが働く場所を選べるような環境作りを目指したいですね。

嶋:
「どこでもオフィス」は働き方の自由度を増やすという挑戦だったと思っています。
私は、インターネットは自由を与えてくれるものだと思っているので、インターネットで実現できる自由を今後も追求し続けたいです。
それまでセキュリティなどの問題もあって開けることができなかったドアが5年前の大震災の時に 「非常事態だからこそやってみよう」と一度開いたことで、社員が社外からでも仕事ができるようになりました。
そして、一度ドアの外に出てみたら、どこにいても仕事ができたらすごく便利だし、やっぱりドアを開けないとダメだとわかったんです。
あの時は、セキュリティの不安以上に大切なものがあったような気がします。だからこそ、それまでできなかったことをやってみることができたし、やってみたからこそ得られた変化が「どこでもオフィス」という働き方につながったのではないでしょうか。
ーーーーーーーーーー
制度ができてから、社員はそれぞれ、自宅やカフェ、他の会社、時には旅行先など、さまざまな場所で「どこでもオフィス」をしています。また、台風や大雪などの影響で出社が困難な際にも自宅で業務できることで、より効率的な働き方ができるようになりました。
・「どこでもオフィス」という働き方
・「どこでもオフィス」「フレックス」制度の上手な使い方




【関連リンク】
・【3.11から5年 〈1〉】 CM放送中「防災を生活の一部に」 Yahoo! JAPANアプリの災害通知機能
・【3.11から5年 〈2〉】 東北・石巻の支社社員に聞く、現地からみた被災地の「いま」と「これから」
・「北九州、どう?」の一言で転勤中 入社3年目の若手社員を紹介
・特集 3.11を機に問い直す、ヤフーのBCPとは?(ヤフーのCSR)
