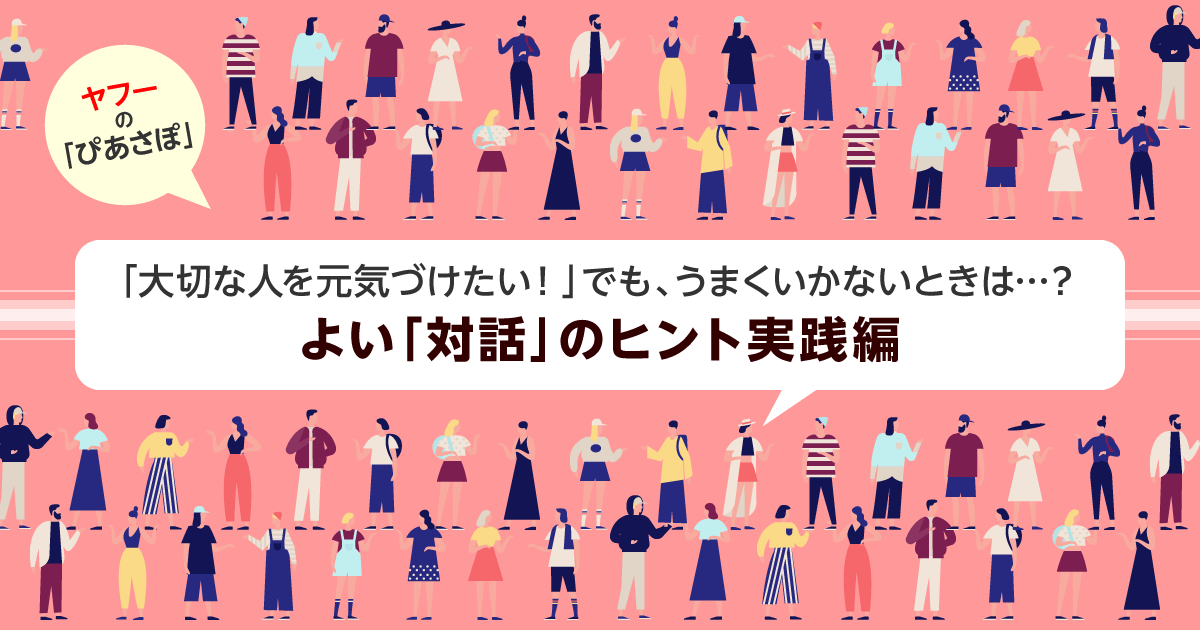この連載では、産業カウンセラーやキャリアコンサルタントの有資格社員で活動している「YJぴあさぽ(※1)」が、よい「対話」のヒントをお伝えしています。
※1 YJぴあさぽ:
同僚を「ピア=仲間」ととらえ、キャリアや人間関係などに関する対話をすることで応援しています。
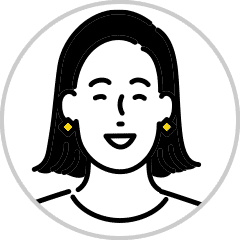
- みーさん
-
グッドコンディション推進室で従業員の健康増進企画を担当。夫と高校生の娘の3人暮らし。
保有資格:産業カウンセラー(JAICO)、交流分析士インストラクター、国家資格公認心理師
今回は、少し元気がない友人の話を「聴き」、元気になってもらいたいと思っているA子さんの悩みをもとに、「大切な人との対話のヒント」をお伝えします。
- 目次:
- 元気づけることは、誰にとっての「ゴール」?
- 果たして、気持ちが落ち込んでいることは悪いことなのか
- 元気がない大切な人に、何もできないときはどうしたらいい?
- 誰かを元気づけたいと思ったら、「私」のケアも忘れずに

A子さんのお悩み:
「傾聴が大切ということを理解したので、落ち込んでいる友人の話をとにかく聴いてみたのですが…、結局元気づけることができませんでした…。」
落ち込んでいるときに元気になってほしいと思い、話を聴いてくれる友人がいたらとても心強いですよね。
A子さんもきっと、そんな存在になりたいと思い、話を聴いたのだと思います。でも、元気づけることができなかったこと、みなさんにもあるのではないでしょうか?
子どもや親、パートナー、同僚との関係において、相手を励まそうとしたり、逆に励まされる側になったりしたこともあると思います。
もし、Aさんからこんな悩みを相談されたら、私だったらこんな風にアプローチするかなということを、いくつか整理してみます。
元気づけることは、誰にとっての「ゴール」?
大切な人が落ち込んでいるときに元気づけたい、元気でいてほしいと思うのは、とても自然だと思います。
でも、その気持ちの持ち主は誰なのでしょうか?
それは「私」です。そのため、「相手を元気づけたい」というのは「私欲」とも言えます。
それがいけないということではなく、そのことに気がついておくことが大切です。
大切な人が落ち込んでいたら、「私」がそれを見ているのもつらいということもあります。
そして、なかなか元気になってくれなかったら、どこかもどかしい気持ちになったり、「私だったらとっくに元気になるのに…」などと自分とつい比べてしまったりすることもあるかもしれません。
これはすべて「私」が感じていることです。
このように、主語を意識すると責任の所在がわかります。
「大切な人」が落ち込んでいるときに、傾聴や励まし、寄り添うなど、いろいろな支援の形がありますが、それはあくまで「支援」です。
「友人」の落ち込みはあくまで「友人」のもの。支援を受けて、落ち込み続けるか前向きになるかは「友人」自身が決めることという尊重の気持ちをもつことが大切です。
どんなに努力しても「私」以外の人を引き受けることはできないし、元気づけられると思うことは、少し傲慢(ごうまん)なことかもしれない、という理解があるといいと思います。
果たして、気持ちが落ち込んでいることは悪いことなのか
そして、元気でいるべき、落ち込みからはなるべく早く回復すべき、そんな思い込みについてはどうでしょうか。
もちろん、その人が落ち込んでいると周囲が感じるときは、表情が暗かったり、外出の頻度が減っていたり、観察可能な変化や予兆があるから。それらが長期的に続くことが精神的、肉体的にも影響を及ぼすことが心配になりますよね。
気づいて気にかけることはよいことだと思います。ですが、もしかしたらそのような状態になることが、その人にとってはある意味、必要という面もあるのではと思います。
動物は、傷を負ったら回復のために身を隠す行動をしますが、人間がそうなることもあります。そう思えば、「落ち込んでいる」という、もしかしたら傷を負ってしまって回復に向かっている途中の人にしてあげられることは、励まして急いで元気にすることではなく、その人が安心して過ごせる「隠れ家」のような存在になってあげることかもしれません。
身近で大切な人であればあるほど、ただ見守り寄り添うのは難しく、ついあれこれアプローチしたくなりますが、相手が過ごしやすい環境を整えてあげることも、ストローク(※存在認知の1単位)です。
対話や傾聴が必要な状況ではない可能性も考えて、できることを考えてみましょう。もしかしたら、なにもせずそっとしておくのもひとつかもしれません。
様子がわからないことが心配だったら、「せめて(メッセージに)既読だけでもつけてね」などと伝えておき、つながりが断たれないよう定期的に連絡することを決めておくと、安心できるかもしれませんね。

元気がない大切な人に、何もできないときはどうしたらいい?
そうは言っても、大切な人に元気になってほしいのに、何もできないのはつらいですよね…。
そんなときは、「何もしないことが今の私の役割でミッション。今は出番を待っている」と認識してみてはいかがでしょうか。必要なときがきたら支援できる準備を整えておくような気持ちでいるとよいかもしれません。
このように、その人のことを大事に思う気持ちを持ち続け「待機」するために良い方法は、相手のことを思い出して、「元気になってほしいな」と願うこと。直接相手にアプローチしなくても「思いやる」ことはできます。なにもできないと感じたときにおすすめの方法です。

誰かを元気づけたいと思ったら、「私」のケアも忘れずに
今回のA子さんのように、
「落ち込んでいる友人の話をとにかく一生懸命に聴いたのですが、結局元気づけることができなくて…自分にはもう無理(元気づけられないかもしれない)」
と思っている「私」のこともケアすることが大事です。
応急手当の原則でもそうですが、けがしている人を見かけたら、まずはまわりの安全を確認します。あわてて駆け寄って、自分もけがしてしまったら助けようがありません。
自分が人を助けられる安全な状態にあることが大事だということは、話を聴く場面でも同じです。誰かのことを元気づけたいと思ったときは、「私」のケアも大事だということを覚えておいてください。
また、話を聴いた結果、「私」がダメージを受けてしまう可能性もあります。話の内容からダメージを受ける場合もありますし、話を聴いた結果、相手との間に起こったことで受ける場合もあります。
先ほども書きましたが、責任の所在を混在しないことが大切です。「私」がケアを必要としているかどうか、どんなケアが必要かも意識できるといいと思います。
自分が十分にケアされていれば、大事な人をケアすることが、よりできるようになるかもしれません。
ここまで、A子さんのお悩みに4つのポイントでアプローチしてみましたが、いかがでしょうか。皆さんの思い浮かぶケースで、何か参考になることがあればうれしいです。
対話による実践編と言いつつ、今回はあまり対話そのものが出てきていないですね。
でも、元気づけることができなくてつらい、と感じる背景をいろいろ想像しながら書いてみました。こんな風に、いろいろな「かもしれない」が増えていくことも、対話的アプローチだと思っています。
この連載では、これからもお悩み相談などの実践編で、いろいろなケースを考えてみたいと思います。
最後まで読んでいただきありがとうございました。