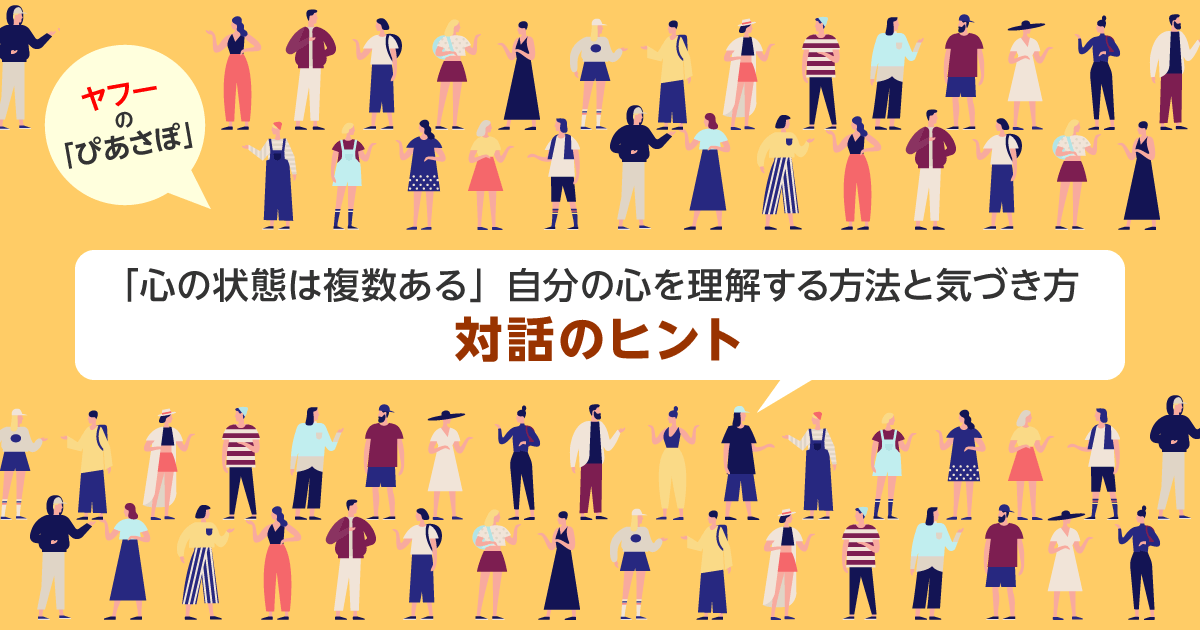この連載では、産業カウンセラーやキャリアコンサルタントの有資格社員で活動している「YJぴあさぽ(※1)」が、よい「対話」のヒント、実際の2on1やオープンダイアローグから、みなさんのコミュニケーションに役立てていただけそうなことをお伝えしています。
※1 YJぴあさぽ:
同僚を「ピア=仲間」ととらえ、キャリアや人間関係などに関する対話をすることで応援しています。具体的には、定期的に「オープンダイアローグ(※2)」と「2on1」を実施しています。
※2 オープンダイアローグ:
フィンランドで開発された精神科医療の包括的なアプローチで「開かれた対話」と訳されます。YJぴあさぽでは、話すこと、そして聴くこと、「対話」を大事にしたいという思いから、対話の場を「オープンダイアローグ」と呼んでいます。
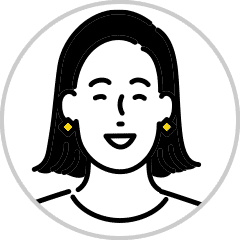
- みーさん
-
グッドコンディション推進室で従業員の健康増進企画を担当。夫と高校生の娘の三人暮らし。
保有資格:産業カウンセラー(JAICO)、交流分析士インストラクター、国家資格公認心理師
「心の状態は複数ある」と考えてみる
先日、健康診断で人生初の胃カメラを経験しました。受けたいと思っていたものの、これまで周囲の胃カメラを受けた人からは「相当苦しい」と聞いていたので、なかなかチャレンジできずにいました。
そんなとき、オフィス近くのクリニックでは鼻からカメラをいれる胃カメラであること、そしてとても上手な医師が担当されることと聞いて思い切って「バリウム検査」ではなく胃カメラを予約しました。
ですが…人生初の胃カメラは、とても苦しかったです…。
周囲の人が言っていた「(胃カメラは)口からよりは鼻からは楽」というのは、口からがよほど苦しいからそれよりは楽、ということでした。
とはいえ、鼻からちょっと血が出たくらいで、私の初めての胃カメラは無事に終了しました。(上手なお医者さんだったのは間違いないようです)
ただ…私の心は、「無事」ではありませんでした。
「これが胃カメラの通常運転なのか」という学びと理解とは別のところで、「ひどいことをされた!」と心がすっかり傷ついてしまったのです。
次の日はお休みだったこともあり、心の傷を癒やすために、ちょっとゆっくり過ごすことにしました。
いい大人が、と思われるかもしれませんが、心というのは理屈が通じないところがあるので、理屈を優先せずに心と理性の信頼関係を回復しなければなりません。
「胃カメラくらいで情けないな」「痛みに弱すぎる」など、ただでさえ傷ついた自分の心に自分で塩を塗るようなことをしてしまうと、余計に回復は遅くなります。
たとえるなら、ペットの犬を予防注射にだまし討ちで連れていったら、しばらく飼い主との信頼関係が戻らないような感じです。健康のために受けさせた予防接種ですが、怖がる時間を減らすためにだまし討ちで連れて行ったことで犬の心は裏切りと注射のショックで傷ついてしまうことがあります。そんなときは、「ごめんね、よしよし、もう嫌なことはしばらくないよ」と、犬の心を回復させることに専念すると良いのと同じで、自分の傷ついた心もしっかり回復させることが大切です。

「心は一つだけで、いつも同じように感じて考えて行動している」と思ってしまうと、理解しづらいことがあります。「心の状態は複数ある」と考えると、自分の状態を理解したり適切に対応したりするためのヒントになるかもしれません。
人と人との関係や交流に着目した、交流分析(※3)という心理学では、この「複数の心の状態」を「自我状態」という概念で説明しています。
※3 交流分析:
1950年代半ば、アメリカの精神科医エリック・バーンによって開発された心理学。自分と他人との関係に着目することで、人間関係の改善や自律的な生き方や自己実現に役立つと考えられている。
対人関係の改善や、自己理解を助けるさまざまな理論があり、自我状態はその一つ。
心には、3つの自我状態がある
交流分析でいう「自我状態」とは、そのときの思考・感情・行動の基になっている心の状態をいいます。心の状態は一つではなく、心の様態によって、思考・感情・行動は、3つの別人のように変わるという考え方です。
精神科医であったエリック・バーンは、自分の患者が時々別人のように変わることに興味をもち、表情・態度・言語といった観察可能なデータから、3つの「自我状態」という発想に到達しました。
心を構成する3つの自我状態は、成長の過程で形作られます。
親の自我状態(Parent)(ペアレント)
・過去の成長過程で、自分の親など身近な養育者や大人から取り入れたように、思考・感情・行動する自我状態
・子どものときに経験した、子どもからみた大人像をコピーして思考・感情・行動する
成人の自我状態(Adult)(アダルト)
今この場の状況に応じて、理性的に思考・感情・行動する自我状態
子どもの自我状態(Child)(チャイルド)
過去の子どものころに体験したように、思考・感情・行動する自我状態

生まれたばかりの赤ちゃんの心は、大人(親)のような思考・感情・行動は存在せず、ごくごく未熟な、子どもの自我状態の原型だけをもって生まれます。
そこから、シャワーのように大人の思考・感情・行動に触れ外界の刺激やさまざまな知覚を経験しながら、大人(親)を模倣したり、自分なりに考え行動したりしながら、心の構成ができあがっていきます。そう考えると、心というのはその人が生きてきた歴史そのものとも言えますね。
そして大人になってからも、子どものときに経験した通りに反応する子どもの自我状態になるときもあれば、子供のときにインプットした親の自我状態になるときもあれば、今ここに対応する成人の自我状態になるときもあるのです。自分でも気づかずに、心の状態は揺れ動いているのです。
自我状態の働き方は、これまでの人生で出会った親や人々との関わりの経験を、自分がどう受け止めてきたのかに影響を受けるもので、それがその人の「個性」にもなります。兄弟が同じ親の元で似た経験をしたとしても、本人がそれをどう受け止めて取り入れたかによって、異なる個性を持つことになります。
自分の心の成り立ちを想像してみてください。親が繰り返し言い聞かせたことや、子どものころの感じ方が今につながっていること、それらを使いながら、今を生きていると考えると、心の取り扱い説明書になりそうだと思いませんか?
3つの自我状態
| Parent | Adult | Child | |
|---|---|---|---|
| 成立ち | 親や養育者から獲得 | 子どものころから現在までの実際の経験から獲得 成長を続ける |
子どものころの経験から獲得 |
| 特徴 | 断定的 常識や社会規範を守りたい 教育、養育、保護する 上から目線や子ども扱い |
理性的 目標達成や課題解決のために状況判断して行動したい 対等でありたい 自己決定したい |
感覚的 のびのびした生きる力 好かれたい、嫌われたくない |
| 自己認識 | 厳しい私、優しい私 | 考える私 | 自由な私、従順な私 |
| 良い働き | 道徳的、正義感、保護的、親切 | 論理的、合理的、客観的、計画的、行動的 | 創造的、自発的、明るくほがらか、謙虚、協調性 |
| 悪い働き | 権威的、威圧的、過保護、偏見、見栄っ張り | 理屈っぽい、打算的 | わがまま、依存的、非自律 |
たとえば、私が胃カメラを受けたときの心の動きを、自我状態で表してみると次のようになります。
「もう無理、怖い!」というC(子どもの自我状態)の感じ方をしながらも、
「これが通常モードなら大丈夫なはず」とA(成人の自我状態)で考え、
さらには「取り乱しではいけない」と親からインプットされたP(親の自我状態)で家に帰るまでは平気なふりをしていました。
そして、ほっとしたらC(子どもの自我状態)の「無理、怖い!」のショックがまだあったので、P(親の自我状態)でゆっくりしようと自分を休ませました。
いかがでしょうか? このように、心の状態、動きを説明できると、自分で心の状態を分析できます。また、考えや行動も予測できます。自分の心に振り回されることも防げるかもしれません。
そのためには、自分の自我状態を意識することが大切です。意識するとは、気づくことですので、A(成人の自我状態)の働きです。今ここで、適切な自我状態が良い働きをしているかな? と考えてみてください。
あなたにとって常識外れだと感じる行動をしている人を見たら、イライラしませんか? 逆に、他の人にとっての「常識」を押しつけられて、嫌な気持ちになることもあるでしょう。それに気づいたら、「こうあるべき」では解決しない場面です。Aを働かせて、自我状態を変えてみましょう。
決断を先伸ばしにしたり、人に決めてもらいたい気持ちになったりすることはありますか? そんなときは、今のあなたは親の教えに守られたり縛られていたりした無力な子どもではないことを思い出しましょう。人に合わせて決めてもいいし、自分で決めてもいい、選択権は自分にあります。
また、合理的、効率的な選択ばかりで毎日を過ごしていませんか? 自我状態の偏りは心の柔軟さを損ないます。仲間と助け合ったり、感謝したり、仕事終わりの夕空に目を向けたり、自我状態が自由に行き来しているか意識してみましょう。

ここまで、心を交流分析の自我状態から理解する方法と、気づき方をいくつかを紹介してきました。
自我状態は1日の中でも一生の中でも、刻々と変わります。良い悪いではなく、自分の現状の傾向はこうとらえることもできるのだなと、自分の心を理解し、より良い毎日にする参考にしていただければと思います。
自分の心は、自分の生きてきた歴史です。これからも心と仲良く人生を歩んでくださいね。
最後に、心について考えるとき、いつも思い出す大好きな詩を紹介します。
八木重吉「心よ」
こころよ
では いっておいで
しかし
また もどっておいでね
やっぱり
ここが いいのだに
こころよ
では 行っておいで
(八木重吉のことば: こころよ、では行っておいで)