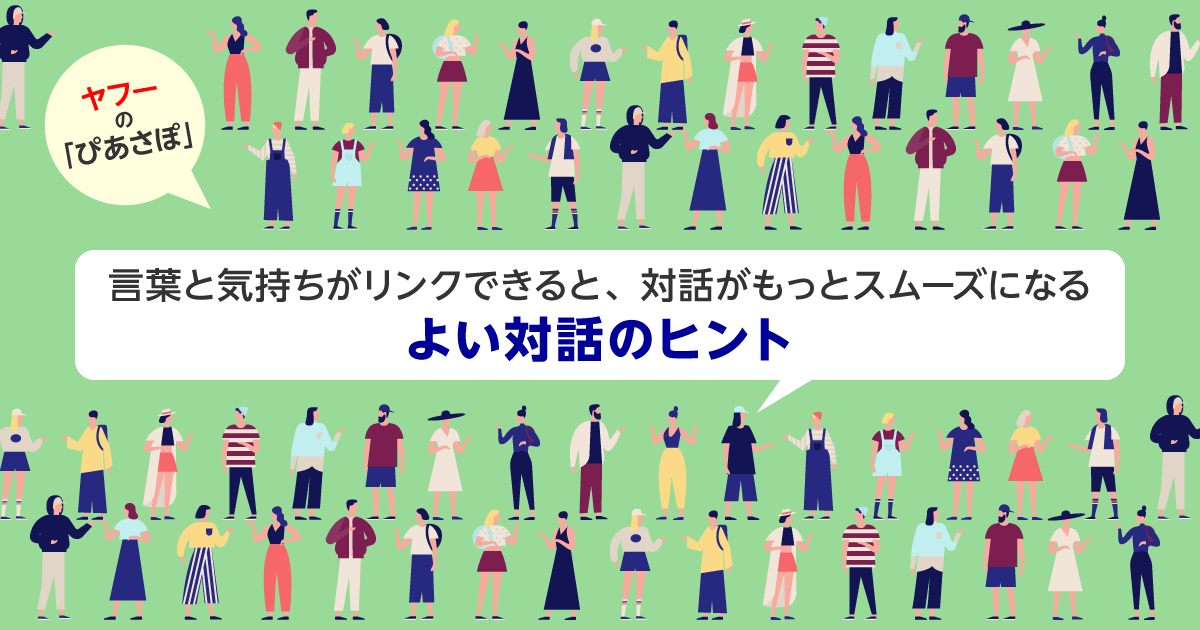産業カウンセラーやキャリアコンサルタントの有資格社員で活動している「YJぴあさぽ」は、同僚を「ピア=仲間」ととらえ、キャリアや人間関係などに関する対話をすることで応援しています。具体的には、定期的に「オープンダイアローグ(※)」と「2on1」を実施しています。
※オープンダイアローグ:
フィンランドで開発された精神科医療の包括的なアプローチで「開かれた対話」と訳されます。YJぴあさぽでは、話すこと、そして聴くこと、「対話」を大事にしたいという思いから、対話の場を「オープンダイアローグ」と呼んでいます。
この連載では、よい「対話」のヒント、そして実際の2on1やオープンダイアローグから、みなさんのコミュニケーションに役立てていただけそうなことを、ぴあさぽメンバーがお伝えしていきます。
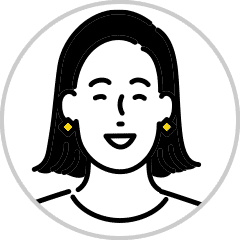
- みーさん
- グッドコンディション推進室で従業員の健康増進企画を担当。夫と高校生の娘の三人暮らし。 保有資格:産業カウンセラー(JAICO)、国家資格公認心理師、交流分析士インストラクター
- 目次:
- その言葉はどんな意図? こめられた理由や気持ちを知ることが大事
- 「自分が使っている言葉の辞書」をアップデートする
- 辞書のアップデートに大切なのは、言葉と自分の気持ちがリンクすること
- あらゆることは訓練・経験、気づいたことが大進歩!
その言葉はどんな意図? こめられた理由や気持ちを知ることが大事
「ちょっとそこのおしょうゆに手が届く?」という言葉は、実は「おしょうゆをとってほしい」という意味。
また、「どうしてそれをしないの?」と言われると、じんわりと圧をかけられていたり、怒られたりしているように感じる人もいるのではないでしょうか。でも、相手は責めるつもりはなく単純に「なぜ?」と聞きたいだけかもしれません。
このように、その言葉がどのような意図で発せられたのか、わからないこともあるのではないでしょうか?
私たちが日々使っている「言葉」は、大体正解の意味が相手に通じるはずだと信じられています。ですが、時と場合によっては伝わらないこともあります。
そして、自分が使う「言葉」の正解と、相手が使う「言葉」の正解がずれていることが続くと、自分が間違っているのか、相手が間違っているのかわからなくなってしまい、コミュニケーションの難しさを感じることになります。
相手の言葉の意味はわかるけれど、どんな気持ちでその言葉を発しているのかがわからないと、不安になるのではないでしょうか。言葉の裏には、その言葉を発した人の考えや気持ちがあります。それには「絶対正解がない」ところに、コミュニケーションの難しさがあるように思います。
今、もし、あなたがコミュニケーションで困っているとしたら、その相手ももしかしたら言葉をうまく使えていないのかもしれません。
ここからは、いくつかのステップで、私たちが対話による支援で大事にしていることを紹介していきます。
「自分が使っている言葉の辞書」をアップデートする
言語形成と人格形成は生まれ育った環境下での経験学習によるところが大きいと思います。育つ過程での偶発的な経験学習なので、人それぞれ違いや偏りがあるのは当然です。
コミュニケーションを改善するためには、まず自分の「偏り」に気づくことが大切です。ですが、言語は常に何気なく使っているものなので、自分では偏りに気づき難いことがあります。また、ちょっと癖があっても、長年使ってきた「自分が使っている言葉の辞書」を変えるのは、そう簡単ではありません。
もし、「自分が今使っている言葉の辞書」をアップデートしたいと思ったら、まずは使っている言葉を意識してみましょう。
仕事の交渉などの複雑な場面ではなく、「自分がお客さん」という場面で意識するのがおススメです。
具体的には、美容師さんやマッサージ師さんなど接客のプロとのコミュニケーションで、自分がどんな風に言葉を使っているかを意識してみましょう。
自分にとって素直に言葉を使えているでしょうか? もし使えていたら、使えていない他の場面とのギャップに気づくかもしれません。
改善したい「コミュニケーションの癖」に気づいたら、もっとしっくりくる言葉に上書きし、自分にとってより良い辞書になるように改善していく。そのようなステップを踏むのが良いと思います。

実践に向けたヒント
・素直なコミュニケーションができる場所はありますか? 人はいますか?
・何気ない会話、たとえば美容院やマッサージ店の店員さんとの会話でも自分の気持ちと一致している言葉を使う練習はできるので、試してみてください
辞書のアップデートに大切なのは、言葉と自分の気持ちがリンクすること
「自分にとってより良い辞書になるように改善していく」とお伝えしましたが、その良い辞書の基準は何でしょうか?
自分にとっての「良い辞書」とは…
・言葉がその通りの意味
・言葉と自分の気持ちが合っている
・他人にもその意味で通じる
だと思います。
たとえば、「悲しい」と言う言葉に「悲しい気持ち」、「うれしい」という言葉に「うれしい気持ち」がちゃんとリンクしている、ということです。
「そんなの当たり前のことなのでは?」と思う人もいるかもしれません。でも、1日のうちで気持ちをあまり意識せずに言葉を口にしている瞬間も多いのではないでしょうか。
むしろ、社会的な役割として、情報を効率よく伝達したり、その場で求められる会話をしたりするときには、まるで役を演じる俳優のように、自分の気持ちはどこか別のところに置いておくのが普通になっているかもしれません。
実は、その時間が長くなりすぎると、次第に言葉と気持ちがリンクしなくなってきてしまいます。本当の気持ちは、無視され過ぎると元気がなくなるからです。そうならないためには、言葉と気持ちがリンクする場所と時間を持つことがとても大切です。
そうすることで、自分の気持ちを大事にしながら(良い辞書を持ちながら)も、職場などにおける、役割上の辞書も上手に使えるようになってくるのではと思います。
自分の気持ちと言葉を一致させることを意識して話し、「役割上の辞書」と、「本当の気持ちの辞書」がいったりきたりすることで、「本当の気持ちはこういう言葉であらわせる!」と自分にとっての正解に近づいていくことがあります。私たちはそのお手伝いをさせてもらっているイメージです。

あらゆることは訓練・経験、気づいたことが大進歩!
これまで書いてきたことを意識しなくても、人間関係のなかで自然にコミュニケーションは行われています。
自分が職場や家庭などで受け持っている役割で多くの人と会ってたくさん話したあとは、一人になりたくなったり、熱い議論を交わした後は、少し気軽な会話をしたくなったりと、「役割上の辞書」ばかりを使ったあとは、「本当の気持ちの辞書」を使って話すことで、気持ちのバランスをとりたくなるかもしれません。
もし、あなたが「どんな場面でも自分らしく言葉が使えたらいいのに」と思ったら、「今は自分にとっての良い辞書を使って話しているかな?」と自分に問いかけてみてください。
まとめ
・みんなそんなに上手に、言葉を使えるわけではない
・大事なのは、言葉と自分の気持ちがリンクすること
・あらゆることは訓練・経験、気づいたことが大進歩!